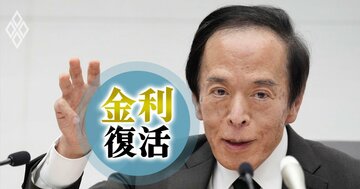Photo:EPA=JIJI
Photo:EPA=JIJI
6月のFOMC(米連邦公開市場委員会)では、年内の利下げ回数の見通しが3月の3回から1回に減少した。インフレ見通しも引き上げられた。利下げ開始時期が大きく後ずれするように受け取れる。しかし、インフレ見通しなどを含め中身を精査していくと、9月利下げ開始の可能性は高い。(みずほリサーチ&テクノロジーズ調査部プリンシパル 小野 亮)
今回のFOMCインフレ見通しは
上昇率低下した5月米CPIを反映せず
6月12日のFOMC(米連邦公開市場委員会)では、年内の利下げ回数が3回から1回へと大幅に変更された。インフレ見通しの悪化を受けた修正とされるが、実はこれらは、見通しと実際の政策運営との間に大きなギャップがあることを露呈している。
FRB(米連邦準備制度理事会)のパウエル議長が好んで使う「3カ月前比年率」というインフレ率の計測方法に従えば、9月の利下げ開始はむしろ確度が高いといえそうだ。ただその先、利下げテンポが早まるかどうかは、雇用情勢や米企業動向にも左右される。パウエル議長をはじめとするFOMC高官が軽視するR-star(自然利子率)の議論も避けられないだろう。
今回のFOMCで最も関心を集めたのが、インフレ見通しの悪化であった。2024年末のコアインフレ率見通しは前回の2.6%から2.8%に引き上げられた。一方、見通し発表の朝、米国労働省が発表した5月米CPI(消費者物価指数)において、コアCPIが前月比0.16%と大幅に減速したことが明らかになった。
そのため記者会見では、「今朝のCPIは反映されているのか」という質問や、「年末までにインフレは悪化する見通しなのか? その中で利下げができるとは思えない」という記者もいた。
パウエル議長は、FOMC当日に発表される経済指標については「一般的には、数人が見通しに反映するものの、ほとんどの参加者は見通しを変更することはない」と説明した。
これまでの記者会見や講演などでも繰り返し指摘されてきたことだが、特定の経済指標ではなく、さまざまな指標から総合判断するという、いわば「規律」が見通し策定作業にも働いているということだろう。
パウエル議長の説明を読み解くと、実はFOMC参加者は、4月米CPIが見せたディスインフレの胎動を「あえて」軽視して見通しを作成した様子も浮かび上がる。
1月から3月までの米CPIでは前月比0.4%というコアインフレ率が続き、インフレ再燃のリスクが高まっていた。しかし5月に発表された4月のコアインフレ率は前月比0.3%と減速し、ディスインフレ再開への期待を高めるものだった。
当然、ディスインフレがさらに進んだ5月米CPIと合わせれば、その期待は一段と強まったはずである。しかし、FOMC参加者らがインフレ見通しを作成する段階では、ディスインフレは4月だけの現象に過ぎず、見通しに織り込むのは楽観的過ぎる。
その結果、今回発表されたインフレ見通しは「インフレ再燃リスク」を強く意識したものにならざるを得なかったのである。
しかし今回のFOMCを経て、ディスインフレは2カ月連続で観察されたことになった。9月会合までに発表される3カ月分のインフレ指標の大半が落ち着いた内容なら、9月利下げの蓋然(がいぜん)性は高い。
なぜそうなるのか。次ページ以降、データを基に解説していく。