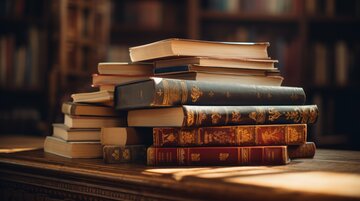【老後】「死ぬのが怖い」の超意外な正体とは?
世界的名著『存在と時間』を著したマルティン・ハイデガーの哲学をストーリー仕立てで解説した『あした死ぬ幸福の王子』が発売されます。ハイデガーが唱える「死の先駆的覚悟(死を自覚したとき、はじめて人は自分の人生を生きることができる)」に焦点をあて、私たちに「人生とは何か?」を問いかけます。なぜ幸せを実感できないのか、なぜ不安に襲われるのか、なぜ生きる意味を見いだせないのか。本連載は、同書から抜粋する形で、ハイデガー哲学のエッセンスを紹介するものです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
もし、あした死ぬとしたら、今までの日々に後悔はありませんか?
【あらすじ】
本書の舞台は中世ヨーロッパ。傲慢な王子は、ある日サソリに刺され、余命幾ばくかの身に。絶望した王子は死の恐怖に耐えられず、自ら命を絶とうとします。そこに謎の老人が現れ、こう告げます。
「自分の死期を知らされるなんて、おまえはとてつもなく幸福なやつだ」
ハイデガー哲学を学んだ王子は、「残された時間」をどう過ごすのでしょうか?
【本編】
「これから『人間は存在について語れないにもかかわらず、なぜか存在についてわかってしまっている』という不思議な事実について話そう」
「人間が存在をわかっている?」
「実際そうではないだろうか。今までさんざん『人間は存在について語れない』と言ってきたわけだが、そうは言ってもおまえだって『存在』という言葉の意味はなんとなくは理解しているだろう?」
「はい、しています」
私は大きくうなずいて続けた。
「実は、そこに違和感があったのです。存在について語れないと言いつつも、日常的に私たちは『存在する』や『ある』という言葉を話して使っています。使っているわけですから、それらの言葉を理解している、わかっているということですよね?」
ハイデガー哲学の核心とは?
「その通りだ。わかっていなかったら、当然それらの言葉は使えないだろう。だから、やはり人間は、存在とは何かがわかっているのだ」
「語れないのに、ですか?」
「そう! まさにそこだ! そこがこの話の肝であり、ハイデガー哲学の入り口における核心部分でもある。いいだろうか。人間は、存在とは何かが語れないにもかかわらず、存在の意味を理解し、存在を土台とする言語を駆使している。これは、どう考えても不思議で神秘的なことではないだろうか?」
「たしかに不思議な感じはします。神秘的かと言われるとちょっとわかりませんが」
「いやいや、それを神秘的と思えるかどうか、ここが哲学を志す人間においてもっとも重要な資質であり、理解のターニングポイントだ。もっと具体的に言えば、人間自体を神秘的なものとして捉えられる感性があるかどうか。もし、人間が神秘的なものではないとするなら、人間という生物は、タンパク質という有機物の塊―言わば機械のようなものであり、壊れたら動かなくなる、ただそれだけのモノに成り下がってしまうだろう。もし、人間が、そうした機械、ただのモノにすぎないとするならば……、人間には尊厳もなければ、世の中に正義も美もない―すなわち哲学をやる意味すらなくなってしまうのではないだろうか」
「人間がただの機械にすぎないのだとしたら……」
私は、歯車じかけの玩具の人形を思い浮かべ、それが人間だと考えてみた。そして、その人形たちがたくさん並んでいる状態を国家だと考えてみる。たしかに、それはぞっとする光景だった。そうだとすると人間の営みはすべて、組み合わさった歯車がギシギシと規則通りに動いた結果であり、その人形たちが「ア・イ」「セ・イ・ギ」と音を発したところで、そこには何の意味もないように思えたからだ。
死ぬのが怖い。そのシンプルな理由
「なるほど、言いたいことがわかった気がします。少しずれますが、死が怖い理由も、その話につながっていると思いました。私はただのモノであり、死んだら終わるだけの肉の塊にすぎない……。もちろんそんなふうに自分を思いたくはありませんが、死はそのことを容赦なく突きつけ、『すべてを無意味だと感じさせてしまう』―だから怖いのだと思うのです」
「うむ、まさにその通りだな。もちろん、そうは思わないという人もいるだろう。『人間はただのモノで、死んだら終わりだ』と言われても、何にも感じず『そんなこと知ってるよ、だからどうした』と軽く答える者もいるかもしれない。
だが、そういう者でも明日死ぬぞと言われ、死が差し迫っていることを唐突に知れば、そんなことは言っていられないはずだ。おそらくは『なぜだ? どうしてだ?』と取り乱し、人生が消えて無くなることに慌てふためくだろう。人間は、無意味―虚無に耐えられるようにはできてはいないのだ」
(本原稿は『あした死ぬ幸福の王子ーーストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」』の第1章を抜粋・編集したものです)