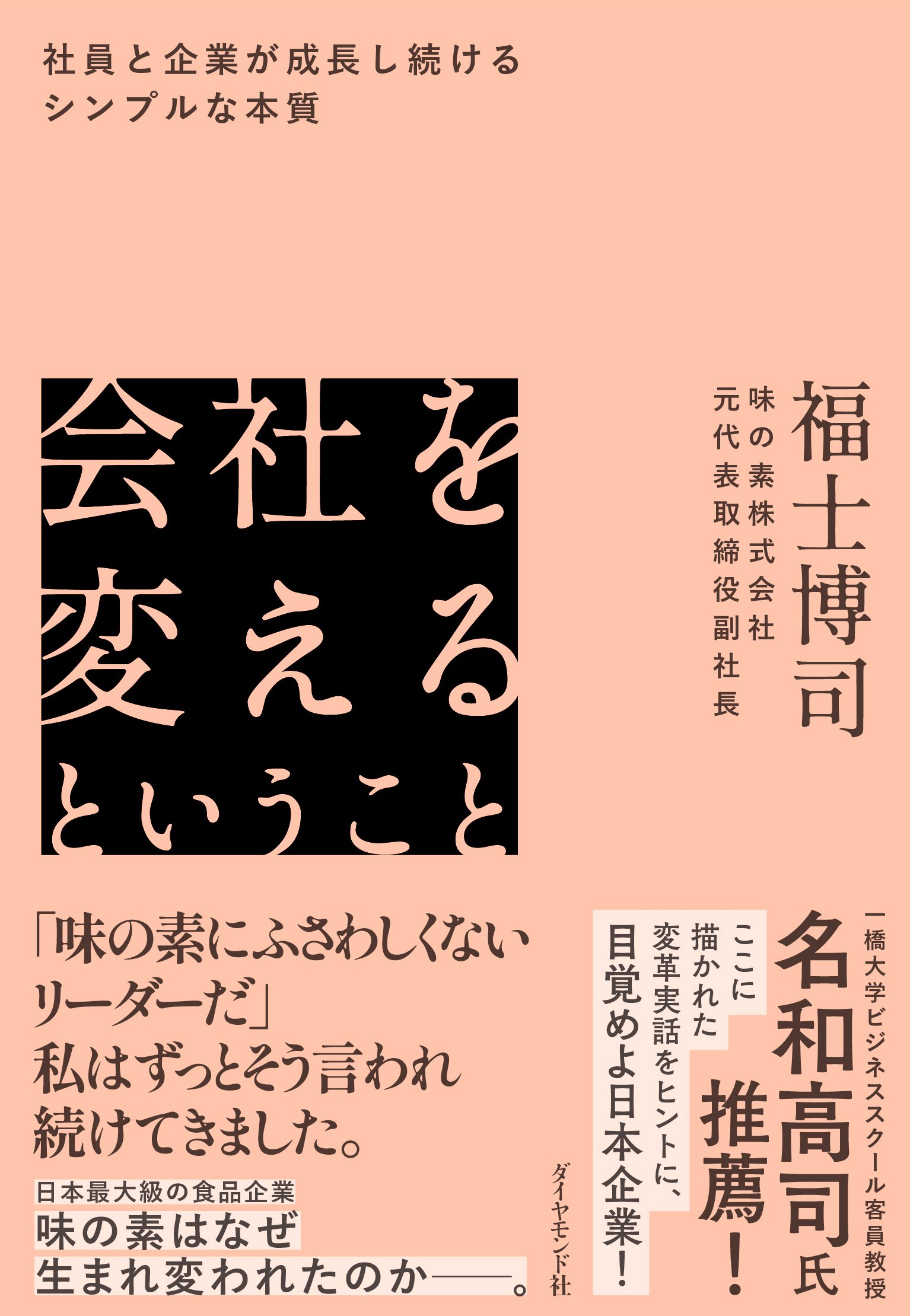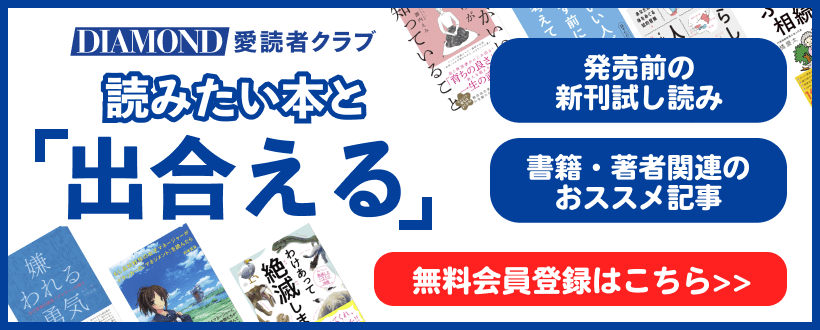会議ばかりしていて、物事が前に進まない
こうなると実作業よりも、すり合わせの時間が長くなる傾向も顕著です。結果として起こるのは、多種多様の会議に同じメンバーが集まってしまう、会議だけはこなすが活動はさっぱり進まないという非常に生産性の低い状況です。この事態にすでに陥っている企業も多いのではないでしょうか?
そんな状況で、新たに全社でDXを始めると言われても、それこそ、忙しすぎて対応できませんというのが現場の実体だと思います。理想的には、事業縦割りの力学をポートフォリオマネジメントで整理、進化させると同時に、種々の横軸活動も、企業の目指すべき北極星であるパーパスにしたがって整理、進化させていくべきです。
しかし、このような美しい流れのなかで仕事が進んでいく企業はあまりなく、実際のDX導入は、さまざまな横軸機能とその活動とのぶつかり合いのなかで、泥縄式にやっていくしかありません。
泥縄式でやっていくしかないのですが、それに消費される内部エネルギーの量は莫大です。その効率性に限界を感じた私は内部だけへのアピールではなく、外部へもアピールし、その評判をもって社内のDXへの熱量を上げることができないかと考えるようになりました。
当然、まだ全社としてのDXの実績はほとんどなかったので、西井社長と相談し、味の素のDXは当時あらたに設定したパーパスである「食と健康の課題解決企業」を実現するためのものであり、パーパス経営への転換と一体になったものでもあるという考え方を前面に出すことにしました。
要するに、味の素は社会のDXの波に乗るが、それが目的ではなく、もっと重要なパーパスの実現のためにDXをやるのだという認識を社内レベルのみならず、外部や日本の社会的な認識にしたかったのです。