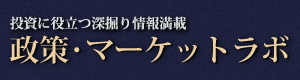Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
6月の実質賃金 前年同月比1.1%増
だが手放しでは喜ぶわけにはいかない
毎月勤労統計調査(6月速報)によれば、6月の実質賃金(現金給与総額、事業所規模5人以上)の対前年同月比が1.1%と、2年3カ月ぶりにプラスになった。
これまで長く実質賃金の低下が続いてきたが、やっとその傾向に変化の兆しが現れたことになる。
今年の春闘の平均賃上げ率は5.1%と33年ぶり高水準を実現し、その影響が6月分からの実際の賃金に反映されると考えられていたが、実際にそうなり、そして、「賃金と物価の好循環」が始まったと評価する声が少なくない。
8月15日に公表された4~6月期GDP統計では、マイナスが続いていた実質個人消費も5四半期ぶりに前期比プラスに転じた。
しかし、いまの事態を手放しで喜ぶわけにはいかない。
なぜなら、6月の実質賃金の対前年比プラス転化は、ボーナスの増加という一時的な要因が大きかったからだ。
他にも今回の実質賃金プラス化を素直に喜ぶわけにはいかないより重要な理由がある。