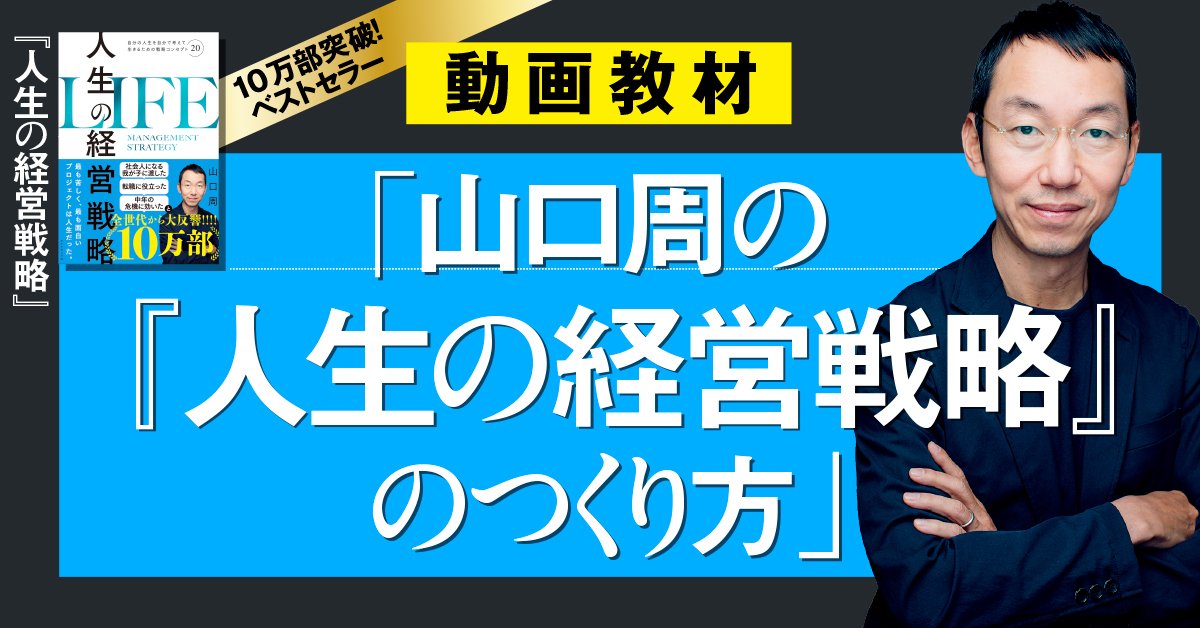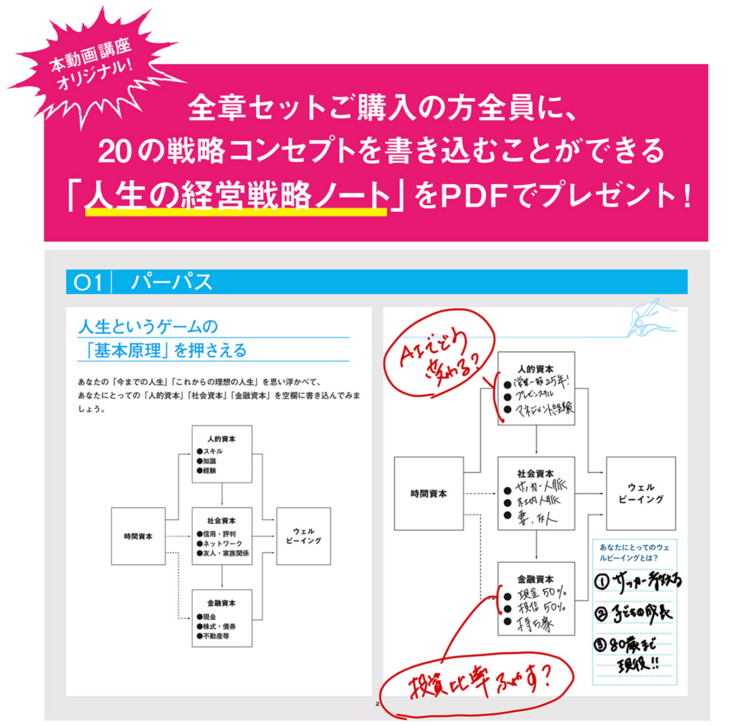「あなたは人生というゲームのルールを知っていますか?」――そう語るのは、人気著者の山口周さん。20年以上コンサルティング業界に身を置き、そこで企業に対して使ってきた経営戦略を、意識的に自身の人生にも応用してきました。その内容をまとめたのが、『人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』。「仕事ばかりでプライベートが悲惨な状態…」「40代で中年の危機にぶつかった…」「自分には欠点だらけで自分に自信が持てない…」こうした人生のさまざまな問題に「経営学」で合理的に答えを出す、まったく新しい生き方の本です。この記事では、本書より一部を抜粋・編集します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
行き詰まった米企業が取った、驚くべき行動
本書で紹介している経営戦略、ベンチマーキングとは、ある組織や個人が他者の成功事例やパフォーマンスを基準に、自らのプロセスや成果を比較・評価し、改善策を導き出す経営手法です。
ベンチマーキングの概念は、1980年代にアメリカのゼロックス社が、自社の業務改善のために組織的に導入したのが始まりと言われています。当時、ゼロックスは日本のメーカー、中でもキヤノンから強い競争圧力を受けていました。
ゼロックスは複写機に関する特許のほとんどを独占していましたが、それらの特許に抵触しない形で、まずは70年にキヤノンが普通紙複写機市場に参入し、これにリコーやミノルタが続いた結果、一時期は100%に届くかと思われた市場シェアは、82年には13%にまで落ち込んでしまいます。
何が問題だったのでしょうか?
競合となる日本企業と比較すると、ゼロックスの製品は品質が悪く、コストは高く、開発期間は長くかかっていました。これでは競争に負けるのは当たり前です。
彼らは自分たちの劣位を謙虚に認め、日本企業をお手本として改革を進めることを決心したのです。
ゼロックスの経営陣がまずやったことは、安くて高品質な競合企業の製品をバラバラにして調べてみることでした。これを経営用語ではリバース・エンジニアリングと呼びます。結果、彼らはその品質の高さ・コストの低さに驚愕します。なぜ、こんなことができるのか?
ゼロックスの経営陣は直球のアプローチを採用し、富士ゼロックスに調査協力を依頼して、調査チームを送り込み、結果「市場で敗北する前に、工場で敗北していた」ということを理解します。
やがて、ゼロックスによるベンチマークの効果は、業界を超えて知られるようになり、その後は自動車、エレクトロニクスなどの業界でも盛んに日本企業のベンチマークが行われるようになり、米国の企業変革の核となっていきます。
一流ほど、どんな相手からも「謙虚に真似る」
今から思えば、米国企業によって日本企業を対象としたベンチマークが盛んに行われた1980年代という時代は、衰退する米国経済が底を打って反転攻勢に出る、まさにターンアラウンドの時期だったのかもしれません。
なぜなら、こういった取り組みが米国企業によって大々的に行われたということが、深いレベルにおける米国ビジネスパーソンのマインドセットの変容を象徴的に表していると思うからです。
米国は、主に欧州からの移民によって成立したという歴史的な経緯の影響もあって、個性や独自性を重んじ、特にビジネスやエンタテインメントの分野では「他者の模倣」に対して批判的な立場を取ります。
したがって、彼らにとって「他者の模倣をする」というベンチマーキングの考え方は、深いレベルでの精神性の変容がなければ、絶対に受け入れられるものではなかったのです。しかも、模倣の対象となっているのは、太平洋戦争で完膚なきまでに叩きのめした、あの東洋の貧乏国なのです。
本当の企業変革は、精神レベルでの変容がなければ推進できない、とは企業変革の世界でよく言われることですが、80年代の米国による、言うなれば「身も蓋も無い」取り組みは、米国のビジネスパーソンのあいだで、そのような深いレベルでの変容が起きていたことを示しています。