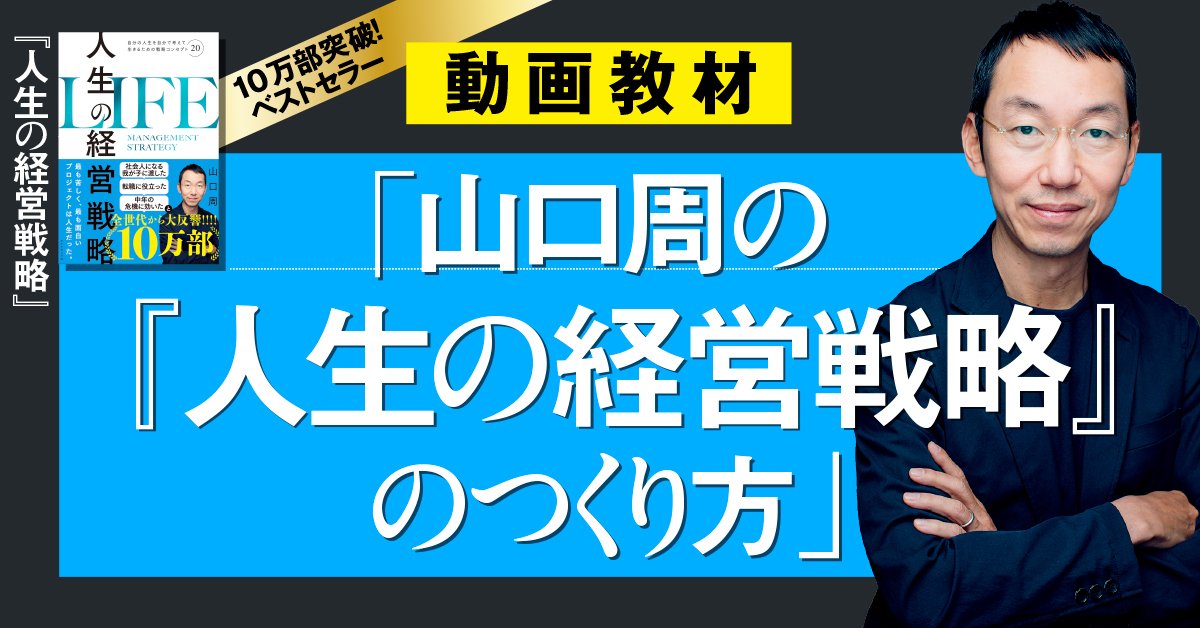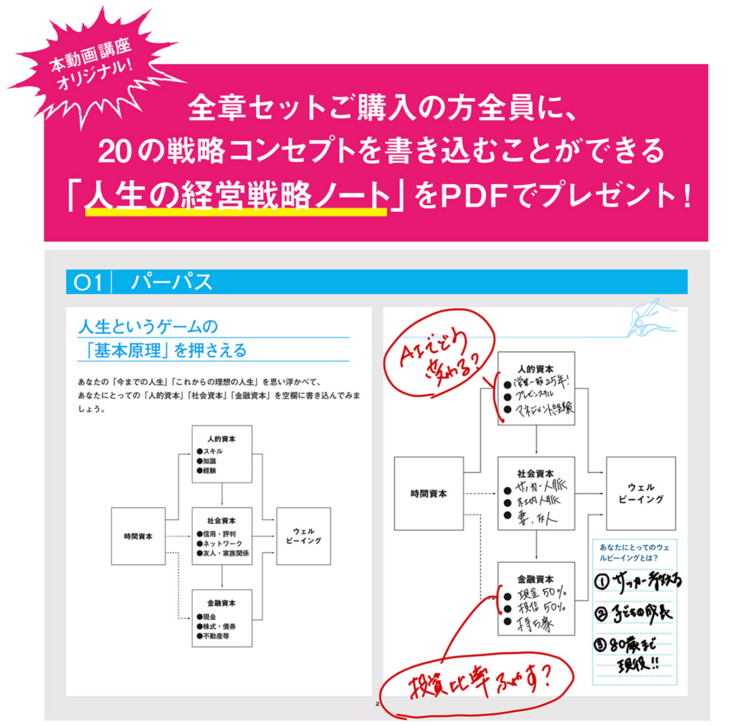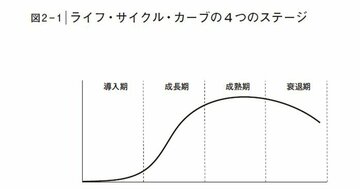20年以上コンサルティング業界で培った経営戦略を人生に応用した『人生の経営戦略』の著者・山口周氏と『君は戦略を立てることができるか』の著者・音部大輔氏。初対面ながら意気投合した両氏が、「戦略論」について熱く語り合った。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
ゲームで学んだ「戦略思考」
――山口さんは、音部さんの『君は戦略を立てることができるか』を、どう読まれましたか?
山口周(以下、山口) 音部さんといえば外資畑のクールなイメージなのに、この本では織田信長の「桶狭間の戦い」を事例に出してくるなど、歴史マニアっぽい記述が多い。その意外性が面白かったですね。
音部大輔(以下、音部) 歴史は昔から好きなのですが、中学生のころ「パンツァーブリッツ」(第二次世界大戦の東部戦線を舞台にした戦術級シミュレーションゲーム。六角形に区切られた盤上で、勝利条件を満たすべく戦車・歩兵・砲兵などの駒を動かす)というボードゲームにハマったのが大きいですね。
このゲームを通じて、ずっと戦略について考えていました。いわゆる「1万時間ルール」でいうと、大人になるまでにはそれくらいやり込んでいたので、キャリアスタートの時点ですでに戦略の専門家だったと言えなくもない(笑)。
山口 「パンツァーブリッツ」、懐かしいなあ。パッケージのデザインもいいんですよね。実はメルカリで買おうかと思っていました。
これね、資源を分散させると必ず負けるんですよ。だから、兵力のトータルの量で比べるのではなく、局面で投じる量がやっぱり重要なんです。桶狭間の戦いもそうですよね。数万人の今川軍に対して織田軍はせいぜい3000人ですから、トータルでは勝ち目がない。そこで、大将である今川義元の首を取るという一点突破に賭けて成功した。「ある局面において優勢な状態を作る」ということをやらないと、絶対に戦いには勝てないんです。
音部 同じ盤面ゲームでも、パンツァーブリッツが将棋などと根本的に違うのは、敵と自分の条件が同じではないということです。つまり、手持ちの資源が違う。
ここから学んだ戦略の重要なエッセンスの一つが「強み」に対する考え方です。お互い条件が異なるなかで「違いが強みになる状況」を探せれば勝てるんですよ。
山口 こと戦いに及んで、一から強みを探している場合ではない、と。
音部 そうです。発想が逆なんです。
もうひとつ重要なのは、シミュレーションゲームには「勝利条件」という概念があって、何をもって勝ちとするかがルールで決められていることです。ところが、ビジネスではそれがないことが多いんですよね。
勝利条件を決めたうえで目的を設定しましょうというのは、私にとっては必然なのですが、なぜかそう言うとビジネスの現場では嫌われたりするんですよ。
山口 以前、チームがサンプリングをやりたいというので、「目的は何ですか?」と聞いたところ「お客様との出会いを増やすこと」と言われるくだりがありますね。堂々と答えられると、はたして突っ込んでいいものか迷いそうです。これでは達成できたかできなかったかがメジャラブル(測定可能)でないので、目的の体を成していない。
音部 さらに言うと、サンプルを配る会社なら「3ヶ月で10万人に配りましょう」でいいのですが、施策としてサンプリングを行う場合、試用を増やしたいのか、認知を上げしたいのか、購買意向を上げたいのか――というところまで記述しておかないと、ただサンプルを配るだけで終わってしまう。
つまり、手段が目的化してしまい、単なる行動の記述が目的っぽく見えてしまう。そういうケースが非常に多いのです。
でも、目的を「勝利条件」と言い換えると枠組みがハッキリする。これまた、あまり勝利、勝利というと嫌がる人がいるんですけどね。
名将はみんな「目的の再解釈」がうまい
山口 音部さんの戦略論では、前回も話題に出た「目的の再解釈」という考え方がきわめて重要になってきます。つまり、手持ちの資源が目的を達成するのに不足している場合は、目的そのものを捉えなおすということですね。
歴史上、戦略の天才というのはみんな目的の再解釈がすごく上手なんです。織田信長もそうですし、ナポレオンもそうでした。ナポレオンが大出世するきっかけになった「トゥーロンの戦い」(1793年)も、目的の再解釈の良い事例だと思います。
当時トゥーロンの港はイギリスに占拠されていたのですが、フランスにとっては要の港だったので、どうしても取り返したい。そこで港を海から包囲して何度も突撃するのですが、一向に勝てなかった。
そのとき、当時20歳そこそこだったナポレオンが、「近くに山があるじゃないか。この山の上に大砲を持っていって、そこから港を撃てばいい」と提案するんです。山は比較的手薄だったので、占領に成功し、そこに砲台を築いて撃ちまくった。そうなると港にいるイギリス軍はたまりません。結局、港から撤退せざるを得なくなって、フランスは港を取り返すことができたのです。
つまり、港そのものを攻めるのではなく、近くの丘を取るというふうに目的の再解釈をすることで勝てたという、僕の大好きなエピソードです。
(第4回に続きます)
1970年東京都生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。ライプニッツ代表。
慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科修了。電通、ボストン コンサルティング グループ等で戦略策定、文化政策、組織開発などに従事。
『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社新書)でビジネス書大賞2018準大賞、HRアワード2018最優秀賞(書籍部門)を受賞。その他の著書に、『武器になる哲学』(KADOKAWA)、『ニュータイプの時代』(ダイヤモンド社)、『ビジネスの未来』(プレジデント社)、『知的戦闘力を高める 独学の技法』(日経ビジネス人文庫)など。
音部大輔(おとべ・だいすけ)
17年間の日米P&Gを経て、ダノンやユニリーバ、資生堂などでマーケティング担当副社長やCMOとしてブランド回復を主導。2018年より独立、現職。家電、化粧品、輸送機器、放送局、電力、広告会社、D2C、ネットサービス、BtoBなど国内外の多様なクライアントのマーケティング組織強化やブランド戦略立案を支援。博士(経営学 神戸大学)。著書に『なぜ「戦略」で差がつくのか。』(宣伝会議)、『マーケティングプロフェッショナルの視点』(日経BP)、『The Art of Marketing マーケティングの技法-パーセプションフロー・モデル全解説』(宣伝会議、日本マーケティング学会「日本マーケティング本大賞」で2022年の大賞受賞)などがある。最新刊『君は戦略を立てることができるか』。