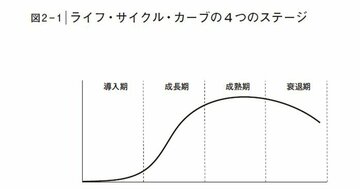20年以上コンサルティング業界で培った経営戦略を人生に応用した『人生の経営戦略』の著者・山口周氏と『君は戦略を立てることができるか』の著者・音部大輔氏。初対面ながら意気投合した両氏が、「戦略論」について熱く語り合った。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
起こってほしい未来を過去形で記述する
山口周(以下、山口) 今回の対談で、戦略においては「目的の再解釈」がたいへん重要だという話をしました。ただ、目的の再解釈というのは、認知的にきわめて難しい作業です。そこで音部さんが提案しているのが「起こってほしい未来を『過去形』で記述してみる」というユニークなメソッドなのですが、これはどうやって考案されたのですか?
音部大輔(以下、音部) 何か脳科学系の本を読んでいたときに、未来を過去として考えるという技術があり、単純に未来のことを考えるのとはちょっと違う脳の働き方をするということを知りました。そこで実際にやってみたら、確かにうまくいくんですよ。
山口 例えば「売上をいくら上げる」という目的を、「売り上げがいくら増えた」と過去形で記述すれば、そこに至るまでの出来事を「シェアがこれくらい増えた」とか「新規顧客をこれくらい獲得できた」といった、より具体的でメジャラブルな形で書き換えられるようになるということですね。
音部 山口さんにはこういう表現のほうがしっくりくるかもしれないですが、これはおそらく、仮説の「アブダクション」なんです。
ご存じのように、仮説の立て方としては、帰納法と演繹法がよく知られています。
帰納法というのは、複数の事例をもとに「地球も火星も木星も丸いから、土星も丸いはずだ」と推論すること。一方、一般的な原理をもとに「惑星は重力に対して等距離を構成しようとするから、土星は球体であるはずだ」と推論するのは、演繹法の考え方です。
では、アブダクションとはどういう考え方か。これも惑星の話で説明すると、19世紀のある科学者が、天王星が計算とは違う動きをしていることに気づきました。その事実のみをもとに考えるなら、ニュートン力学が間違っていることになります。
しかしここで「天王星がこういう動きをするからには、その外側に別の重力体が存在するはずだ(そうすれば自然に説明できる)」と考えるのがアブダクションです。果たして、その仮説をもとに観測を行った結果、発見されたのが海王星でした。
つまりアブダクションとは、ある出来事をいったん「事実」として説明できる何かを探しに行く推論の方法なんですね。このアブダクションの手法を身につけると、目的の再解釈がしやすくなるのです。
エドワード・デボノの「水平思考」
山口 いまの話を聞いていて、エドワード・デボノ(心理学者)の『水平思考の世界』という本に書かれていたエピソードを思い出しました。
17世紀の金貸しが、借金を返せなくなった父娘にある提案をします。袋に白と黒の小石を一個ずつ入れるので、そこから白の石を取り出したら借金は帳消しにする。代わりに黒を取り出したら、娘を自分の妻によこせと。
ところが娘がちらっと見たら、金貸しは袋の中に黒い石を二つ入れていた。つまり、父娘にとっては確実に負けるゲームです。でも、ここで「お前ズルじゃないか」と言ったらゲームはご破算になって、父親は牢屋に入らなくてはならない。
そこで娘はどうしたか。石を取り出してから、わざと落とすんです。「すみません、うっかり落としちゃいました。でも、袋の中を見れば、私が取り出した石が何色だったかわかりますよね」と。袋の中を見ると黒い石が残っているので、白い石を取ったことになる。
つまり「白い石を取る」のではなく「黒い石を残らせる」というふうに、目的を再解釈したわけです。これもまさにアブダクションですね。
競合が「ロイヤルミルクティー」を後押ししてくれる
山口 もう一つ、音部さんの本で面白いのが、資源の捉え方です。通常、資源はヒト・モノ・カネで考えますが、音部さんが考える資源の幅はもっと広くて、あらゆるものが資源になり得る。とりわけ「競合」ですら資源になるという指摘は重要だと思いました。
音部 競合の動きは資源化しやすいんです。わかりやすいのが、リプトンのティーバッグの事例ですね。
リプトンのティーバッグはホッチキスがついてないので、電子レンジが使えるのが特徴です。電子レンジで紅茶を淹れる人はあまりいないかもしれませんが、「ロイヤルミルクティー」をつくるのにはたいへん都合がいい。茶葉をいちいちミルクで煮出さなくても、レンジで加熱すれば済むからです。
この、ロイヤルミルクティーを押し出したマーケティングが功を奏して、リプトンはシェアを伸ばしました。
すると、今度は競合の紅茶ブランドが「本物のロイヤルミルクティーのつくり方」というキャンペーンを、すごくお金をかけてやってくれた。競合としては、リプトンのやり方は本式ではないとアピールしたかったのでしょうが、結局は便利なほうが顧客に受け入れられ、競合の動きはむしろ電子レンジでつくるリプトンの「ロイヤルミルクティーを後押しすることになった。つまり、競合が「資源化」したのです。
山口 マイケル・ポーターも『競争優位の戦略』の中で同様のことを述べています。新しい市場をつくっていかなくてはならないときに、競合企業がその市場の有用性を強調するほど、マーケットは盛り上がる、と。
近年ではテスラがいい例で、彼らはEVというアジェンダを先取りしました。その結果、他の自動車メーカーが「やっぱりEVが大事」「環境に意識の高い人はEV」「先進的な人はEV」と言えば言うほど、結果的には自分のお金を使って競合であるテスラのブランド価値を高めるようなことになったわけです。
ただ、こうしたことが明確にマーケティングの事例として語られている本はあまり見たことがないので、その点でも音部さんの本を面白く読ませていただきました。
音部 山口さんの『人生の経営戦略』と、私の『君は戦略を立てることができるか』は、同じテーマを違う角度から論じているようなものです。なので、読者のみなさんには、ぜひ2冊併せて読んでほしいですね。本というものは1冊読んだだけだと、なんとなくわかった気になって終わりがちなのですが、複数の視点を介することで、ぐっと解像度が深まりますから。
1970年東京都生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。ライプニッツ代表。
慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科修了。電通、ボストン コンサルティング グループ等で戦略策定、文化政策、組織開発などに従事。
『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社新書)でビジネス書大賞2018準大賞、HRアワード2018最優秀賞(書籍部門)を受賞。その他の著書に、『武器になる哲学』(KADOKAWA)、『ニュータイプの時代』(ダイヤモンド社)、『ビジネスの未来』(プレジデント社)、『知的戦闘力を高める 独学の技法』(日経ビジネス人文庫)など。
音部大輔(おとべ・だいすけ)
17年間の日米P&Gを経て、ダノンやユニリーバ、資生堂などでマーケティング担当副社長やCMOとしてブランド回復を主導。2018年より独立、現職。家電、化粧品、輸送機器、放送局、電力、広告会社、D2C、ネットサービス、BtoBなど国内外の多様なクライアントのマーケティング組織強化やブランド戦略立案を支援。博士(経営学 神戸大学)。著書に『なぜ「戦略」で差がつくのか。』(宣伝会議)、『マーケティングプロフェッショナルの視点』(日経BP)、『The Art of Marketing マーケティングの技法-パーセプションフロー・モデル全解説』(宣伝会議、日本マーケティング学会「日本マーケティング本大賞」で2022年の大賞受賞)などがある。最新刊『君は戦略を立てることができるか』。