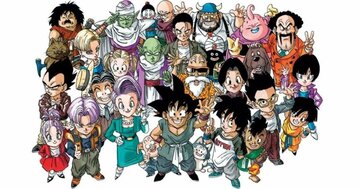「たばこを吸うべからず」の立て札を
引っこ抜く怒りのスナフキン
『たのしいムーミン一家』が、ムーミントロールとスナフキンのいちゃいちゃしている場面から始まって、終盤にスナフキンを思って悲しむムーミントロールの描写があるのと対照的に、『ムーミン谷の夏まつり』は、スナフキンを恋しがるムーミントロールの描写から始まり、ムーミントロールとスナフキンの再会がクライマックスで描かれます。
作品が執筆された背景に視線を転じると、トーベはすでに1952年にアトス(編集部注/アトス・ヴィルタネン。ムーミンの連載の場を提供した新聞の編集長で、スナフキンのモデルになったとされる)と恋人としては決定的に破局していましたが、彼はたいせつな友人としてトーベの心に住みつづけることになりました。
『ムーミン谷の夏まつり』では成りゆき上、置きざりにされたり迷子になったりした24人の子どもたちの世話を焼くことになるスナフキンが描かれます。ふだんのスナフキンには父性的な印象がありませんから、意外なイメージと言えるでしょう。さらに意外なのは、いつもの飄々とした態度を捨てて、反逆児的な姿を見せる場面があることです。おそらく現実上のアトスをむしろ反映しているのかもしれません、それはつぎのようなスナフキンの公園での行状です。
スナフキンは、自分のしたいことをぜんぶ禁止している立てふだを、残らず引きぬいてしまいたいと、これまでずっと思いつづけてきました。ですから、
(さあ、今こそ!)
と考えただけでも、身ぶるいがするのでした。
まず、『たばこを吸うべからず』のふだから始めました。
つぎには、『草の上にすわるべからず』をやっつけました。
それから、『笑うべからず、口笛を吹くべからず』に飛びかかり、
つづいて、『両足で飛びはねるべからず』を、ずたずたにふみつけました。
小さい森の子どもたちは、ただただあっけにとられたまま、スナフキンを見つめていました。(『夏まつり』p.118)
他人に自由を制限されたくないスナフキンは、じぶんの自由を守るためなら、こんなに大胆に乱暴になるのだと考えられます。
美しい自然描写にも見出せる
ニューロマイノリティの感性
さて、またまた自然描写の話をしておきましょう。本作でも、やはりムーミントロールと水の親和性が強調されています。スナフキンを恋しがるムーミントロールは、ぼんやりとした目つきで池の横に寝ころんでいます。とても個人的な意見ですが、私はムーミン・シリーズすべての挿絵のなかで、この場面でのムーミントロールの絵がいちばん好きです。横たわった彼のまわりでは自然界が初夏を謳歌しています。
池のまわりには、すべすべしてつやのある大きな葉っぱがしげっていて、トンボやミズスマシがその上で休んでいました。水面の下では、いろんな小さい虫たちが、ゆうゆうと動きまわっています。もっと下のほうには、カエルが目を金色に光らせていました。いちばん底のどろの中に住んでいる、カエルの親類みたいなおかしな生きものが、ちらりとすがたを見せることもありました。(『夏まつり』p.12)