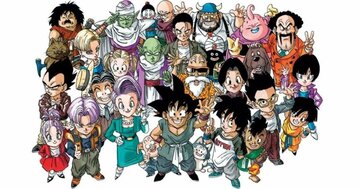Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
日本でもお馴染みのムーミン・シリーズを、発達障害当事者である文学研究者の横道誠氏が独自の観点から読み解いている。牧歌的な物語に見える「ムーミン」だが、よく読めば性的絶頂や同性愛を暗示している箇所が見られるのだという。本稿は、横道 誠『なぜスナフキンは旅をし、ミイは他人を気にせず、ムーミン一家は水辺を好むのか』(ホーム社)の一部を抜粋・編集したものです。
「自閉的」で我が強い住人が集まる
ムーミン谷が意外にも平和な理由
私が思うに、ムーミン谷とはおそらく、トーベ(編集部注/トーベ・ヤンソン。ムーミン・シリーズの作者である女性)自身が属していた芸術家たちや学者たちのコミュニティのメタファー的存在です。それが共同体として理想化された姿が、ムーミン・シリーズに描かれているのではないでしょうか。
ニューロマイノリティ(編集部注/神経学的少数派=注意欠如多動性障害や自閉スペクトラム症などの症状を持つ人のことを非病理的に捉えなおした表現)は芸術家に適していると見なされることが多いです。それもあって、芸術家の世界には似たもの同士が多いと思うのですが、しかし彼らは「自閉的」な傾向を持つためにとても我が強い人たちなわけです。それがときには、深刻な葛藤ももたらすはずです。共同体の存続が危機に瀕することだってあるかもしれません。
そういう現実とは裏腹に、ムーミン谷はあくまで平和です。「自閉的」で我が強いキャラクターだらけなのに、そして彼らはバラバラに行動しているのに、共同体は問題なく持続していきます。そのようなムーミン谷は、トーベにとって「現実もこうだったら良いのに」と感じさせる理想郷だったのではないでしょうか。
『ムーミン谷の夏まつり』を見てみましょう。夏が舞台ということ、作中で演劇が上演されるということから、トーベはシェイクスピアの喜劇、とりわけ『真夏の夜の夢』を意識してこの作品を書いたのではないか、と推測できます。
本作の献辞は、舞台演出家だったヴィヴィカ(編集部注/ヴィヴィカ・バンドレル。トーベと恋愛関係にあった女性)に捧げられています。ヴィヴィカとの恋愛は早くに散ったのですが、ふたりは友人として信頼関係を維持しました。
スノークのおじょうさんが見せる
エクスタシーの表情
1948年に『たのしいムーミン一家』でトーベが人気作家になると、ヴィヴィカの発案で最初のムーミン演劇が構想され、1949年の年末に『ムーミン谷の彗星』が『ムーミントロールと彗星』として舞台化されました。これらの経験が、『ムーミン谷の夏まつり』にみなぎる賑やかな印象と、クライマックスを構成するムーミンパパが台本を書いた『悲劇「ライオンの花よめたち─血のつながり」』へと発展したのだと思われます。
本作では、スノークのおじょうさんのヒロインとしての魅力が爆発しています。とくに劇場で衣装部屋に入る場面ではフェミニティがあふれています。
「衣装……服……ドレス!」
小さく声に出して、ドアのハンドルを動かすと、中へ入りました。
「まあ、すてき!ほんとに、なんてきれいなんでしょう」
おじょうさんは、胸がどきどきしました。
ドレス、ドレス、ドレス。ドレスばかりが見わたすかぎり、いく百となく、ぎっしりとならべられて、何列も長々とつり下がっているではありませんか。金銀の糸で作られたドレスも、雲のようにふわふわのチュールや白鳥の毛のドレスも、花がらのシルクのドレスもあります。ダークレッドのベルベットのドレスも、たくさんのスパンコールが光り、つぎつぎ色が変わる、きらきらのドレスもありました。