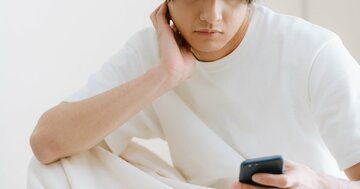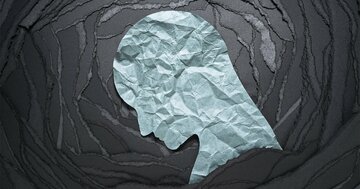ただこの五月病、毎年連休中からニュースになり社会問題化していますが、これまで大規模なデータに基づいて、正確にこの時期にメンタル不調のケースが増えるということを証明した研究は、わたしの知る限りではありませんでした。
しかし、2023年に名古屋市立大学精神医学教室の白石直講師が発表した論文で、その存在が明らかになりました。わたしも共著者です。研究の概要はこうです。
2019年から2021年の日本の大学生1626人のうつ症状の推移を調べました。新型コロナウイルスが蔓延した時期と重なるため、この研究の当初の目的は、緊急事態宣言が発令された時期に大学生のメンタルヘルスが悪化したかどうかを調べることでした。
結果的には、緊急事態宣言の影響は明らかではなく、それよりも新学年が始まった春先にうつ状態が強くなっていました。
このことから、たしかに「大学生にとって、5月を含む春先は要注意」といえることがわかりました。
ただし5月と言わずとも、年末年始や夏休み、秋の連休の後、毎週月曜日などに、学校に行くのが面倒になる、ああしんどい、もっと寝ていたいと思うことは誰にでもあることです。この研究では、そうした細部の解析はしていません。
そのメンタル不調の症状は
日常的な気分の変動の可能性も
ただ、誤解のないように伝えておきたいのは、こういった時期にメンタルヘルスがいつもより良くないとしても、その状態が必ずしもうつ病や適応障害などの「病気」を意味するものではないのです。
メンタルの状態が一時的に不調であっても、いつしか休み前の状態に気力が戻っている場合は、とくに心配する必要はありません。いわゆる「日常的な気分の変動」であり、誰もが経験する正常な反応です。
五月病に関してわたしがもっとも伝えたいのは次のことです。
春先は大学生にとって友人関係が変わったり、進路などの人生の決断を迫られたり、希望とともに失望も経験したりと、そもそもメンタルの不調をきたしやすい時期です。そのため、調子を崩す学生が増えます。
しかし裏を返せば、春先でなくてもそういった状況に追い込まれた場合は、どの時期であろうとも、メンタルに不調をきたす可能性はあるということです。
また、この研究はあくまで大学生だけを対象としており、この結果がほかの世代にも当てはまるかどうかはわかりません。社会人においても、春先は就職や転職、また人事異動などの変化が比較的多い時期なので、注意すべきだとは言えるでしょう。ただこの場合ももちろん、5月でなくてもいつの時期にも起こり得ることです。