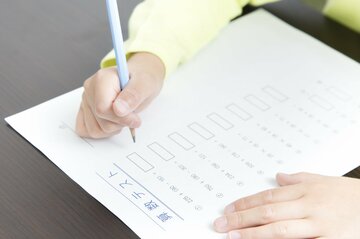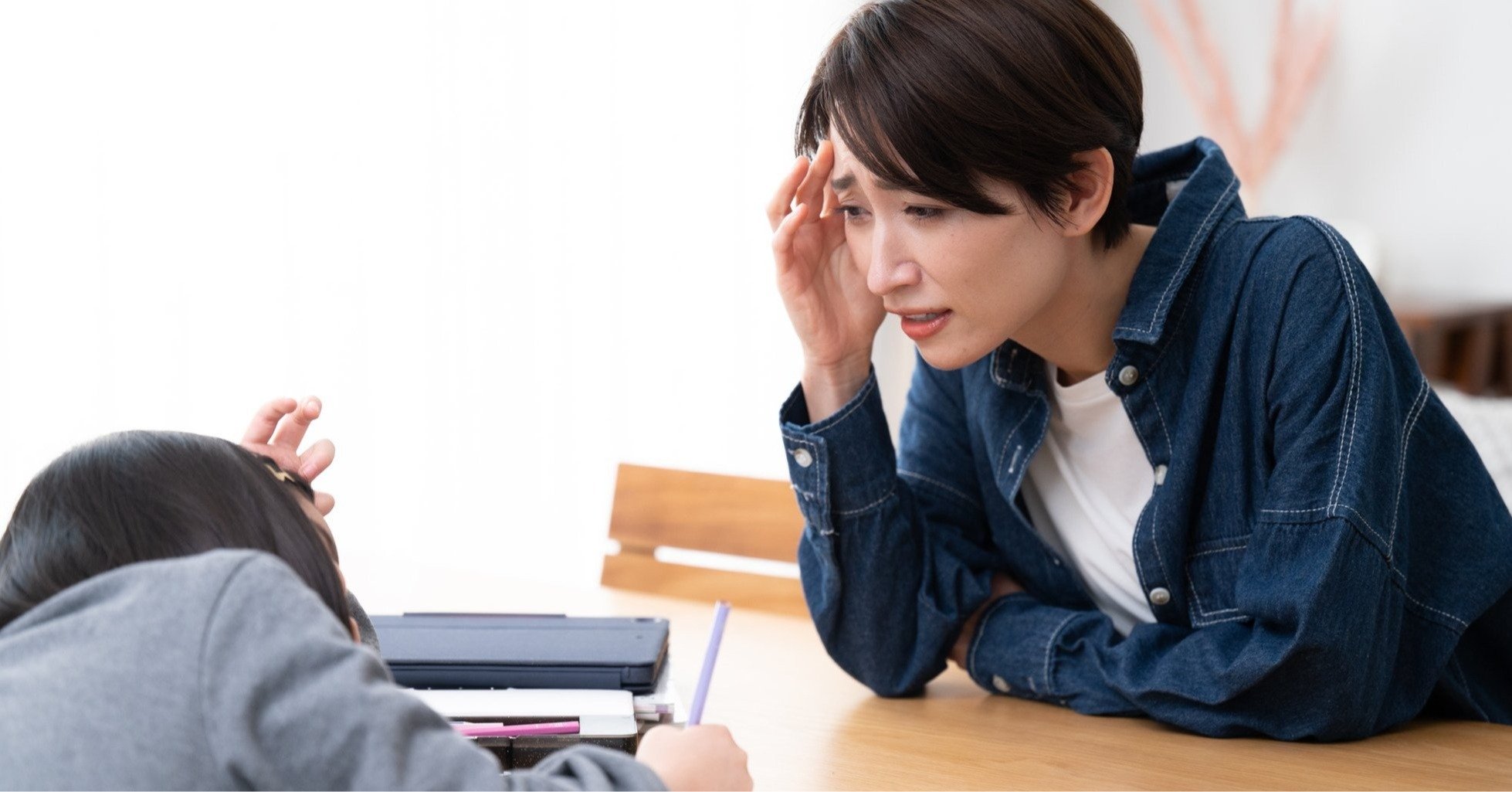 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
SAPIXの広野雅明先生に「中学受験の素朴な疑問」をぶつける連載。今回から全5回にわたって「第2志望の選び方」を取り上げます。憧れの第1志望校はすぐに決まっても、第2志望校で頭を抱える人は少なくありません。実際に行く可能性が高い学校だからこそ、第1志望校に比べると現実的にならざるを得ません。広野先生によると、以前と比べて併願校選びに苦戦する親子が増えたと言います。(聞き手・文/教育アドバイザー 鳥居りんこ)
「お試し受験」の消滅、
大学受験も中学校選びに影響
――中学受験において小学6年生の秋は併願校選びが本格化する時期ですが、ここ数年は「まだ併願校が決まらない」という保護者の悩みをよく耳にします。中学受験界では何が起こっているのでしょうか?
確かに以前と比べて併願校選びに苦慮しているご家庭が増えているのは確かです。その理由を挙げますと、次の6パターンが考えられるかと思います。
(1) 「定番パターン」がなくなってきている
(2) 「お試し受験」という概念が消えた
(3) 午後受験が増えた
(4) 学校の広報担当の先生方がプレゼン上手になった
(5) 「母と子の受験」から「家族の受験」になった
(6) SNSなどのネット情報が増えた
(1)の「定番パターン」の減少ですが、以前だと、地域ごとに(あるいはお子様の偏差値帯ごとに)ある程度、受験する学校が自動的に決まっていました。
例えば、神奈川県では2月1日サレジオ学院(または逗子開成など)、2日栄光学園(または聖光学院など)、3日浅野などといった具合です。
しかし、近年では「定番受験」は減少傾向です。例に挙げた3校はすべて男子校ですが「男子(女子)校でなければならない」とか、「キリスト教の学校だけを受験」というような“○○縛り”にこだわるご家庭が少なくなってきたのです。
――確かに、以前は2月1日にカトリックの雙葉を受けるのであれば、2月2日も同じカトリックである白百合がいいよねといったスクールカラー重視という定番パターンがありました。今は大学附属校に行きたいのかと思いきや、附属校ではない学校も併願校に入っているという具合にラインナップはご家庭ごとで異なり、バラエティーに富んでいる印象があります。
一昔前までは進学校であれば進学校だけで並べる、大学附属校ならば、附属校だけで統一したものでしたが、今はあまりこだわらないご家庭が多い。たとえ大学附属であっても、併設大学への内部進学率が必ずしも高くない高校も少なからずあり、大学によっては推薦権を保持したまま併設大学以外にも挑戦できます。
さらに附属校は6年間で英語学習と探究型の授業を重視している学校も多いので、大学の総合型選抜入試との相性も悪くない。大学附属に入ったとしても、併設大学以外にも進学しやすくなっています。それであれば別に附属校でもいいというご家庭の意識の変化があると思います。
――保護者のこだわりが薄くなって定番受験が激減しているということですね。どうしてでしょうか?