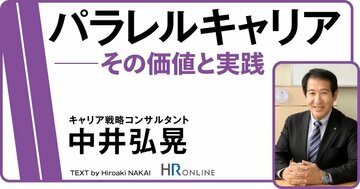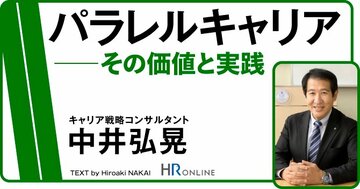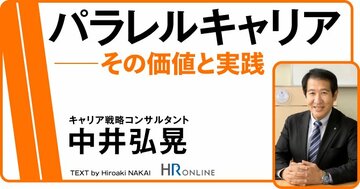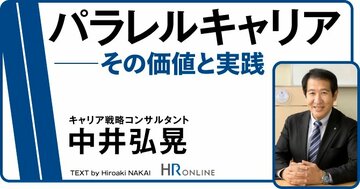そこに、“自発的な姿勢”と“学びの意識”があるか
ここまで、“付加価値のあるパラレルキャリア”のケースを見てきましたが、より理解を深める目的で、それ以外の2人のケースを見ていきましょう。
Fさん(20代後半 総務部女性)のケース:さまざまな雑務対応や人間関係にストレスを感じているFさん。月1回開催される趣味の俳句サークルに入会。
Fさんのケースは、自発的な社外活動であり、仕事のリフレッシュ効果はあるかもしれませんが、現在、あるいは将来のビジネスキャリアにつながる学びの活動ではなく、組織への貢献度期待も大きくないため、私が定義し、推奨する“付加価値のあるパラレルキャリア”でも“広義のパラレルキャリア”でもありません。リフレッシュして仕事に向かうことができる、というような副次効果はあるかもしれませんが、本業とのつながりは大きくはありません。趣味のサークル活動は、基本的に、プライベートの充実を目指した個人の社外活動なので、“付加価値のあるパラレルキャリア”とは言えず、個人が自身の意思で取り組めばいい話です。組織があえて推奨する必要もないでしょう。しかし、俳句を極めて、世の中で、俳人として認められ、俳句教室の講師や運営を担うようになった場合は、単なる趣味の域を超えて、仕事として成り立ちますので、タイプ(4)の「プライベート充実型パラレルキャリア」となり得ます。
Gさん(30代前半 営業部男性)のケース:給料の少なさを嘆くGさん。生活費を補うためにコンビニでのアルバイトを1年間実施。それでも十分ではないので、最近、データ入力のスキマバイトも開始。
Gさんのケースは、複数の収入源を確保し、働き方をポートフォリオ化しているように見えますが、私が推奨する“付加価値のあるパラレルキャリア”ではありません。自発的に始めたわけでもなく、学びの意識もないからです。スキマバイトであっても、専門性を要し、本業との相乗効果が期待できる場合は、タイプ(1)の「本業改善型パラレルキャリア」とみなす余地もありますが、本ケースは、自身の成長や将来のキャリアにつながらず、かつ、労働時間増による疲労の蓄積によって、本業への支障が出る可能性が高まるので、個人にも組織にも推奨できません。