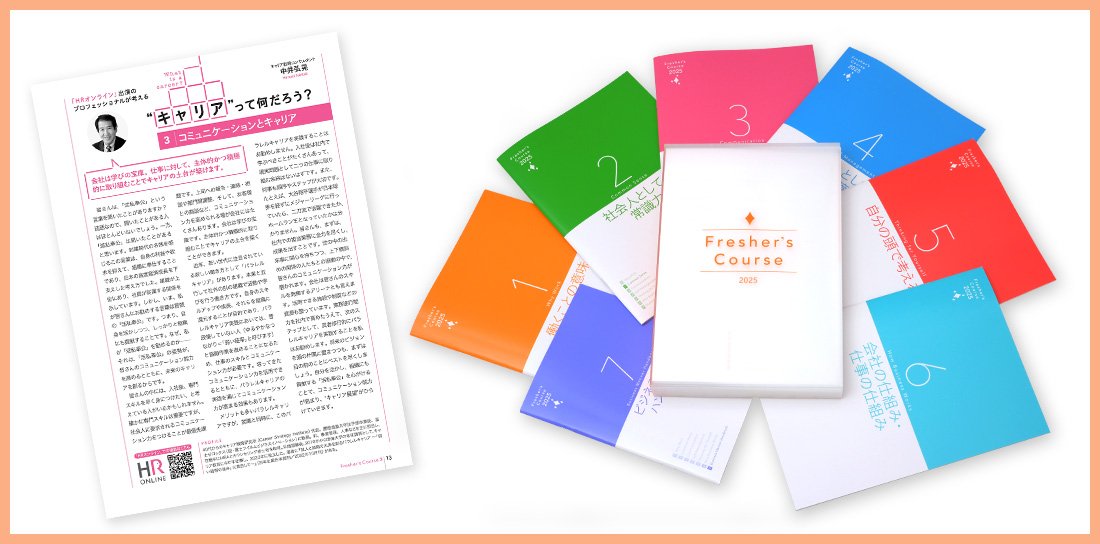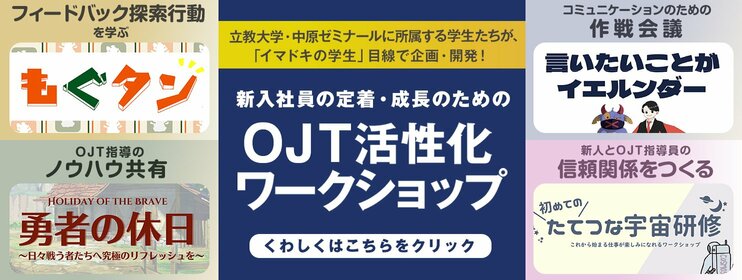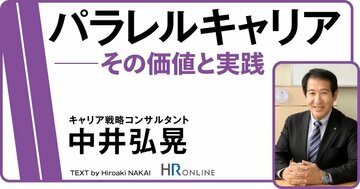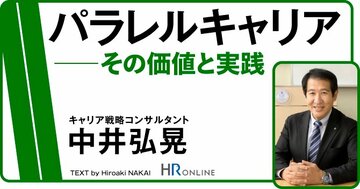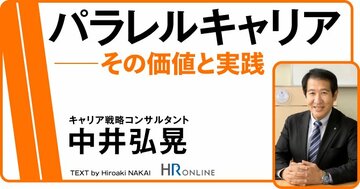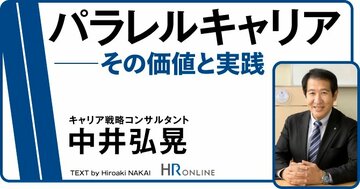“活私奉公型パラレルキャリア”が望まれる理由は…
私は、副業自体を否定しているわけではありません。個人の成長やキャリアにつながる副業も世の中に多く存在するからです。私がお勧めできない副業は、収入補填のために、やむを得ず受動的に取り組む副業です。
コンビニでのアルバイトのケースであっても、将来、フランチャイズオーナーとして経営に携わるキャリアプランがあって、そのために消費者行動などを学ぼうといった目的がある場合は、タイプ(2)の「将来布石型パラレルキャリア」となるとも考えられます。
前述のCさんのように、個人のスキルアップを本業の改善につなげようとする、目的や明確な意図のある副業は、個人にも組織にも推奨できる副業と言えると同時に“付加価値のあるパラレルキャリア”となると私は思います。
2018年に「モデル就業規則」が改定されたことに伴い、副業を解禁する企業も少しずつ増えてきているようです。こうした副業解禁の流れの中で、タイプ(5)の「収入補填型パラレルキャリア(副業)」に取り組む社員が増加することは、個人にとっても組織にとっても、決して望ましいものではないと思います。社外での活動は、個人の意思に委ねるのが原則であるにしても、社員には目先の収入に向かうのではなく、タイプ(1)(2)(3)の“付加価値のあるパラレルキャリア”に向かうように仕向ける工夫が組織には必要だと思います。この3つのタイプであれば、パラレルキャリアの実践効果が、個人と組織双方に生じることが期待できるからです。
先行き不透明の厳しいビジネス環境下、70歳まで働くことも現実味を帯びてきています。たとえ50代のシニア社員であっても、将来のキャリアを考えるべき時代に私たちは生きていると言えるでしょう。
将来の布石として中長期的視点で“付加価値のあるパラレルキャリア”を実践し、スキルのアップデートを行うことは、必要不可欠なキャリアサバイバル戦略とも言えます。短期的な目先の結果(収入等)を求めるのではなく、我慢して、中長期的に結果が出るよう、戦略的に考え、行動することが大切です。
一方で、古い考え方かもしれませんが、社外での活動を、決して、自分の将来のキャリア形成だけを目的とするのではなく、勤務している企業へ還元する姿勢を持つことも重要だと思います。
「24時間働けますか?」――これは、昭和から平成に変わった1989年の新語・流行語に選ばれた栄養ドリンクのCMのフレーズです。現在では完全にアウトですが、当時は、残業・徹夜・休日出勤がごく当たり前に行われ、個人に対しても「滅私奉公」が求められる時代でした。
時代や価値観が大きく変わった現在、私の提案する働き方は「滅私奉公」ではなく「活私奉公」です。自分を滅するのではなく、自分を活かしつつ、所属組織に貢献するという取り組み姿勢です。「奉公」という言葉も、古い言葉ではありますが、いつの時代であっても、「感謝の気持ちを持って所属組織に仕える、貢献する」という姿勢は大切だと私は考えます。
“付加価値のあるパラレルキャリア”を、総称して “活私奉公型パラレルキャリア”と言い換えることも可能ではないかと思っています。
私は、この“活私奉公型パラレルキャリア”こそが、「個人と組織の未来を創るパラレルキャリア」と言えると思っており、個人と組織双方に推奨するものです。
収入を伴わないケースが多く、短期的な成果も期待できないかもしれませんが、中長期的にリターンが期待できる必要な自己投資だと思います。
定時後や週末などの空き時間を活用して、“活私奉公型パラレルキャリア”に取り組んでみることをお勧めします。きっと、将来のキャリアを豊かにしてくれる、新たな「弱い紐帯」(緩やかなつながり)や「偶然の出会いや出来事」が待っているはずです。