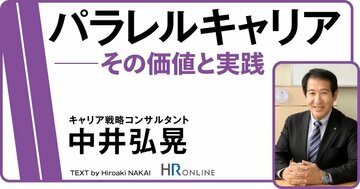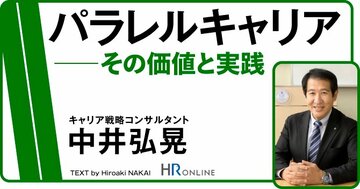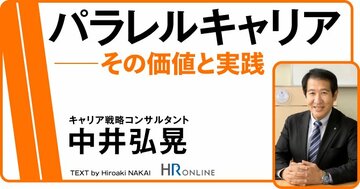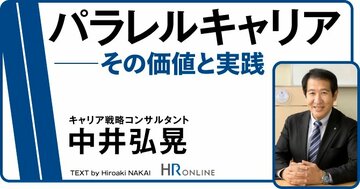“付加価値のあるパラレルキャリア”と言えるか否か
では、どのような活動が、個人と組織双方に推奨する“付加価値のあるパラレルキャリア”となるのかを、ケースごとに見ていきましょう。
Aさん(30代後半 財務部男性)のケース:資金管理担当のAさん。さらにファイナンスの専門性を高め、業務品質を向上させるために、定時外や週末を利用して社会人大学院のMBAコースで2年間勉強。
Aさんのケースは、自発的に社外の教育機関での学びに取り組んでおり、本業での担当業務の改善を意図しているので、タイプ(1)の「本業改善型パラレルキャリア」となります。
Bさん(50代後半 営業計画部男性)のケース:営業計画部のBさん。役職定年に伴い、権限もなくなり、疎外感や定年後への不安を感じるなか、新たな領域へのキャリアチェンジにトライしたいと一念発起し、社会人大学院に入学し、関心があるカウンセリングを勉強。
Bさんのケースは、Aさん同様、社会人大学院での学びに取り組むケースです。違いはAさんが現在の担当業務に関連した学びを対象としたことに対して、Bさんは、現在の担当業務と異なる領域を学びの対象とした点です。自身の将来のキャリアへの布石の意味合いが強いので、タイプ(2)の「将来布石型パラレルキャリア」となります。
Cさん(40代前半 販売推進部女性)のケース:販売推進部のCさん。お客様満足度でも高い評価を得ており、自身のホスピタリティに自信があるが、より高いレベルを目指して、週末を利用してホスピタリティで定評のあるテーマパークでのキャストのアルバイトをスタート。
Cさんのケースは、タイプ(5)の「収入補填型パラレルキャリア(副業)」に見えるかもしれません。しかし、取り組んだ狙いは、自身のホスピタリティスキルを伸ばすことなので、実際には、タイプ(1)の「本業改善型パラレルキャリア」であると私は解釈します。
何に取り組んだかといった、表面的なことで判断するのではなく、本人の目的や意図を考慮して、“付加価値のあるパラレルキャリア”と言えるか否かを判断します。
Dさん(40代前半 広報部女性)のケース:広報業務経験20年のベテランのDさん。ある日、後輩から、友人が勤務するNPOが広報人材を探していると相談を受け、自身のスキルが社会貢献活動につながればと思い、平日の定時後、週2回サポート。
Dさんのケースは、自身のスキルを社外でボランティア的に活かす、いわゆる「プロボノ」を自発的に始めたもので、タイプ(3)の「社会課題解決型パラレルキャリア」と言えます。異なる領域の広報を経験することによるスキルアップを通じて、本業への貢献度が高まる可能性もあるので、タイプ(1)の「本業改善型パラレルキャリア」にもなり得ます。
Eさん(40代後半 営業部男性)のケース:営業経験25年、営業一筋のEさん。実家が障がい者サポート関連の施設を経営している関係もあり、障がい者サポートに関心があり、関連するNPOで毎週末活動。
EさんのケースもDさん同様にタイプ(3)の「社会課題解決型パラレルキャリア」と言えます。こうした活動を通した本業組織への効果は、間接的なものであるケースが多いですが、直接的にプラス効果をもたらすこともあります。社会貢献活動を行っている点が、お客様から評価され、実際の商談成功につながった話を聞いたこともあります。
企業がSDGsに積極的に取り組むことは社会的評価を高めるだけでなく、採用活動や投資家へのアピールにもつながります。社員が社会貢献活動に取り組むことを推奨することは、組織にとってもメリットがあると言えるでしょう。