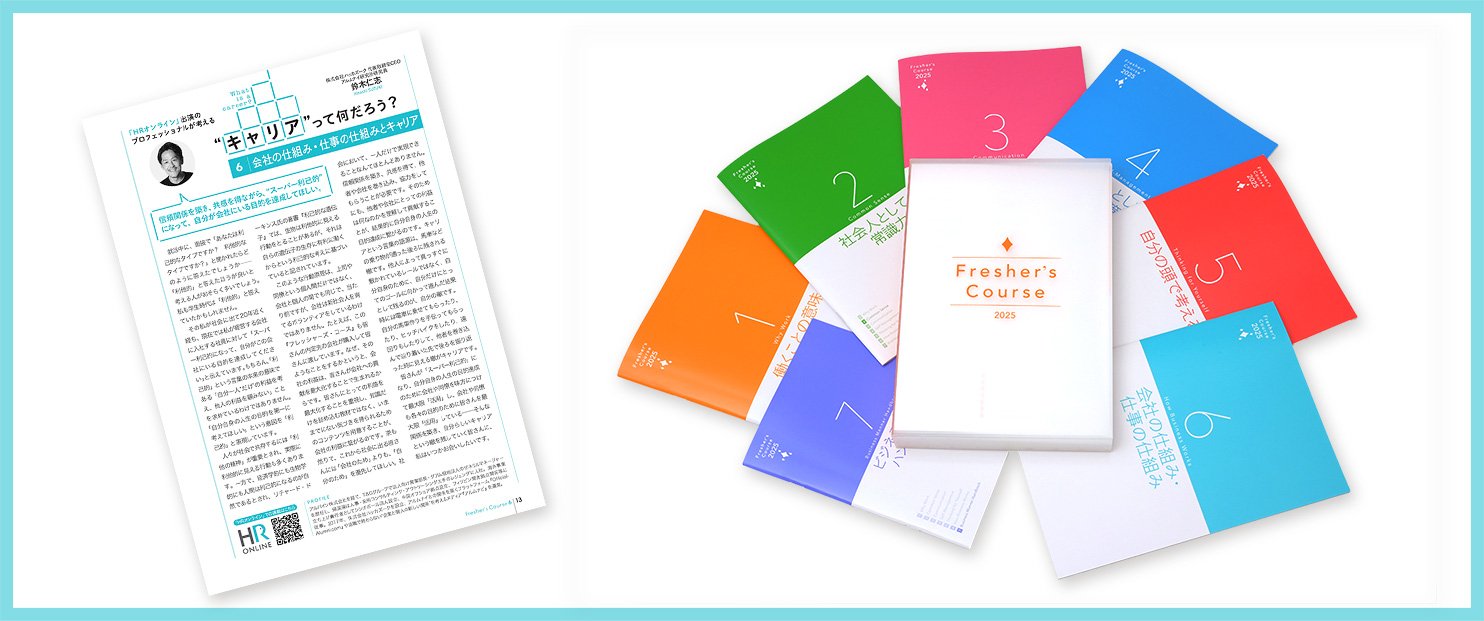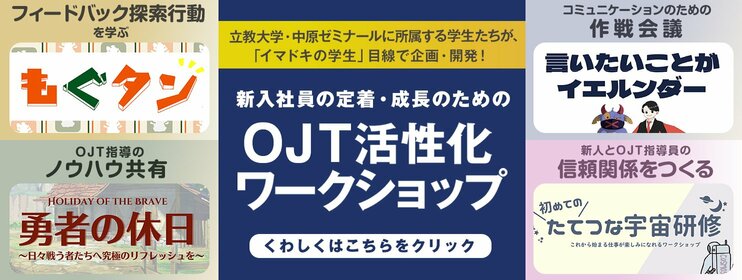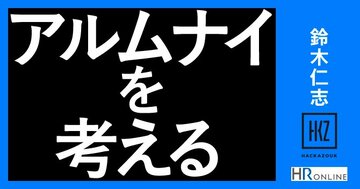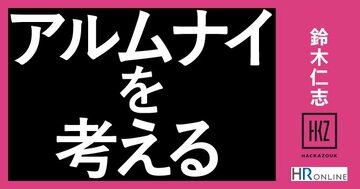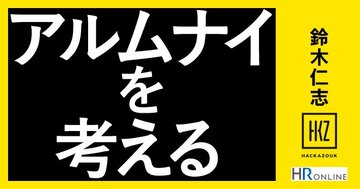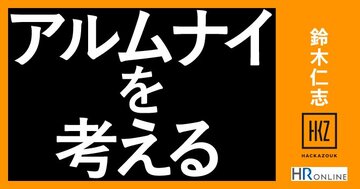長期雇用前提のメンバーシップ型雇用だからこそ
一方で、これまで、新卒採用中心だった日本の大企業でも、中途採用の比率が高まってくるにつれて、ジョブ型雇用まではいかなくても、採用時には「ジョブ型採用」となることが増えてきています。専門性を持った人材が外部から入ってきて、長期間にわたって同じ企業で一緒に仕事をする人たちが減少すると、その企業だけの特殊的ではない、より一般的な言葉やルールが使われるようになり、その企業内での企業特殊的能力の存在は少しずつ薄まることになります。それでも、同じ企業で働いたことがある人同士の「話が早い」「話が通じやすい」「一緒に仕事がしやすい」という感覚の希少性と重要性を実感したことがある人は少なくないでしょう。また、そのような共通言語がある関係だからこそ、社外に一度出た人材が価値の高いスキルや専門性を身に付け、その会社に戻ったり、その会社と協業したりした場合には、共通言語を持ち込んで発揮できるのです。
そして、だからこそ、同じ企業での企業特殊的能力を共有して活かせる人同士、もしくは双方がその企業を去って社外に出たとしても、アルムナイ・リレーションシップを構築してつながり続け、その企業特殊的能力を活かせる環境があることに大きな価値があるのです。個人が属人的に構築しているアルムナイ同士やアルムナイと社員のつながりだけでは広がりに限界があるため、企業特殊的能力を共有する人同士のつながりの価値を実感している企業が、公式にアルムナイ・リレーションシップを構築し始めています。
労働市場全体の大きな流れは変えることはできないものの、それによって生じる変化はコントロールすることができます。社員の退職を全て防ぐことはできなくても、退職によって変化してしまう企業と個人の関係を変えることは可能です。自社における企業特殊的能力を持った人が退職してしまっても、その人とアルムナイ・リレーションシップを構築することで、お互いにとっての共通資産である企業特殊的能力を発揮することができる関係を維持でき、メンバーシップ型の良いところを活かせるのです。
「終身雇用・長期雇用前提のメンバーシップ型雇用だから、退職したら裏切り者」ではなく、「終身雇用・長期雇用前提のメンバーシップ型雇用だからこそ、企業特殊的能力を退職後も活かせるように、アルムナイ・リレーションシップを構築すべき」と言われる日も、そう遠い未来ではないはずです。