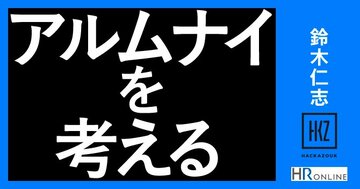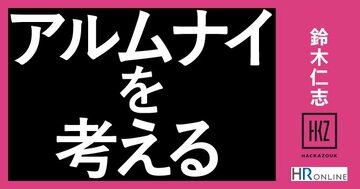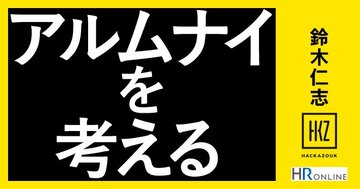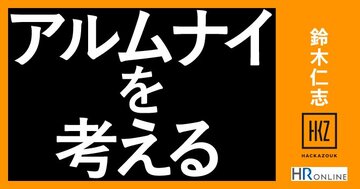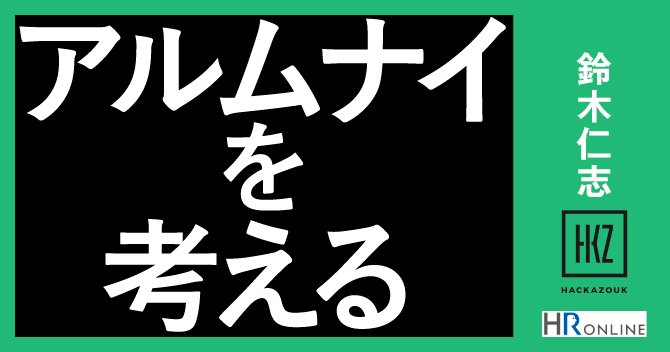
「人的資本経営」のキーワードとして「アルムナイ」が注目されている。企業が自社の退職者である「アルムナイ」とどのような関係(アルムナイ・リレーションシップ)を築いていくかは、人材の流動性が高まっている時代でことさら重要だ。さまざまなメディアからの出演依頼が続き、昨年(2024年)には著書も発表した、「アルムナイ」知見についての第一人者・鈴木仁志さん(株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員)による、「HRオンライン」連載=「アルムナイを考える」の第9回をお届けする。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)
>>連載第1回 「退職したら関係ない!」はあり得ない――適切な「辞められ方」「辞め方」を考える
>>連載第2回 誰もが明日から実践できる「辞め方改革」が、あなたと企業を幸せにする理由
>>連載第3回 「辞め方」と「辞められ方」――プロサッカークラブに見る“アルムナイ”の大切さ
>>連載第4回 “出戻り社員”が、会社と本人を幸せにする理由と、お互いが成功する方法
>>連載第5回 内定辞退者や早期退職者に対する“負の感情”が減る「辞め方改革」とは?
>>連載第6回 「急がば回れ」の姿勢が、“アルムナイ採用”をしっかり成功させていく
>>連載第7回 「アルムナイ」の広がりに伴う“さまざまな声”について、私がいま思うこと
>>連載第8回 いま、このタイミングで、“アルムナイ”の書籍を執筆して気づいたこと
メンバーシップ型雇用とアルムナイ・リレーションシップ
「ジョブ型雇用が一般的な欧米企業では合うかもしれないけど、メンバーシップ型雇用が主流の日本企業とアルムナイは相性が悪い」――これは、筆者がハッカズークを設立してアルムナイに関する事業を始めた2017年、多くの方に言われた言葉です。その理由として、大きく分けると以下の二つが挙げられました。
・メンバーシップ型雇用の組織は、社外に一度出て、価値の高いスキルや専門性を身に付けた人材が、前の会社に戻ったり、前の会社と協業したりしようとしても、それを持ち込んで発揮しづらい環境だから。
・メンバーシップ型雇用では終身雇用や長期雇用が前提となっているため、「退職者=裏切り者」となりやすいため。
2点目は事実ではあるものの、ここ数年での日本企業の変化を本連載で何度か書いてきたため、本稿では割愛し、1点目について、私の意見をお伝えしようと思います
拙著「アルムナイ 雇用を超えたつながりが生み出す新たな価値」の中でも書きましたが、私は2017年当時から上記のような反対意見に対しては懐疑的で、真逆の仮説を持っていました。それは、「メンバーシップ型雇用の日本企業でこそ、アルムナイは唯一無二の貴重な存在であるため、アルムナイ・リレーションシップから受けられる恩恵がとても多い」というもので、8年ほど経った現在(いま)では、自信を持って「メンバーシップ型の日本企業こそ、アルムナイ・リレーションシップの構築に取り組むべき」と言うことができます。
「日本人はメンバーシップ型(雇用)に向いている」と言う方がいますが、日本は過去にジョブ型と呼ばれる就職型と、メンバーシップ型と呼ばれる就社型の両方を経て、現在に至っています。1970年〜1980年頃までは、労働者が特定の仕事(ジョブ)を遂行すると対価が支払われる、いわゆるジョブ型が一般的でした。その後、高度成長期に入る中で、新卒の一括採用などに代表される未経験者の大量採用と職業訓練を行い、その都度、会社側の裁量で異動や配置転換を命ずることができる、メンバーシップ型雇用が始まりました。その後は皆さんもご存じのとおり、メンバーシップ型雇用は日本的経営の象徴と言われるまでに普及し、日本経済が停滞を始める2000年頃からは、再度、ジョブ型雇用への移行を訴える声が多くなりました。