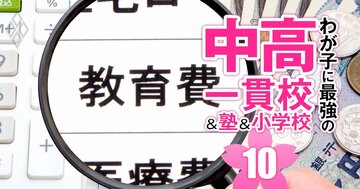「何も難関大学の合格がすべてではない。もともと教員が何も言わなくても一定数が東大に合格している。私立と同じことをするのが公立の役割ではない。公教育なのだから、地域に残り、地域に貢献する人材を育てるべきだ。
偏差値の高い大学に進学することを目的とすれば、都市部に出た子どもたちが戻ってくるとは限らない。公教育とは、東京に出ていく若者を育てることではないはず。教育現場が中高生のうちから地元企業を知る機会を作ることが必要だ。地元で活躍している大人を知ってもらうことこそ、公教育がすべきだ」
そもそも中高一貫校は、少子化のなかで私立の学校が生徒を囲い込むために始められた側面がある。
私立の中高一貫校のなかには予備校と提携するなど大学受験対策に手厚く、授業を先取りして高校2年生のうちに終わらせ、3年生をまるまる受験対策の時間に当てることをウリにしている学校も少なくない。
すると、ただでさえ少子化で子どもの奪い合いとなるのに、大学合格の実績を掲げる私立に人気が流れ、県立高校に欠員が出てしまう事態に陥る地域もある。公立も私立の動向を無視できず、「高校受験のない中高一貫の6年間で特色ある教育を行う」などをうたい文句に、中高一貫化が進んでいる。
公立の場合、学校教育法の改正によって1999年度から中高一貫教育を行えるようになった。中高一貫校には、中学校と高校が併設されて高校に無選抜で入学できる「併設型」と調査書やテストの成績以外の資料で入学者を選抜できる「連携型」、高校からの募集は行わないで6年間を通した教育を行う「中等教育学校」がある。
文部科学省の「学校基本調査」によれば、中等教育学校は2024年度で59校あり、設置者別では、国立が4校、公立が35校、私立が20校となっている。在学者は過去最高の合計3万4514人となった。
そうしたなか、前述の中高一貫校化を推し進めた知事は「地域の中の学校として、地域の人材を地域で育成」「トップレベル人財の育成」などを掲げてエリートの輩出を目指すというが、逆の現象が起こりつつある。