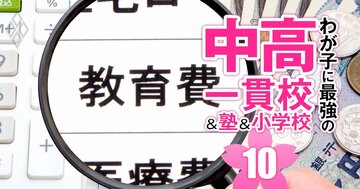“真のエリート育成”から
かけ離れている教育改革
地元の教育関係者は「中学受験をするなかでもトップの層は、地元からでも電車で通学可能な東京の御三家に入学してしまいます。中学から東京に出てしまえば、地元に愛着が生まれるはずがない」と人材流出を懸念している。
知事がいうエリートとは「東大、京大、医学部」に合格する子どもたちで、椅子取りゲームができる富裕層という狭いなかから選抜される人材でしかない。政治家が“教育改革”を行ったというための実績作りとしかなりかねず、「ノブレス・オブリージュ」とかけ離れていく。
ノブレス・オブリージュとは19世紀にフランスで生まれた言葉で、当時の階級社会のなかで貴族を指して「身分の高い者には、それに応じて果たす社会的責任と義務がある」という意味がある。自己の持つ力を磨き、その能力を社会に還元する。それが真のエリートであるはずだが、県立高校の中高一貫校化には、そうした行く先への意識があるのだろうか。
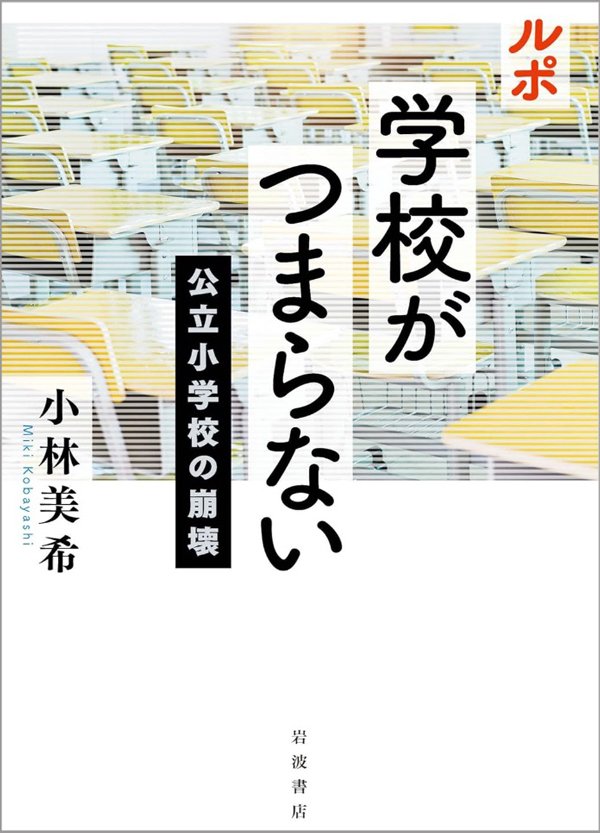 『ルポ 学校がつまらない――公立小学校の崩壊』(小林美希 岩波書店)
『ルポ 学校がつまらない――公立小学校の崩壊』(小林美希 岩波書店)
一方、その地方の私立学校も生徒の獲得に必死だ。県立に負けまいとユニークな教育を目指して入試は柔軟な発想を問うような設問に変わりつつあるとされる。“集客”を睨んだ立地戦略で、交通の便の良いところに学校を移転するなどして人気を集め、地方でも受験熱が高まりそうだ。
東海地方のある県でも2025年に県立の名門高校が中高一貫化するに当たり、大手予備校はうごめいている。附属中学の受験に向け2023年4月に小学4~5年生になる児童を対象にした「中学受験クラス」を開講。最難関の名門校の中学受験では入試倍率が10倍になると予想し、不合格だった場合に高校受験で他の名門校に再チャレンジできるよう特別な受験クラスまで設置する計画だ。