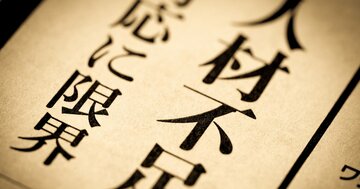これからの人口減少経済においては、コストプッシュによる価格上昇圧力は高まるはずだ。生産性の低い事業者が撤退することで市場の競争環境が緩めば、生き残った企業は財やサービスの価格をより積極的に引き上げることができるようになる。
今後の日本経済においては、こうした構造変化に伴って、緩やかなインフレーションが定着していくとみられる。
なお、物価が継続的に上昇していけば、為替を取り巻く環境も変わってくる可能性がある。現在の日本円は、実質実効為替レートでみれば歴史的な円安水準にある。この点、現下の日本円の過小評価を調整する経路は主に2つの方向性がある。
つまり為替が円高方向に修正されるか、物価上昇が進むことで円の価値が切り下がり、結果的に現在の為替水準に調整されるかというシナリオである。
どちらが実現するかはわからないが、長期的にみればいずれかもしくは両方の作用が働く形で現在の円安は調整されることになるだろう。
懇切丁寧な無料サービスは消失し
セルフサービスが標準に
将来の日本経済において、物価は持続的に上昇していくことになると予想することができる。しかし、物価が上昇するということは、消費者にとって決して好ましいことではない。
物価上昇とはすなわち同じ商品やサービスであっても、これまでよりも高い値段で消費者は商品を購入せざるを得なくなるということであるからだ。
これまで多くの日本企業では労働力を大量に利用して人海戦術で懇切丁寧なサービスを提供してきた。
そして、消費者はその恩恵に存分に浴してきた。しかし、今後、人手不足が深刻化していけば、これまでのようなサービス提供の仕方は難しくなっていくだろう。
これからの経済においては、現在提供されているサービスに優先順位をつけたうえで、優先順位が低いものについては消費者があきらめざるを得なくなるというプロセスをたどることになるのである。
たとえば、運輸業に焦点を当てれば、現代日本においては、消費者の住居1戸1戸に最短日程で荷物が届く高水準のサービスが行き届いている。それだけではなく、利用者の都合によって不在であったとしても、無料で何回も再配達を行ってくれる。
諸外国で行われているサービスと比較したとき、日本社会がここまでに質の高いサービスを安価に提供できる体制を整えているということは驚くべきことだ。そして、その陰には絶え間ない企業努力と多数の労働者の献身がある。
しかし、こうした多数の労働者によって提供されているきめ細やかなサービスについては、これからの時代においては、人件費コストの上昇に見合わなくなっていくだろう。