中国の2024年小売売上高
前年比伸び率
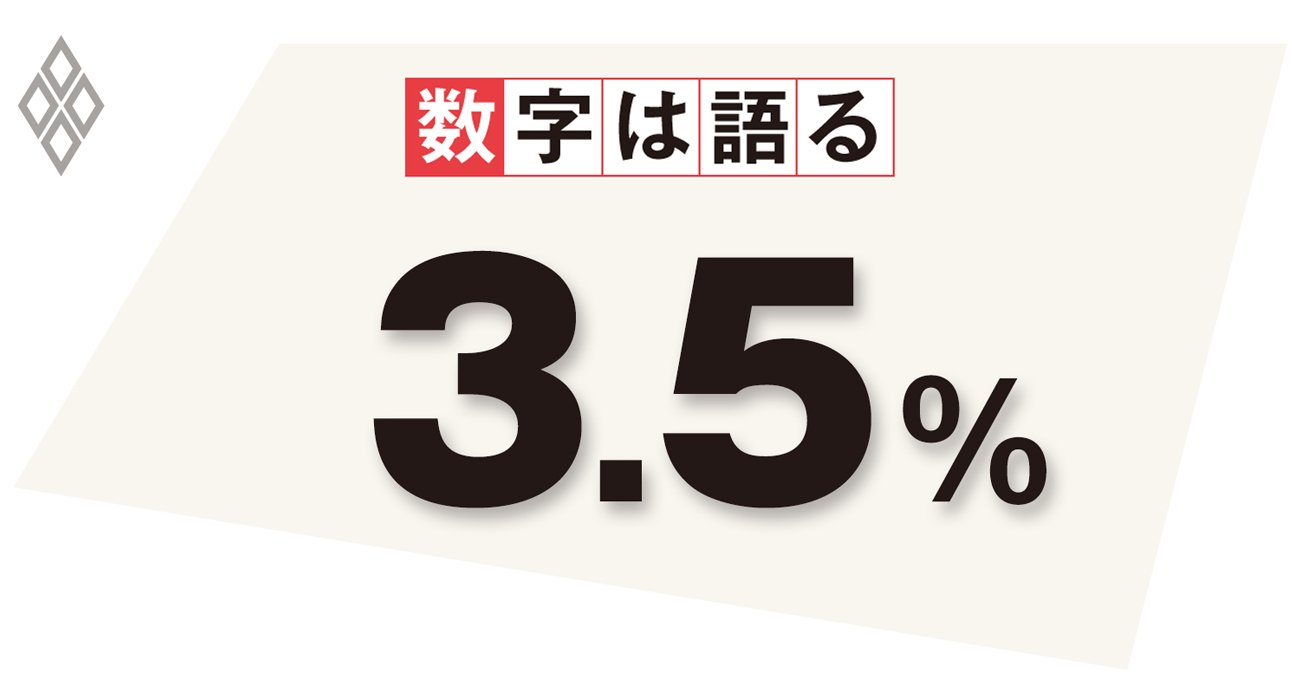 中国の2024年小売売上高前年比伸び率 出所:中国国家統計局
中国の2024年小売売上高前年比伸び率 出所:中国国家統計局
中国の国債金利が日本の金利を下回るなど、日本が経験したような長期停滞とディスインフレ基調に中国経済が陥るリスクは高まっている。消費者物価指数は前年比0%近傍を推移し、卸売物価指数は2年以上もマイナスが続く。
成長目標の達成が危ぶまれ始めた中で、当局も財政金融政策による景気刺激策を矢継ぎ早に打ち出してきた。しかしながら、個人消費の活性化には苦戦を続けている。
中国の小売売上高はコロナ前には前年比10%程度で推移していたが、昨年半ばには3%を切るまで減速した。危機感を覚えた政府は車や家電の下取り・買い替え補助、EV補助金などの消費てこ入れ策を拡大し、小売売上高は徐々に伸び率が回復している。
年初に買い替え対象品目がスマホやスマートウオッチなどに拡大されたこともあり、昨年に3.5%の伸びに終わった小売売上高は今年に4%台前半をどうにか確保すると現時点では見込んでいる。
しかしながら、こうした回復の動きは支援対象となる商品に限られるだけでなく、年央以降は政策効果の減衰に伴って個人消費全体は再び失速する可能性が高い。
買い替え支援措置は将来の需要の先食いにすぎない。中国で金融危機後の2年間続いた類似の支援策の効果を見ると、危機前に平均して22%で伸びていた家電売り上げは30%に加速したが、施策終了後は反動で12%に減速した。乗用車売り上げもそれぞれ35%、44%、17%と同じように増減した。
重要なのは家計所得の伸び悩みや雇用不安などを背景に、家計のコンフィデンス(経済の先行きに対する信頼感)は22年に急落した後も底這いを続けていることだ。賃金の伸びは6%と2010年代の平均12%と比べ半減している。家計貯蓄率はコロナ禍以降歴史的水準で高止まり、今後に備えた定期預金の積み上がりが続く。
当局の目指す消費主導の持続的な成長モデルを確立するには、家計マインドの回復が鍵を握る。そのためには不動産問題の抜本的な解決や財政、社会保障など多岐にわたる領域での構造改革への断固たる取り組みが欠かせない。
(オックスフォード・エコノミクス 在日代表 長井滋人)







