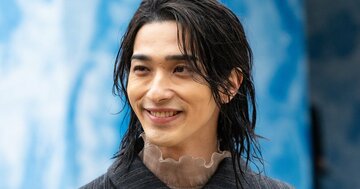しかし、これまでも同様の洒落本が多数出版されていて、版元蔦重にしても、改めの上許可を出した月行事にしても、この小冊3作が特段の問題をはらんでいるという認識は無かったはずである。「教訓読本」をうたったのも、教訓流行りの時世を踏まえた他愛ないシャレであろう。
蔦屋重三郎が処罰されたのは
町触の実効性を示すためだった
内容に関する「不埒」の理由などいかようにも言い立てられるもので、この一件の本質的なところではない。吟味の対象になった者たちの調書に必ず長々と引用されているのが、前年11月に出された町触の文言である。端的に言えば、この一件は、町触の実効性を確かなものにするために仕組まれたものである。
『近世物之本江戸作者部類』は、この時処罰された行事2名は、裏屋住まいの者で、本の仕立てで生計を立てている弱い立場の者であり、蔦重の意向に逆らえなかったとする。『伊波伝毛乃記』は、行事2人にひそかに蔦重が合力金を渡したとしており、ありうる話かと思われる。とすれば、仲間内の改めは、その発足当初から実際緩く流れたものなのであろう。行事2名に厳しい処罰を科したのも、行事の責任、行事による改めの重さを周知するためであろうし、京伝と蔦重を対象としたのも、当時一番目立つ存在で、見せしめとしての効果が絶大であると踏んだからであろう。
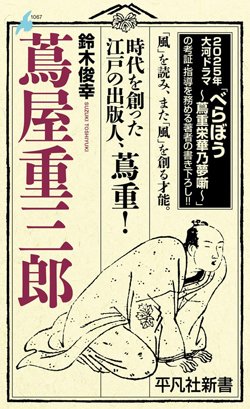 『蔦屋重三郎』(平凡社新書)
『蔦屋重三郎』(平凡社新書)鈴木俊幸 著
もちろん、老中定信がこの一件についての指示を具体的に出したということは考えにくく、町年寄を筆頭にした町役人が、町の風俗引き締めの風に乗じて町奉行に働きかけたものと考えるのが自然であろう。その効果はそれなりにあったようで、翌寛政4年(1792)に洒落本の出版は確認できない。
蔦重店の資本力は半減した。吉原の出店も手放すことになる。順風満帆とはいかない経営を迫られることになる。
蔦重は「大腹中の男子なれば」咎めもさほどのことと思わない様子であったが、京伝は謹慎第一の人となったと『山東京伝一代記』は記している。また皮肉なことにこの一件の風聞が世上に広まり、京伝の名はいよいよ高くなり、田舎でも知らない者はいなくなったとも伝えている。「京伝の名」は、蔦重店の経営にとっていよいよ重みを増していくことになるのである。