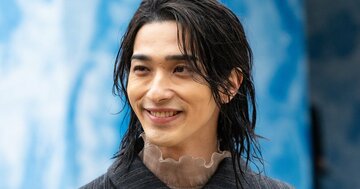写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』で話題の蔦屋重三郎。出版業を中心に江戸のメディア王として躍進していた彼に大きな危機が訪れる。天明の大飢饉により、商業発展の時代から打って変わって、質素倹約の時代が到来したのだ。規制が厳しさを増すなか、蔦重の店があった吉原では三味線の音が消えたという。吉原冬の時代について、近代文学の専門家・鈴木俊幸氏が解説する。※本稿は、鈴木俊幸氏『蔦屋重三郎』(平凡社新書)の一部を抜粋・編集したものです。
幕府が「倹約」を押し進め
大きな痛手を被った遊廓
18世紀末の寛政という時代は世の中が大きく変わる歴史の転換点であった。それは、武家社会の変化をきっかけにして、民間の知のあり方がめざましく変容していったことが大きい。民間に学問志向の風が流れ、書籍の市場は新たに浮上した読者を含み込んで大きく広がっていく。読者層の多くを占めるようになった彼らの存在は文芸の傾向を大きく変化させていく。蔦重(蔦屋重三郎)の商売も、その変化に対応していくことになる。
幕臣に向けられた倹約のかけ声は、幕臣のみならず江戸の武家社会全体を侵食し始めて、贅沢自粛の空気に包まれる。それは「不要不急」の行楽や遊びが憚られる空気でもある。江戸の人口の大きな割合を占める非生産者である武士たちの消費の落ち込みは、この都市の経済に大きな影を落とすことになる。田沼意次の時代のようには、お金が町に回らなくなるのである。
奢侈が売り物の場所や施設が真っ先に痛手を蒙る。芝居町と遊廓である。『よしの冊子』にもそのあたりの噂は多く記されている。天明7年(1787)6月から10月ころの記事に、諸組与力やお旗本へも頭から武芸出精専務のことなので遊所等へ行くことを固く禁止する旨、また家に芸者を呼ぶことも無用という通達が発せられ、吉原・品川・新宿などもいたって寂しく、芝居見物も少なくなったという話が載る。
留守居役などの会合を吉原で行うことも憚られるようになった。また、吉原にはそれなりに人は来るけれども八朔や月見の趣向も例年のようではなく、芸者もこっそり呼ぶようになったこと、芝居の上演はあるものの続き桟敷を買って贅沢に見物する客はいなくなり、金銀の落ち方も少なく、吉原も芝居町も困っているという噂も載る。