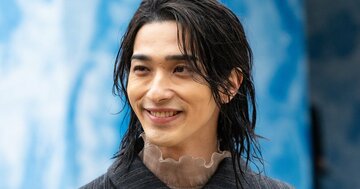三味線の音さえ聞こえない
町を覆った景気の冷え込み
寛政元年(1789)9月、棄捐令(きえんれい)が発せられる。幕臣が扶持米を担保に札差(蔵宿)から借金を重ねていて、倹約のみでは打開できないほど彼らの経済状況が悪化していた。その状況を打開すべく案じられたもので、天明4年(1784)以前の借金は棒引き、それ以後のものについても金利を引き下げるというものであった。
この法令によって札差が蒙った損失は莫大なものであった。吉原の経済は、札差や魚河岸連のような、突出した金持ちに支えられている部分が大きかった。札差の手許不如意は、吉原の不景気をさらに推し進めたものと思われる。『よしの冊子』寛政元年9月よりの記事には、蔵宿一件後は吉原がいたって寂しくなり、3日ほど一向客が無い日が続いたという風聞も載る。また、花扇などの名妓を抱える大店扇屋(編集部注/著名な遊女屋の名前)が株を売ったというデマも流れている。
扇屋墨河などの知友や血のつながった縁者が吉原に多数いるばかりではなく、吉原を本屋稼業の大きな支柱としていた蔦重にとっては頭の痛い状況であったと思われる。また、芝居町の不振も、富本節という劇場音楽の出版を手掛け、町芸者や素人の需要も高い稽古本を制作している身としては、成り行きに大きな不安を覚えたことであろう。『よしの冊子』は町方でも三味線まで弾かないようになったという噂を伝えているのである。
景気の冷え込みは遊廓や芝居町だけではなかった。世間一統銭回りが悪くなったと『よしの冊子』の寛政2年(1790)11月よりの記事は伝える。草紙類は「不要不急」の品の最たるものであろう。
書物類にとどまらず
“風俗”にまで規制が及ぶ
寛政2年11月19日に発せられた町触(編集部注/町内に伝達された法令)がある。それは次のような内容のものであった。
書物については以前より厳しく仲間内にての改めを行うように申し渡してきたが、いつのまにかそれが乱れてきているので、今回、書物屋どもと一枚絵草双紙問屋(地本問屋)どもに改めをしっかりするように申し渡すこと。
また、これまで行事を立てずにきた地本問屋については、今後2名ずつ行事を定めること。そして、貸本屋・世利本屋など類似の商売を行う者もいるので、書物屋どもと地本問屋(編集部注/江戸で出版された絵入りの本を出版する本屋)どもは、触書の趣を心得、新版に際しては行事による改めを受けた上で売買すること、というものであった。