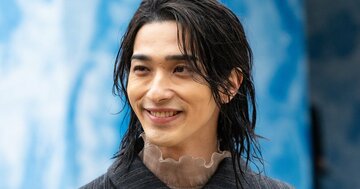これが松平定信による思想・言論統制の一環で、それが書物類だけではなく、地本類にまで及んだことを示す事例とする見解があるが、そもそも「言論」概念は近代のものであり、この時代の受け止め方とは大きな隔たりがあると思われる。書物についての文言は、享保以来行われてきたことの踏襲にすぎない。この町触の主眼は、明らかに地本問屋仲間を機能させて地本出版における責任体制の徹底を図ることにあった。
この町触に先立ち、10月27日、地本問屋に対しての仲間触が出されたようで、『類集撰要』巻四十六にその内容が載っている。翌月の町触とほぼ同様なのであるが、異なるところは、風俗のためにならない猥りがわしき出版物が出ることを未然に防ぐという意義をうたっているところである。つまり、書物に関する内容といっしょになっているので混乱してしまうが、地本類については言論レベルではなく風俗レベルの規制なのである。
「遊廓」を書いただけで
不埒とされ京伝は手鎖に
寛政3年(1791)3月、山東京伝と蔦重、そして前年12月の地本問屋月行事2名が町奉行は初鹿野河内守に召し出される。この年正月蔦重が出版した京伝作洒落本『大磯風俗 仕懸文庫(しかけぶんこ)』『青楼昼の世界 錦之裏』『手管詰物 しょうぎきぬぶるい』の3作についての吟味である。その結果、京伝は手鎖50日、蔦重は身上半減の重過料、行事2人は商売取り上げの上、所払いを申しつけられる。
定信の改革政治の典型的事例として高校の日本史教科書にも取り上げられる有名な一件である。民間にも及ぶ厳しい思想統制・言論統制の一例という格である。しかし、表現は統制されるべきではなく自由であるべきだという感覚は現代のもので、この現代的通念から事態を評価してしまってはいないだろうか。定信の厳しい政治姿勢をことさら演出するために持ち出されてはいないだろうか。
京伝・蔦重・京伝父・仲間行事それぞれについて町奉行所が作成した調書の内容が『山東京伝一代記』に収められている。それによる限り、関係者の咎めは、制禁を侵して風俗のためによろしくないものを執筆、出版したこと、また改めが甘かったということである。
調書は、『大磯風俗 仕懸文庫』は鎌倉時代になぞらえて深川遊廓での遊興の様子を描いたもの、『青楼昼の世界 錦之裏』『手管詰物 しょうぎきぬぶるい』は、浄瑠璃の筋立てと登場人物によそえて吉原遊廓の様子を描いたものとして、この3作が「不埒の読本」であるとする。『山東京伝一代記』は、「教訓読本」と唱えて、昔の人名を借りて今の風俗を書きあらわした洒落本を、制禁を侵して出版したことが不埒であったとする。