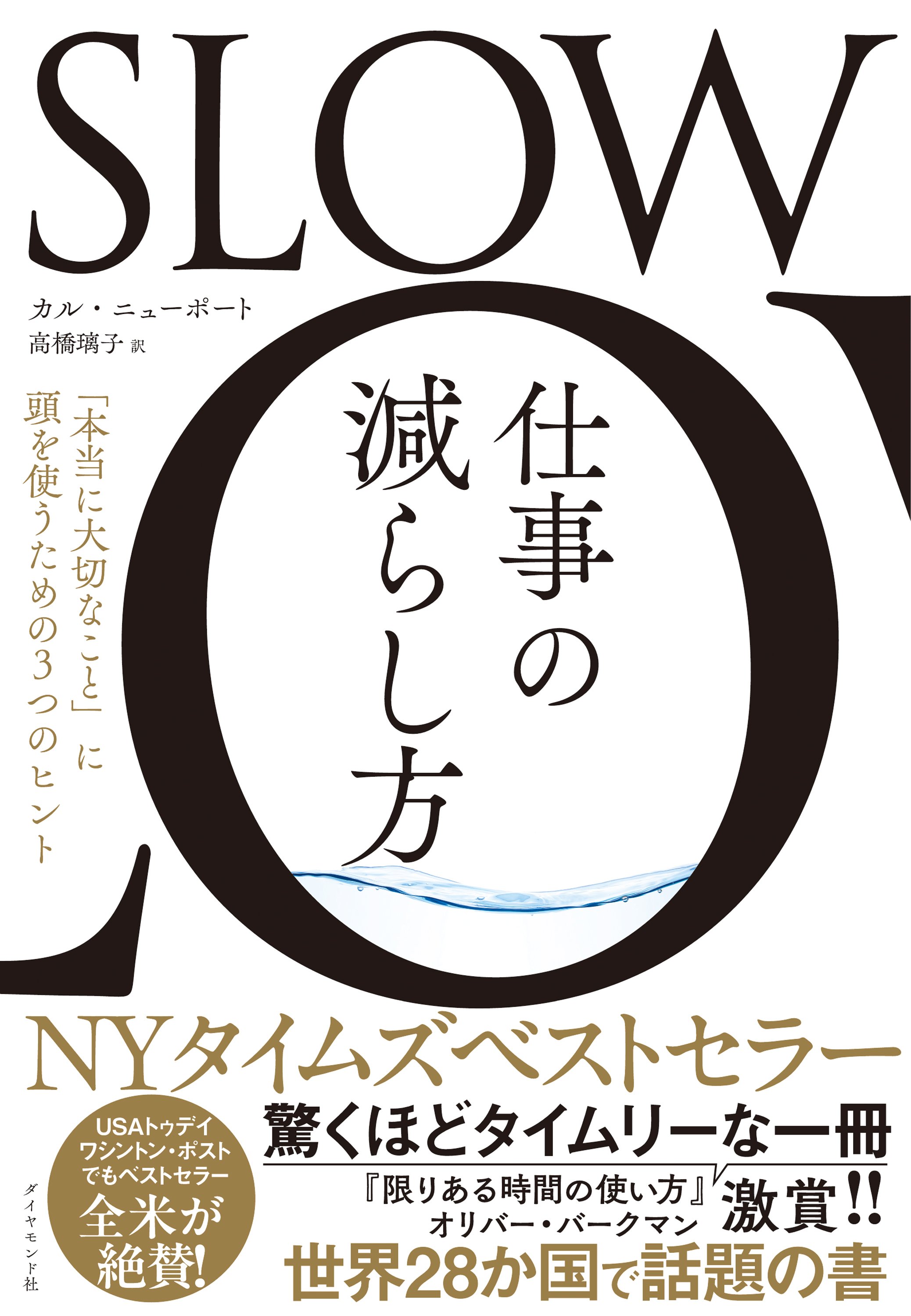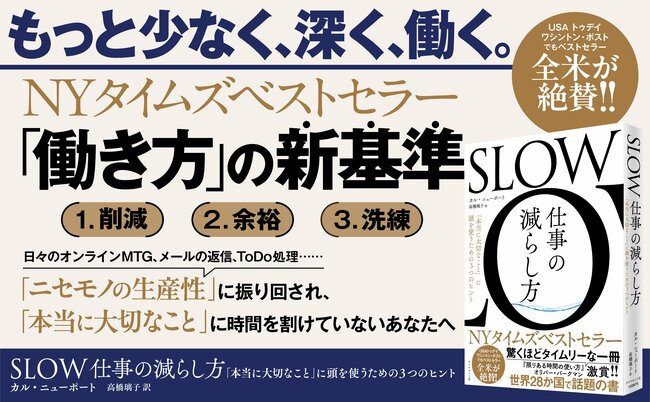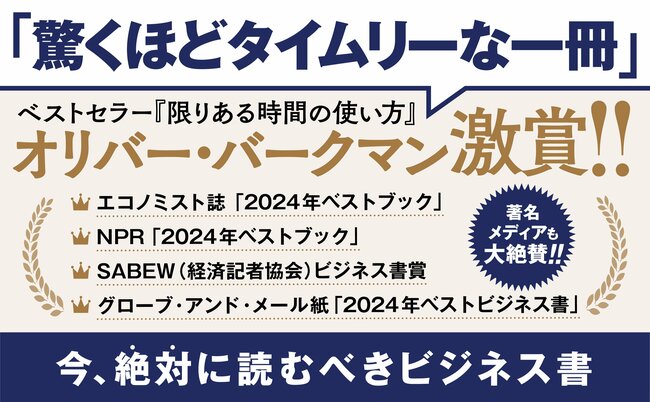やってもやっても仕事が終わらない、前に進まない――。そんな状況に共感するビジネスパーソンは多いはずだ。事実、コロナ禍以降、私たちは一層仕事に圧迫されている。次々に押し寄せるオンライン会議やメール・チャットの返信、その隙間時間に日々のToDo処理をするのが精いっぱいで、「本当に大切なこと」に時間を割けない。そんな状況を変える一冊として全米で話題を呼び、多くの著名メディアでベストセラー、2024年年間ベストを受賞したのが『SLOW 仕事の減らし方』だ。これからの時代に求められる「知的労働者の働き方」の新基準とは? 今回は、本書の邦訳版の刊行を記念して、その一部を抜粋して紹介する。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
2週間、裏庭で寝転んでいたジョン・マクフィーの話
裏庭で葉っぱを見上げて過ごすジョン・マクフィーの話を初めて知ったとき、僕はそれを一種の郷愁として受けとった。なにか遠い昔の、まだゆっくりと自分のペースで考える余裕があった時代のお話だろうと。「生産性を気にせずに好きなだけ時間をかけられる仕事があったら素敵なんだけどな」と僕は思った。
しかし、やがて無視できない事実に気がついた。ジョン・マクフィーは、実際すごく生産的だったじゃないか?
あの裏庭のピクニックテーブルから視点をぐっと引いて、マクフィーのキャリア全体を見渡してみると、その生産性は圧倒的だ。現時点で29冊の本を出版し、そのうちの1冊はピューリッツァー賞を受賞、2冊は全米図書賞にノミネートされている。
ニューヨーカー誌で50年以上にわたってすぐれた記事を書いているほか、プリンストン大学で長年クリエイティブライティングを教え、リチャード・プレストンやエリック・シュローサー、ジェニファー・ウェイナー、デイヴィッド・レムニックなど名だたるノンフィクション作家を生みだしてきた。
言葉のどんな定義からいっても彼は生産的なのだが、その働き方は多忙さや激務とは無縁のように見える。
この気づきが、本書の中心となるアイデアに発展した。知的労働の問題は生産性そのものにあるのではなく、生産性の誤った定義にあるのではないか?
忙しい=生産性が高い?
現代人をたえまなく苦しめる過重労働は、生産性を「忙しさ」と同一視する風潮に由来する。メールやチャットにすばやく返信し、大量の会議をこなし、タスクをどんどん引き受け、長時間バリバリと働く。それが仕事ができる人のイメージだ。
でも詳しく調べてみると、そう考える根拠はとくにないように思える。まったく違うやり方が生産的であると評価されてもおかしくないはずなのだ。
満杯のタスクリストを抱えて活発に動きまわるよりも、ゆっくりと、静かに働くほうが生産性が高い可能性もある。
成果を出す人の働き方「3つの共通点」
さらにこの問題を掘り下げるうちに、昔の知的労働者たちの習慣や儀式から多くを学べることに気がついた。21世紀の仕事の現実をうまく考慮に入れれば、それらは単なるインスピレーションにとどまらず、現代の仕事観を変革するための豊かな情報源になるはずだ。
こうした洞察に突き動かされ、仕事への向き合い方を考え直すうちに、現代の過労状態に代わる新たな仕事観が浮かび上がってきた。
スローワーキング……持続可能かつ有意義なやり方で知的労働に取り組むための仕事哲学。以下の3つの原則に基づく。
1.削減― やるべきことを減らす
2.余裕― 心地よいペースで働く
3.洗練― クオリティにこだわり抜く
これから見ていくように、スローワーキングは忙しさを否定する仕事哲学だ。
過剰な仕事量はけっして名誉ではなく、成果をさまたげる障壁である。仕事はもっと変化に富んだ人間的なペースで進めるもので、集中的に働く時期もあればゆっくり休む時期もあっていい。やたらと頑張っている感をアピールするよりも、黙ってクオリティの高い仕事をする。それがスローワーキングの基本姿勢だ。
これらの原則がなぜ大事なのか、どのように実践していけばいいのかを、本書では詳しく論じていきたい。
(本稿は、『SLOW 仕事の減らし方~「本当に大切なこと」に頭を使うための3つのヒント』(カル・ニューポート著、高橋璃子訳)の内容を一部抜粋・編集したものです)