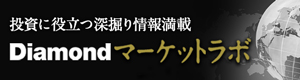埼玉県八潮市の県道交差点で発生した道路陥没現場=2月3日[草加八潮消防局提供] Photo:JIJI
埼玉県八潮市の県道交差点で発生した道路陥没現場=2月3日[草加八潮消防局提供] Photo:JIJI
人ごとでない八潮市の道路陥没事故
成長期に整備の社会資本が耐用年数を迎える
埼玉県八潮市で1月28日、道路が突然陥没し、トラックが転落した。運転手の安否は不明だ。
報道によると、下水から硫化水素が発生し空気に触れて硫酸となり、これが下水管を腐食させ、管が壊れて周辺の土砂が流れ、道路内に空洞ができて陥没したのだという。
穴は、深さが最大15メートル程度で、幅は40メートル程度まで広がった。周りの住民も、穴がさらに広がらないかと心配だろう。また、周辺の市町村に対しては、下水道使用の抑制が要請されている。影響は120万人に及ぶ。
同じような事故は、いつどこで起きるか分からない。そして誰が巻き込まれるかも分からない。集団登校中の生徒たちが巻き込まれてしまう可能性もあり、そうしたことを考えるとぞっとする。
今回の事故について重要なのは、これは単発的、偶発的な事故ではなく、極めて大きな問題の一部が必然的に表面化したものであることだ。
大きな問題とは、日本の社会資本の劣化だ。下水道だけでなく、道路、橋梁、トンネルなども、経年劣化によって事故が起きるかもしれない。
日本では、高度成長期に急激な都市化が進み、80年代までの成長期において社会資本が急速に整備されたが、それらが、耐用期限を迎えているのだ。
すでに2020年時点で道路橋の30%、トンネルや港湾施設も2割が耐用年数を超えている。だから、類似の事件が、日本のさまざまな地域でこれから多発する危険がある。