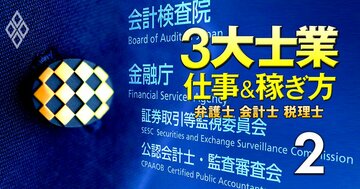Photo by Yoshihisa Wada
Photo by Yoshihisa Wada
監査法人業界で総売上高トップに君臨する有限責任監査法人トーマツ。監査証明業務の規制強化やサステナビリティ情報の開示がスタートするなど、環境の激変に直面する中で、最大手の法人をどのように運営していくのか。特集『公認会計士「実名」「実額」2364人ランキング』の#15で、大久保孝一代表執行役に話を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド編集部副編集長 片田江康男)
サステナ情報の開示は
可能性を広げるチャンス
――2027年3月期から、東京証券取引所プライム市場に上場の時価総額3兆円以上の企業でサステナビリティ情報に関する開示が義務化されます。監査法人業界ではチャンスと捉える人も多いですが、どう考えていますか。
チャンスだと考えています。四大監査法人以外で、世界的なネットワークに属しており、独立性を保ちながら高いレベルの保証業務を担えるプロフェッショナルファームがないとしたら、サステナの保証業務は、われわれが担うべきなのだと考えています。公認会計士法に書いてあるように、われわれは資本市場の健全な発展に貢献しなければなりません。それを考えると、われわれが保証業務を担うのが最も合理的だと思います。
四大以外の監査法人は、おそらくさまざまな専門家と協力して担っていくのだと思います。われわれにおいても、財務諸表監査ではITの専門家やバリュエーションの専門家、年金の専門家など、多くの協力を得て進めています。そういう枠組みは、規制する側も規制しやすいでしょうし、情報を受け取る側も信頼しやすいのかなと思います。
――チャンスというのは、保証の報酬を得られるという意味でのチャンスでしょうか。
それもあります。もう一つは、若い公認会計士などにとって、新しいことにチャレンジするチャンスでもあります。若手に新しい可能性を広げてあげられる業務だと思います。それはわれわれのファームで働き続けたいという思いを、高めることにもなります。もしかしたら、公認会計士以外の専門家も引き付けることができるかもしれません。われわれが違うステージに行ける可能性が広がります。
――サステナ情報の開示や保証がスタートする中で、トーマツとして、四大の中で差別化できる点は何でしょうか。
四大監査法人はそれぞれグローバル展開するグループの一員であり、日本ではコンサルティングやファイナンシャルアドバイザリーの専門の組織を抱えており、似たり寄ったり。日本において監査法人業界トップのトーマツは、自らの強みをどう捉えているのか。次ページでは若手公認会計士の監査離れ問題や、キャリアと出世、給与などについても話を聞いた。