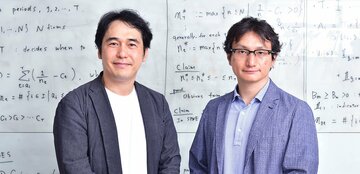社会変革の起こし方を
つかんだ時
――映画から離れますが、山田監督がNHKでディレクターされた番組『石田ゆり子 世界の犬と猫を抱きしめる~台湾編』でも、犬を飼うことによる子供たちへの良い影響についての話がありました。
今年1月に放映しました。台湾の小学校・中学校・高校では、動物に対する意識を高めるスクールドッグ・スクールキャット制度があります。子供たちが動物を飼うことで命について学んでいくことを推奨していて、政府は資金を出しています。動物を飼うようになった学校では、不登校やいじめが減るという効果が見られ、人間だけではフォローできない心のケアがあると言われています。
――同じシリーズの企画でイギリス編も作られています。そうした海外の状況と日本を比較して、考えられることはありますか?
私がこういう取材を始めたのは東日本大震災があった2011年からですが、その時に比べたら、動物愛護に関して言えば改善はしています。犬と猫の殺処分数は今も1万匹くらいいるのですが、当時は20万匹くらいでしたので、かなり減って良くなっていると思います。そこに関しては、日本は改善しています。
ただし、被災地で動物と一緒に避難できるかどうかなどは、まだまだ課題はたくさんあります。
――山田さんが監督をされた映画『犬に名前をつける日』や、脚本を担当された映画『犬部!』に登場するような人々の活動の成果が少しずつ出ているのでしょうか。
私がここ10数年こうした取材やってきて感じたことは、「社会は変えられる」ということです。
映画『犬に名前をつける日』を撮った時、2012年頃から千葉の動物愛護センターに取材で通うようになるのですが、最初に行っていた頃は、野良犬として同じ日に捕えられた犬たちは集団で同じ部屋に入れられていました。殺処分の日まで毎日順に部屋を移動していくのですが、強い犬、弱い犬、気の荒い犬、繊細な犬など全て一緒なので、喧嘩して強い犬が弱い犬を殺してしまうこともありました。あるいはパルボウイルスみたいな強烈な感染症が流行ると全員がかかって死んでしまうなど、ひどい状態でした。
でも、何年か通っていると、変わっていったのです。捕獲された犬が個別管理になって、他の犬に殺される犬が減り、全ての犬にワクチンを打つようになって感染症で死ぬ子が減ったり、ドッグランができたりと改善されていきました。
3年目ぐらいの時に、センターの人に尋ねたのです。かつてどうにかならないのですかと聞いた時は「自分は公務員だから規則通りにするしかない」と言っていたけど、改善したじゃないですか、なぜですかと。そうしたら、「動物愛護団体の人たちが毎日のようにやってきて、明日死ぬかもしれない子に餌をやったり、ボロボロの子でも綺麗にしたら里親が見つかるかもしれないと言って体を洗ったりするのを見ていたら、自分も規則通りにやっていればいいとは思えなくなってきた」と言われたのです。
自分に何かできることはないかと考え、個別管理したりワクチンを打ったりする予算をもらえないかと上司に交渉したと言うのです。そのセンターは、犬を飼いたいという人への譲渡活動に注力するようになり、殺処分数が激減しました。
その人の話を聞いた時、目の前で何かを救ってみせるという行為は、誰かがそれを見ていて、そのうちの何人かは行動を変えるんだなと思いました。社会変革って、こうやって起こすんだということをつかみました。
――社会は変えられる、と
取材をしていると、自分も人間に希望を持てるようになるのです。戦地に行ったりすると、戦争ってひどいなとつくづく思うけど、一方でそれに抗う人たちがいて、それを見ると自分の気持ちが洗われるようなことも結構あるんです。
怖い目にも遭うけど、日本にいたら得られない人間の美しさを見ることができる。だから、私たちのこういう小さい映画でも、頑張って広めようとしています。
――映画を見てそういう風に変わる人もいるでしょうね。
希望を捨てたくないなと思っているのです。私の残りの人生もそう長くはないかもしれないけど、取材して、そうした良いことを知ることができると、自分ももう少し頑張ろうかなと思えるのです。
 (c)『犬と戦争』製作委員会
(c)『犬と戦争』製作委員会
――山田監督にとって、犬はどういう存在なのですか。
犬のことは普通に好きですけど、例えば今ウチで飼っている犬のハルが、朝起きたらゴキブリになっていたとするじゃないですか、カフカの小説『変身』のように。そうなった時、ゴキブリになったハルを愛せるのだろうかって自分に問いかけると、最初はゴキブリだから触れないと思うのですが、どう見てもこれはハルだなと思ったなら、大切にすると思うんですよ。
であるならば、私は犬の造形を愛しているわけではない。もちろん、耳とか黒い鼻とか尻尾とかの造形も好きなのですが。でも、それ以上に、犬という生き物の持つ何か、愛情豊かな生き物を見られることが、この上なき幸せなのだなということになります。
この映画のナレーションは、俳優の東出昌大さんにお願いしました。とても動物が好きな方で、彼は「犬が好きだからこの映画のナレーションを引き受けた」と言ってくれました。そして、「犬って愛の塊じゃないですか。これ以上に愛を教えてくれる生き物を僕は知らない」と。私もそういうふうに思います。
犬ほど愛情を真っ直ぐに向けてくれる動物はない。神様の仕業かわからないけど、誰かが人類に与えてくれた、愛を知らせる生き物なんだと思います。
――なぜ、『犬と戦争』という題名にしたのですか。
ドラマでもフィクションでもないから、犬と戦争について、私がウクライナで見たことを報告させてもらいます、というストレートな気持ちでタイトルをつけました。(了)
 本人提供
本人提供山田あかね
映像作家。東京都出身。テレビ制作会社勤務を経て、1990年よりフリーのテレビディレクターとして活動。ドキュメンタリー、教養番組、ドラマなど様々な映像作品で演出・脚本を手がける。2009年に制作会社「スモールホープベイプロダクション」を設立。2010年、自身が書き下ろした小説を映画化した『すべては海になる』で映画初監督を務めた。その後、東日本大震災で置き去りにされた動物を保護する人々を取材したことをきっかけに、監督2作目として『犬に名前をつける日』(2015年)を手がける。2021年には、青森県北里大学に実在した動物保護サークルを題材にした映画『犬部!』で脚本を務めた。2022年2月24日に起きたロシアによるウクライナ侵攻から約1カ月後、本作の取材を開始。その最中で、飼い主のいない犬や猫の医療費支援をする団体「ハナコプロジェクト」を俳優の石田ゆり子さんと創設した。現在は、元保護犬の愛犬“ハル”と暮らす。