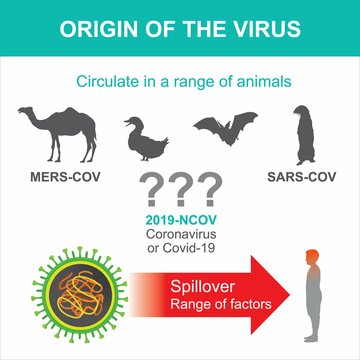Twitterの生みの親であるジャック・ドーシーは、1980年代のハッカー・カルチャーの申し子で、言論・表現の自由こそが世界を進歩させるとかたく信じていた。そして、政府や企業のような中央集権的な組織を強く疑っていた。
【参考記事】
●facebookのファクトチェック廃止やTwitterの買収から「そもそも民間企業による投稿管理が可能なのか」を考える
広告主の意向をつねに忖度し、ファクトチェックの政治的論争に巻き込まれ、コンテンツモデレーションで翻弄されることにうんざりしたドーシーは、「ブロックチェーン台帳上でユーザーがメッセージを投稿できるソーシャルネットワークのアイデア」を信頼できる腹心たちとひそかに議論していた。
――その後、Twitterを買収しようとしたイーロン・マスクともこの話題を話しあった。この新しいSNSは、次のように説明される。
ソフトウェア開発者は、基礎技術を使って、独自のデザイン、ポリシー、アルゴリズムを持つ固有のネットワークを構築することができる。あるソーシャルネットワークにいる人たちは、別のソーシャルネットワークにいる人たちと交流することができるが、各々の体験はどのソーシャルネットワークにサインインするかによって異なる。
人種差別的あるいは性差別的な投稿であれ、誤情報であれ、制限されることなくあらゆる投稿を見たいと思うユーザーにはそのためのネットワークが存在する。そうした投稿はできる限りブロックしたいと思うユーザーにもそのためのネットワークが存在する。無数のネットワークが存在し、それらはそれぞれのクリエイターの好みやニーズに基づいて構築される。ユーザーが望むなら、あるネットワークから別のネットワークに乗り換えることも可能だ。その場合、過去の投稿やデータも一緒に移すことができる(『TwitterからXへ 世界から青い鳥が消えた日 ジャック・ドーシーからイーロン・マスクへ、炎上投稿、黒字化、買収をめぐる成功と失敗のすべて』鈴木ファストアーベント理恵訳/翔泳社)。
この次世代SNSでは、「ツイッターのような企業は、人々の言論の自由を侵害しているのではないかと苦悩することなく、ビジネスに必要だと思われる投稿監視を継続していけばいい」とされる。しかし、それはいったいどのような仕組みなのだろうか。
 Photo/ナオ / PIXTA(ピクスタ)
Photo/ナオ / PIXTA(ピクスタ)
それを教えてくれるのが、シリコンバレーのベンチャーキャピタリスト、クリス・ディクソンの『Read Write Own シリコンバレートップクラスVCが語るインターネットの次の激戦区』(大熊希美訳/日経BP)だ。原書のタイトルも同じだが、副題は“Building the Next Era of the Internet(次世代のインターネットをつくる)”となっている。
Web3.0でユーザーはコンテンツのRead(読み取り)とWrite(書き込み)だけでなく、自分の著作物を所有(Own)できるようになった
ディクソンは「ネットワークの設計がネットワークの運命を左右する」として、それを3つの時代に区分する。それを簡単にまとめると、次のようになる。
Web1.0 プロトコルネットワーク「読み取り(リード時代)」
電子メールやウェブのように、ソフトウェア開発者のコミュニティといったステークホルダーがネットワークを制御するシステム。「これらのネットワークは平等主義的かつ民主的で、利用に許可はいらない。誰でも無料で使える。このシステムではお金と権力はネットワークの末端に流れる傾向にあり、それがネットワークを活用したサービスの成長を促進させる」
Web2.0 企業ネットワーク「読み取り/書き込み(リード/ライド)時代」
コミュニティではなく、企業がネットワークを所有し制御している。中央集権型で、利用には許可がいるが、企業は洗練された機能を素早く開発し、投資家を引きつけ、成長に再投資するための利益を得られる。お金と権力はネットワークの末端を構成するユーザーや開発者から中心、つまりネットワークを所有する企業へと流れる。
Web3.0 ブロックチェーンネットワーク「読み取り/書き込み/所有(リード/ライト/オウン)時代」
誰もがネットワークのステークホルダーとなり、かつては株主や従業員といった少数の関係者だけが手にしていた権力と経済的な恩恵を享受できる。「この新しい時代は大手テック企業の中央集権に対抗し、インターネット本来のダイナミックなあり方を取り戻すものだ」とされる。
ディクソンの歴史観を私なりに整理すると、Web1.0の“Read時代”ではHTMLを使ってホームページを作成できる者(政府や報道機関、企業など)が一方的に情報を提供し、一般のユーザーはそれを読むだけだった。インターネットは、新聞や雑誌、テレビ、ラジオと競合する「マスメディア」でしかなかった。
次いでWeb2.0の“Read/Write時代”では、ユーザー自身がコンテンツを発信できるようになった。だがブログや匿名掲示板にあふれるコンテンツは玉石混交で、しばしば誹謗中傷や非合法なものが含まれていた。この問題には、ふたつの解決策があった。
ひとつは非中央集権的な方法で、ディクソンはRSS(Really Simple Syndication)を高く評価する。ユーザー自身がフォローしたいブログやSNSをリスト化し、更新されると自動的に通知が来る仕組みだ。
もうひとつは中央集権的な方法で、Facebookが典型だが、企業がネットワークを管理し、ユーザーにコンテンツを推奨し、不適切な投稿を削除したり、アカウントを凍結したりする。
当初はどのSNSにもRSSへのフィードが組み込まれていたが、やがてプラットフォーマーはそれがユーザーの囲い込みの障害になることに気づく。こうしてFacebookやTwitterはRSSを排除するようになり、このアイデアは生き延びることができなかった。
RSSの失敗の原因は、ユーザー(クリエイター)はネットにコンテンツを投稿できるものの、そのコンテンツの所有権が企業にあるからだ。その結果、企業(GoogleやMeta、X、TikTok、LINE)はネット全体の繁栄や最適化ではなく、自社の収益の最大化だけに注力するようになる。ユーザーは言論・表現の機会を与えられたものの、それは企業(プラットフォーマー)によって搾取されることでもあるのだ。
それに対してWeb3.0では、ユーザーはコンテンツのRead(読み取り)とWrite(書き込み)だけでなく、自分の著作物を所有(Own)できるようになる。これによってインターネットは新しい段階にパラダイムシフトし、ユーザーやクリエイターに収益が公平に分配され、ネットだけでなく社会全体がより繁栄できるようになるとディクソンは主張する。