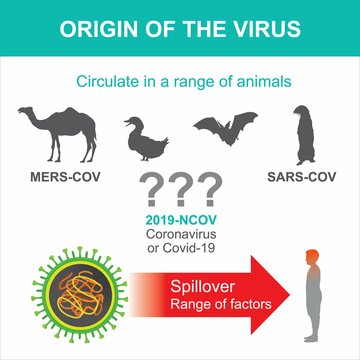『「一人一杯ラーメン注文して」ルール破ったカップルに店が激怒、SNSで話題 客に問題あったのか?』という記事がYahoo!ニュースでアクセスランキング1位になり、3000件近いコメントがついた。「大人は一人一杯」というルールを掲示しているラーメン店を訪れたカップルが、2人で一杯のラーメンしか注文せず、店主が客に返金したうえで帰ってもらい、「今後はご来店いただかなくて大丈夫です」と投稿したのだという。
 Photo/metamorworks / PIXTA(ピクスタ)
Photo/metamorworks / PIXTA(ピクスタ)
このようなささいな出来事が、ロシアに侵攻されたウクライナや、イスラエル軍に攻撃されているガザのパレスチナ人の窮状よりも大きな注目を集めるのはなぜだろうか。それはこの社会が不正に満ちているからではなく、わたしたちが道徳が過剰になった世界に生きているからだと述べるのが、ハンノ・ザウアーの『MORAL 善悪と道徳の人類史』(長谷川圭訳/講談社)だ。ザウアーは1983年生まれのオランダの哲学教授で、最新の進化論や人類学の知見を上手にまとめて、道徳の起源とその歴史を論じている。
協力こそが「わたしたちが人間である理由」
道徳についての最大の謎は、「ヒトはなぜ協力するのか」だ。なぜならほとんどの場合、相手の要求を拒否し、ときには相手をだまして自分の利益を追求することが、生存と生殖の可能性を最大化するという意味での進化の最適戦略になるからだ。ヒトにもっとも近い種であるチンパンジーは、共同で狩りをすることはあるものの、食料を仲間と分け合うことはほとんどない。
人間社会でも、協力にはフリーライダー問題がついてまわる。1人では2の利益しか得られないが、みんなで協力すると1人あたり5の利益が得られるとしよう。これは素晴らしいことだが、じつはもっとうまいやり方がある。自分はさぼって仲間に働かせて、分配だけ受けることで利益は10になる。
このようなケースで、利己的な行動をする者によって苦い思いをさせられたことは、学校や会社で誰もが体験しているだろう。実際、行動経済学の実験では、最初は互いに協力することに前向きでも、対価や代償を払わずに利益を得る便乗者=フリーライダーがいることがわかると、たちまち公共のための個人の貢献度は減り、最後にはほぼゼロになることが繰り返し確認されている。「バカを見る正直者」には誰もなりたくないのだ。
「進化における選択圧は、つねに道徳的な行動に不利になるように働く」とザウアーはいう。フリーライドの機会があれば、それを利用するのが「適者」で、みんなのために汗を流す正直者は子孫を残すことができず、進化のプールから排除されてしまうのだ。
この論理はきわめて強力だが、それにもかかわらず、協調本能が生得的であることを示す多くの証拠がある。生まれてまもない赤ん坊ですら、意地悪をする利己的な人形ではなく、仲間を助ける利他的な人形に手を伸ばす。チンパンジーに協力を教えるのは困難だが、人間の子どもは大人がなにも指示しなくても自然に協力する。
ここからわかるのは、人類がチンパンジーとの共通祖先から分岐したのち、協力という(利己的な遺伝子にとって)不合理な行為をするように、なんらかの進化の淘汰圧がかかったらしいことだ。
もちろん人間以外にも協力する生き物はいる。アリやハチのような社会性昆虫は、特殊な生殖の仕方によって、自分が子どもをつくるよりも、女王アリや女王バチにできるだけ多くの子どもを産ませるように利他的に行動することで、より多くの遺伝子を後世に残すことができる。これは「血縁淘汰(包括適応度)」と呼ばれ、人間の場合、家族・親族のような血のつながった(遺伝子を共有する)者同士が結束し、協力することを説明する。
親密な共同体では、血縁関係がなくても、誰かに親切にすると、自分が困ったときにお返し(助力)を期待できる。チスイコウモリでは、家畜の血をたくさん吸うことができた個体は、腹をすかせた個体がいると血を吐き戻して与える。するとその相手は、親切にしてくれた相手を覚えておいて、次に逆の立場になったときは自分が吸った血を分け合う。これは「互恵的利他主義」といわれ、人間社会でも、中元や歳暮のお返しなど、至るところで互酬性を見ることができる。
このように社会的な生き物の観察から利他性を説明することはできるが、それにも限界がある。ヒトは何千人、何万人、あるいはそれ以上の巨大な共同体をつくり、血縁でもなく、互恵的な関係にもない相手と協力するからだ。このような生き物は、自然界にはヒト以外には存在しない。協力こそが、「わたしたちが人間である理由」なのだ。
人類が、チンパンジーにはない高度な互恵的利他主義を進化させた理由とは?
人類とチンパンジーの共通祖先には名前がないが、便宜的に「CHLCA(チンパンジー=ヒト最終祖先:Chimpanzee-Human Last Common Ancestor)」と呼ばれている(このあとにチンパンジーからボノボが分岐した)。
CHLCAから分かれて人類が“誕生”したのはおよそ500万年前とされていたが、ゲノム分析によって600万~760万年前になり、この分岐後に人類とチンパンジーが交雑していた(子どもをつくっていた)可能性も否定された。CHLCAは樹上生活を送っていたが、地形の変化などの理由で、森が消滅してサバンナに変わる環境に取り残された者たちが人類の祖先だと考えられている。
だが、人類誕生についての議論は決着したわけではなく、2014年の『Science』に、チンパンジーの遺伝的変異に関する研究によると、CHLCAからの遺伝的分化が約1300万年前と判定されたという論文が掲載された。だがこれは従来の説を否定するわけではなく、CHLCAから最終的に人類とチンパンジーが遺伝的に分かれるまで500万~600万年かかったということのようだ。
物的証拠がまったく存在しない以上、人類がいつどのように生まれたのかの謎は容易に決着しないだろうが、CHLCAから分岐したあとのホモ属の特徴として近年、注目を集めているのが投擲(とうてき)、すなわち石を投げる能力だ。
最古の石器はタンザニアのオルドヴァイ渓谷で発見された260万年前のオルドワン石器だったが、その後、ケニアのトルカナ湖西岸の干上がった川床で、330万年前のものと推定される意図的に鋭利にした石器が見つかった。だがもちろん、これが最古というわけではないだろう。
以下は私見だが、石器をつくるようになる前に、人類の祖先ははるかに長い期間、投擲をしていたのではないか。鋭い牙や爪も、強靭な筋力ももたない類人猿は、木から降りてしまえば身を守るものがなにひとつない。それでも生き残れたのは、石を投げて捕食者を追い払うようになったからだと考えるのは理にかなっている。
なぜ親指が残りの4本の指と向き合うように進化したのかも、この仮説で説明できる。そのほうが、石をつかむのに都合がよかったのだ。サバンナで生き延びるために石を握って遠くまで投げる遺伝的変異が選好され、それが石を打ちつけて角をらとがせることにつながった。
この投擲能力は、ふたつの意味で人類の運命に大きな変化をもたらした。ひとつは、徒党を組めば暴力的なメンバーを簡単に排除できるようになったこと。どれほど身体が大きくても、四方から石を投げられたら防ぐことはできないだろう。このようにして、すくなくとも男社会のなかでは、支配-被支配のヒエラルキーをつくることができなくなって、平等主義的な共同体が成立した(支配者になろうとした者は集団の制裁を受け、殺されてしまった)。
もうひとつは、投擲によって大型獣を狩り、肉を手に入れられるようになったこと(その前段階として、ハイエナなどを投擲によって追い払い、屍肉(しにく)をあさった時期があっただろう)。
肉は植物(果実)よりも効率的にエネルギーを取り込めるため、肝臓や消化器官のような代謝コストのかかる臓器を小さくし、その分を脳に割り当てることができる。この「代謝革命」は火の使用(諸説あるものの50万年ほど前とされる)によって加速し、肉からさらに効率的にカロリーを吸収し、脳をより大きくすることができた。
それに加えて、大型獣の肉は一人で食べ切ることはできず、放っておけば腐ってしまう。だとすれば、仲間と分け合って、自分が飢えたときにお返しをしたもらったほうが生き延びる可能性は高くなるだろう。こうして人類は、チンパンジーにはない高度な互恵的利他主義を進化させたのだ(ハーマン・ポンツァー『運動しても痩せないのはなぜか 代謝の最新科学が示す「それでも運動すべき理由」』小巻靖子訳/草思社)。