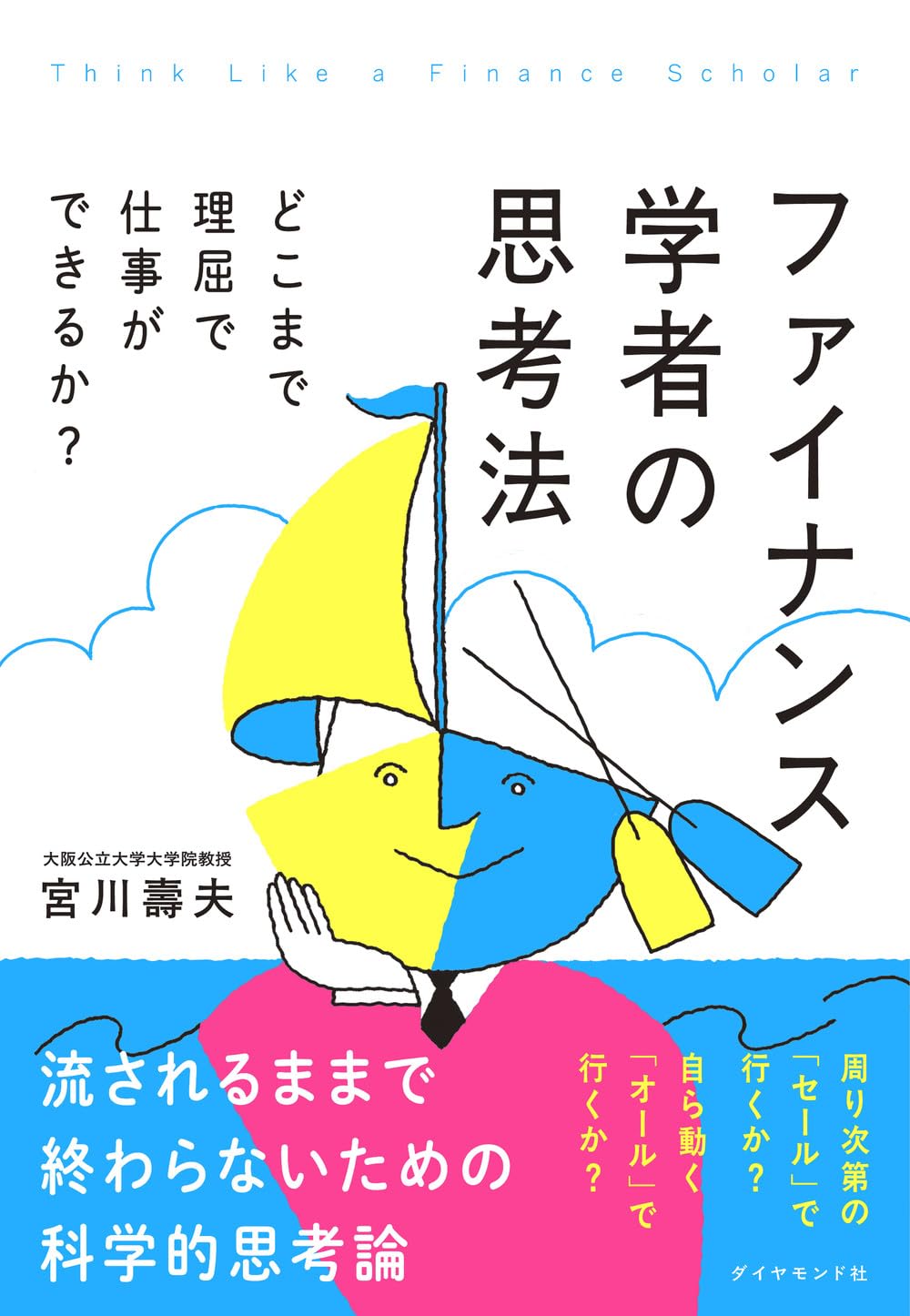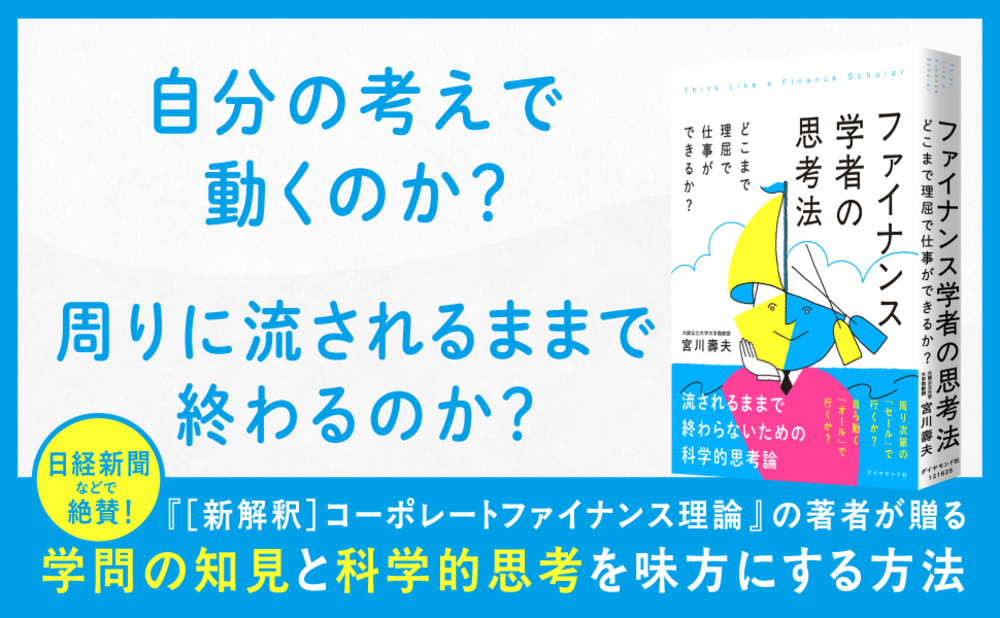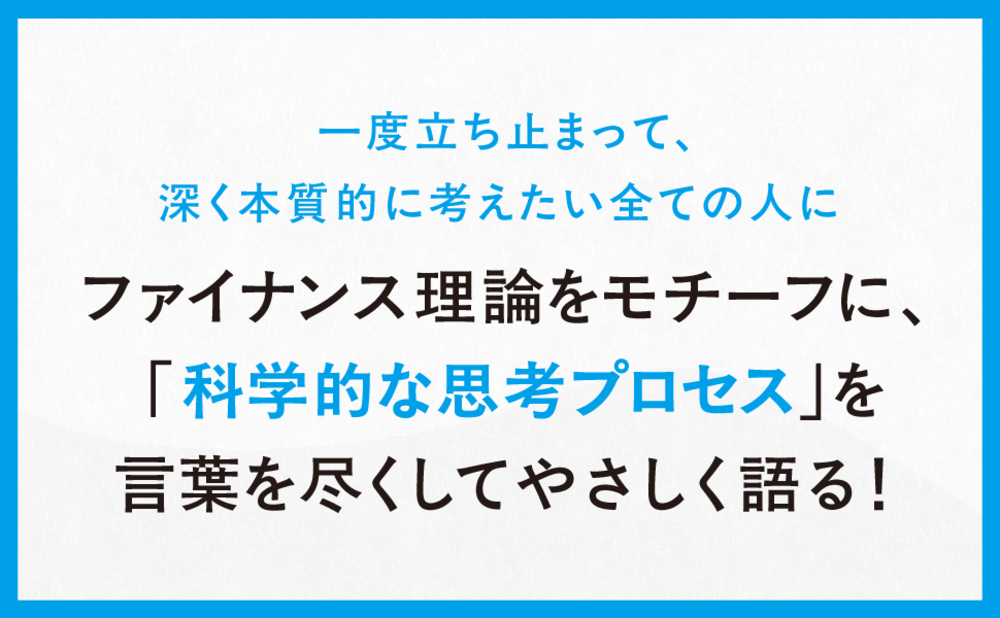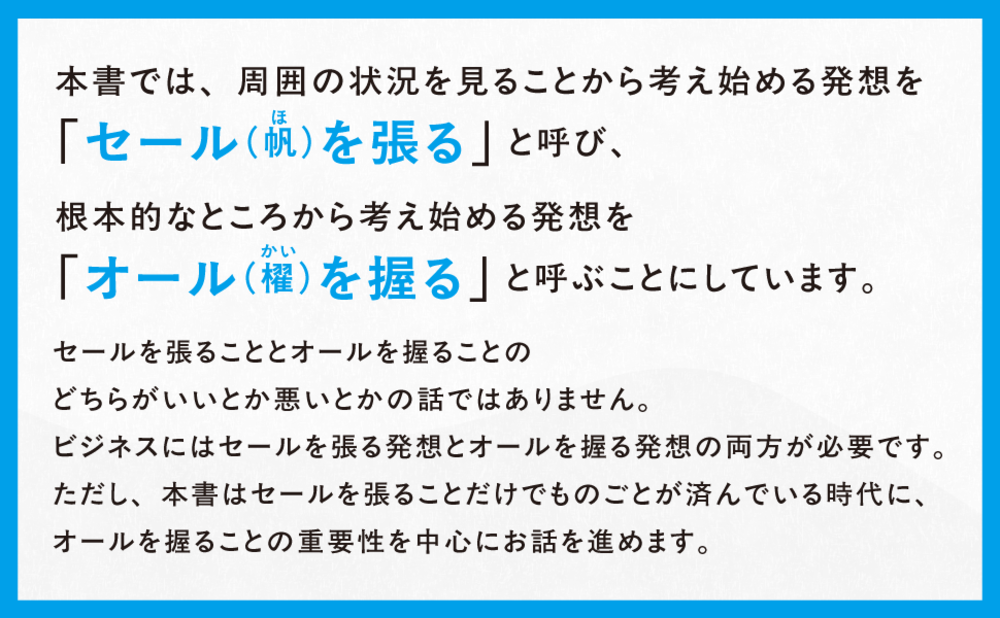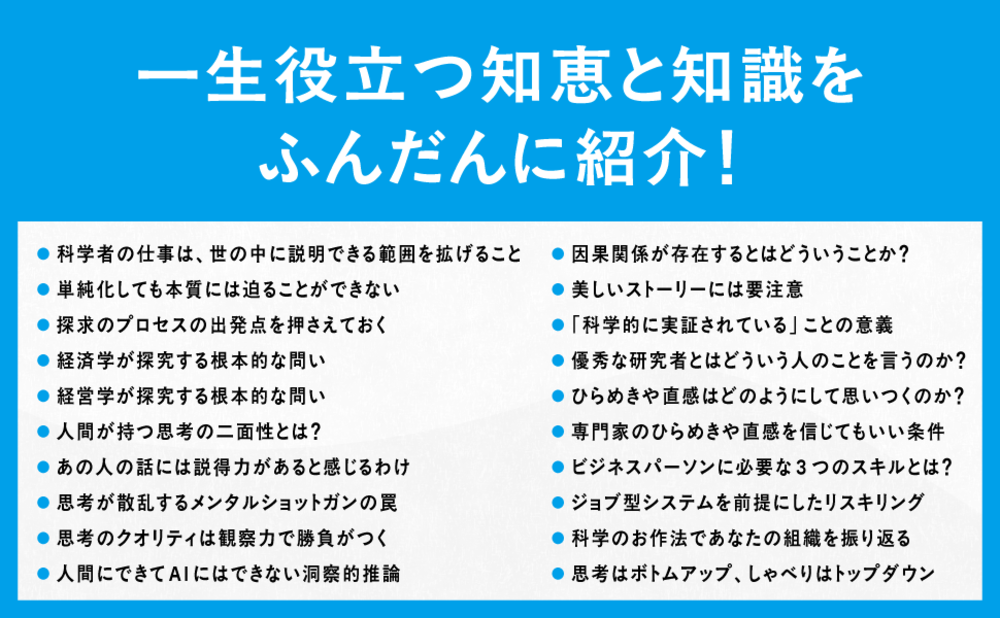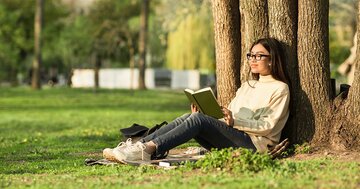新刊『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』は、ものごとを深く本質的に考えたい人に贈る、科学とビジネスをユニークな形でつないだ知的エッセイ。投資銀行と米系コンサルを経て大学教授へと転身した異色の経歴を持つ宮川壽夫氏が、話題書『新解釈 コーポレートファイナンス理論 「企業価値を拡大すべき」って本当ですか?』に続いて世の中に問いかける第二弾です。
ファイナンス理論をモチーフに「科学的な思考プロセス」をいかにしてビジネスの現場に活かすか、その方法と限界について軽妙な語り口でやさしく説きます。風を読みながら適応する「セール(帆)の理論」と、風の方向にかかわらず根本的に考えて進む「オール(櫂)の理論」、本書で展開されるこの新たなメタファーを通じて科学の思考を学べば、明日からきっと仕事へのアプローチが変わります。
今回は、ビジネスパーソンに必須のスキルを経営学の視点から研究したロバート・カッツの「3 skills approach」を起点に、本来の「学び」の可能性を探ります。
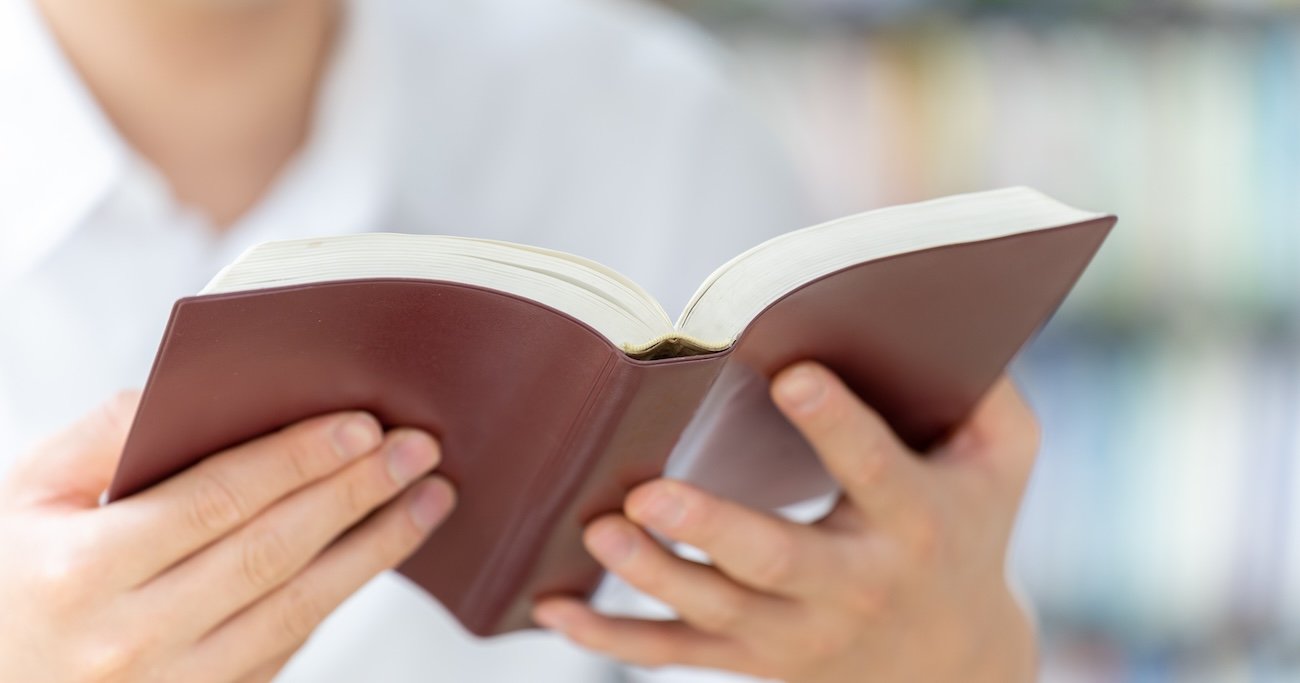 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
この講義を受講するとなにができるようになるんですか?
大学にはシラバスという制度があります。大学の教員は、自分が担当する科目について、どのような内容が講義され、どのように評価を行うかといったことをあらかじめ明示することが義務づけれられています。これはだいたい2000年前後くらいから突如として日本の大学に流行り始めたもので、2007年の文部科学省による規定が正式な根拠とされているようです。ですからそれ以前に大学を卒業した方々にはシラバスなんてあまりなじみがないかもしれません。
シラバスの制度はもともと講師を外部人材から求めることが多く、各講座の独立色が強いという事情を持った米国の大学で行われてきたもので、私が一時期いたシアトルのワシントン大学にもありましたが、ヨーロッパの大学にはほとんどないと聞いています。たしかに講義計画は教員と学生の双方にとってとても大事だとは思うのですが、例によって日本の熱心なお役人シゴトはシラバス制度の導入以来とどまるところを知りません。シラバスの内容はどんどん細かく厳格に決められていき、今やわずかな狂気さえ感じさせるほどの深みにハマっています。
現在のシラバスには記載が求められる項目が「シラバス作成要領」として一律に決まっており、講義の「目的と概要」、「各回ごとの講義内容」、その各回ごとに「事前・事後の学習内容」、「到達目標」、「使用教材」、「成績評価方法」等々といったところですが、とくに「到達目標」の欄には「この科目を受講するとなにができるようになるのか」を具体的に「○○○○ができるようになる」という表現を使って記載することとなっています(作成要領には本当に「○○○○」と四つの○が書いてあります)
昨年も私がコーポレートファイナンス理論のシラバスを提出したところ、学内のシラバス担当の部署からメールが来て「○○○○ができるようになる、という表現での到達目標の記載がありません」といってシラバスの書き直しを要求されました。私にとっては狂気の沙汰としか思えません。「CAPM理論(資本資産評価モデルというファイナンス分野の知識です)の公式を覚えたらなにができるようになるのか?」って言われてもなあ。それは高等教育とそれを受ける学生が持っている無限の可能性に対する冒とくだと私は強く思っています。この勉強をしたら「なにができるようになるのか」があらかじめ具体的に決まっているのは今のところ自動車教習所くらいです。縦列駐車ができるようになるとか、坂道発進ができるようになるとか。
大学教育はそういうものではありません。なにかを一方的に教えて学生が「できるようになる」ところではなく、私の役割は、学生からなにかを引き出して、一緒に伴走することです。だから学生は学んだ知に対して自らのリアクションを求められます。そのリアクションはもちろん予測を超えて多岐にわたりますが、それどころか、それらがどこに向かうのかさえ一時的にはわかりません。だから私のようなプロの伴走者が必要になります。私の学術的専門性と学生の可能性を最大限コーディネートするために、大学の教室はかなり懐の深さを持ったものでなければなりません。
私が社会人大学院の修士課程に入学した最初の講義のときに、ある老教授がこう言いました。
「キミたちね、これから2年間でね、そうだな、最低でも2トントラック一杯分くらいの本を読んでもらうことになるからね」
私はこれを聞いたとき言い知れぬほどスカイハイな気持ちになり、なるほど大学院という高等教育機関はまさに学問の世界の広大さと深遠さを思い知る場所なんだと悟りました。大学のキャンパスは、自分の目の前に果てしなく広くて深い空間が広がっていて、そこで走ったり転んだりしながらどこまで遠くに行ってもいいんだという開放感と、だけどいつなにが目の前に現れるかわからないという神秘性の両方を思う存分に味わえる空間でなくてはなりません。もしも、あのときこの老教授が「私の講義を受けるとね、そうだな、具体的には○○○○ができるようになるんだよ」と言ったとしたら、今の私はありませんでした。
ただし、「2トントラック一杯分」はこの老教授の間違いで(ひょっとしたら私の聞き間違いかも)、2年間でそれほどの量の本を読むことはかなりの速読者でも不可能です。「2年間で2トントラック一杯分」の読書量とは、だいたい400ページの文庫本なら一日およそ14冊、上下合わせると1600ページあるブリーリー/マイヤーズ/アレンの『コーポレート・ファイナンス』のようなハードカバーの教科書だと一日およそ3冊を毎日読まなければ修士課程を修了することができない計算になります。老教授、なかなかふっかけたものではありますが、この「2トントラック」発言は、多くの学生にとってその後の学びの姿勢を変えたはずです。今でも筑波の同窓会ではこのことが話題になります。「あれは刺激的だったね」と。
学べばなにものかに変貌できる
大学の講義はテクニカルスキルを身につけるための典型的なひとつのトレーニングの場かもしれませんが、講義を聴いている途中でそのスキルがコミュニケーションスキルとなり、コンセプチュアルスキルに発展するかもしれませんし、10年後にそうなるかもしれません。ただし、そこで得たものがどのようなものに変貌していくかは個人によって異なります。大人も含めて大学生以降の学びは、高校までの勉強と違って、ただ単に数学的に知識を増やすことではなく、なにものかに変貌することではないかと思います。
2トントラックをたとえにした老教授の示唆は「それだけの本を読むとどうなるかって? それはキミ次第だよ。確実に言えるのはキミの中になにか変化が起きるはずだ。ただし、それがどういう変化でいつ起きるか私にはわからないがね」ということだったと私は感じました。それは大学院を修了した私自身がそうであったように。
おそらく高校生までは受動的な理解力とか飲みこみの速さがある程度の勝負を決めます。もちろん理解力とか飲みこみの速さは後々も重要な武器になるのですが、しかし、私が大学で扱っているもの、そしてビジネスの世界で扱ってきたものはすぐに飲みこめてすぐにできるようになるものばかりではありません。すぐには飲みこむことができないので、大学の研究室の中を師匠と一緒にあっちへ行ってみたり、こっちへ行ってみたり、ウロウロ歩き回ります。そのさまよい歩いたことの意味がずいぶん後になって少しずつじわじわとわかりだし、想像もしなかった別のものに変わっていくことがあります。そして、ようやく理解できるようになったとき、自分がかつて見てきたものは全体の中のほんの断片にすぎなかったことに気づきます。ビジネスもまったく同じで、このプロセスをたどって自分は力をつけてきたのだろうと今になって感じます。
それにしても教養科目にしろ専門科目にしろ「○○○○ができるようになる」というストックフレーズで統一されたシラバス集は考えただけでもかなりグロテスクです。私は高等教育のあり方について、ここはひとつきちんと議論しようと考え、くだんのメールを送ってきたシラバス担当者に電話をすることにしました。できれば直接会って話を聞こうと。ところが、内線電話に出たそのメールの送り主である当該シラバス担当者は(私の記憶が正しければ)、人材派遣の会社から大学に派遣されて、つい最近の異動で現在の部署に来たばかりの方でした。聞くところによれば、渡されたマニュアルを見ながらそれに従っていないシラバスの表現を見つけては担当教員にメールを送るのが彼女の仕事だということです。そのマニュアルもどこから送られてきたもので、だれが作ったものかはわからないと困惑しながらも打ち明けてくれました。彼女はついでに、東京に霞が関というところがあって、文部科学省と書かれた立派な建物があるから、そこに行けばひょっとしたら私の疑問にだれか答えてくれる人がいるかもしれないという有益なアドバイスをくれました。
それ以上のことを彼女に相談するのは気の毒だと思った私はコーポレートファイナンス理論のシラバスの到達目標に「この講義を受講したら縦列駐車ができるようになる」と最後に書いて「シラバス修正完了」のメールを返信しました。しかし、どこの部署からもなにも言ってきませんでした。しばらくは私もそのことをすっかり忘れていたのですが、かろうじてシラバス公開の前にたまたま気がつき、さすがの私でもこれはちょっとまずいだろうと感じたので、その縦列駐車の一文ごとシラバスから削除しました。しかし、その後は二度とシラバス担当者から私のシラバスに対する建設的なコメントも画期的な助言も、やはりありませんでした。
(本記事は『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』より、本文の一部を抜粋・加筆・再編集したものです)