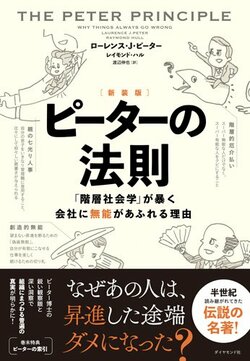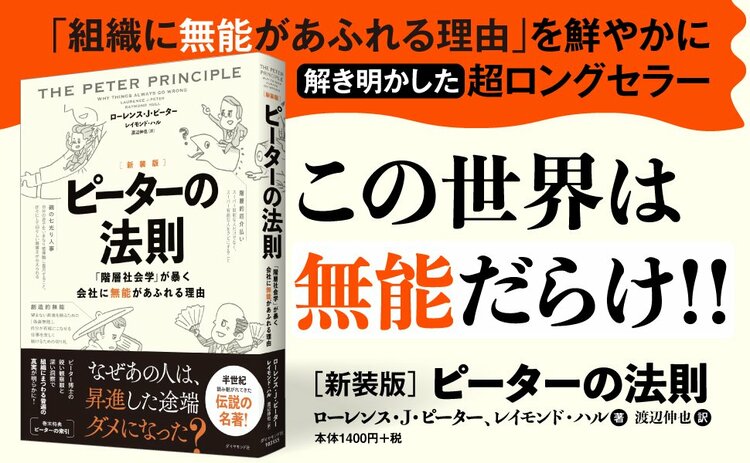階層社会では、人は昇進を重ねると、おのおのの無能レベルに到達してしまう。そんな驚くべき法則を唱え、世界的なベストセラーになったのが、『ピーターの法則』だ。必然的に「世の中のあらゆるポストは職責を果たせない無能な人間によって占められることになる」というメッセージは大きな衝撃を与えることになった。では、そんな世界で個々人が組織で生き残るための知恵とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
昇進した途端、ダメになる理由とは?
帯の文言には、「なぜあの人は、昇進した途端ダメになった?」とある。
企業社会では、そうした声が数多く飛び交っているからに他ならないからだろう。そしてその理由が、豊富な実例とともに、明快かつシニカルに解説されていく。
原著の刊行は1969年。邦訳が出たのが1970年。2018年には、新装版が発売されている。
畳み掛けるようにメッセージしてくるのは、「階層社会では、すべての人は昇進を重ね、おのおのの無能レベルに到達する」というピーターの法則。
そして、「やがて、あらゆるポストは、職責を果たせない無能な人間によって占められる」というピーターの必然だ。
そこから逃れられる方法は、果たしてあるのか。
終点到達というのは、肉体的にも心理学的にも惨めな徴候を伴うし、職業人生の終わりを通告されるようなものだと尻込みをしてしまったでしょうか?
みなさんの心配はごもっともです。(P.195)
実は、この哲学的難題について、どうすればいいのかについても著者は記している。
「昇進を断り続ける」という選択は難しい
たとえ今の仕事で有能だったとしても、昇進すると自分の能力を超えるもの、あるいは自分の能力にないものを求められる可能性がある。だから、無能になってしまう。
これがピーターの法則だが、そうであるならシンプルな方法があるとすぐに気づけるだろう。
「昇進を断って、自分が有能にこなせる仕事を楽しくやっていればいいんでしょう」
打診された昇進をきっぱり断ることは、「ピーターの受け流し」という名で知られています。簡単なようですが、私はこの成功例をたった一つしか見つけられないでいます。(P.196)
その例として挙げられるのが、大工のT・ソーヤーの事例だ。仕事熱心で腕が立ち、良心的でもあったので、雇われていた建設会社から「親方にならないか」と何度も声をかけられた。上司を尊敬していたので、彼の喜ぶ顔を見たいとも思った。
しかしソーヤーは、一介の大工として幸せを感じていた。毎日午後4時半になれば仕事のことを忘れられたのだ。
親方になれば、夜も翌日のことを心配し、週末になっても翌週のことで頭を悩ますことがわかっていた。だから、昇進を一貫して断り続けた。
ただ、それはソーヤーが独身で、近親者もおらず、友人もほとんどいなかったからだと著者は記す。自分のやりたいようにやれる環境があったのだ。
大半の人にとって、「ピーターの受け直し」は簡単にできるものではないのである。家族がいれば、当然、反対される可能性が高い。
では、どうすればいいのか。見事に目標を達成していた人がいた。書類をなくしがちな園芸職人、仕事部屋がぐちゃぐちゃな工場の監督、給与小切手がなかなか換金されない教師の3人の実例から、著者は読み取る。無能の偽装だ。
しかし、一つだけはっきりしていることがあります。
彼らは昇進を拒否するのではなく(中略)初めから昇進の話を持ちかけられないように工夫することによって、上のポストに登るのを避けてきたということです!(P.202)
だから、3人は昇進せずに済んでいたのだ。昇進をせずに済んだからこそ、ピーターの法則に倣って無能にならずに済んだ。
仕事においても、私生活においても、健康と幸福を手に入れるための秘訣。それは、こうした「創造的無能」だというのである。
職務の遂行に支障をきたさない無能ぶりを示す
創造的無能こそ、無敵の処世術だと著者は記す。
最終的な昇進の回避が意識的だったかどうかは、どうでもいい。そうすることによって、自分を無能にすることから解き放たれるのだ。
終点到達者に現れる症状(病気以外の症状)を一つか二つ、外に向けて示すことで、これを実行できます。(P.203)
例えば、先の園芸職人は、軽度の「書類恐怖症」がみられた。工場の監督は、「書類溺愛症」が進行していた。教師は小切手換金ができなかった。しかし、職務の遂行には、支障をきたしていない。
つまり、その程度の無能を選ぶことによって、創造的無能を演出できるということだ。
事務職員なら、退社する際に机の引き出しを開けっぱなしにしておく。倹約の大切さを説きながら照明を消して回る。ちょっとした変人になるのだ。また、一匹狼になるのも効果的だという。
外見を演出するのも方法だ。人は見た目で判断しているからである。型破りな服や擦り切れた服を着る、髪を伸ばし放題にする、髭を剃り残す。
そこまでしてでも、創造的無能に挑んだほうがいいと著者は語る。
なぜなら、ピーターの法則によって無能になることは、それ以上にしんどいことだから。ただ、創造的無能には注意点がある。
カムフラージュする方法として、ときおり職場でこんなことをつぶやいてみるのもいいでしょう。
「おかしいなあ。出世する人間と、取り残される人間って、いったい何が違うんだろう?」(P.208)
まず、今の仕事とは無関係なところで無能を探してみるといいという。
それを見つけたら、コツコツと実践してみる。そうすれば、自分にしかわからない満足感が得られる。そして著者はこうも記す。
創造的無能を手に入れることは、昇進願望を果たすのと同じくらい大きなチャレンジだと。
「ピーターの法則」は、仕事観を大いに揺さぶられる。それでも、組織で働く人間は知っておいて損はないだろう。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。