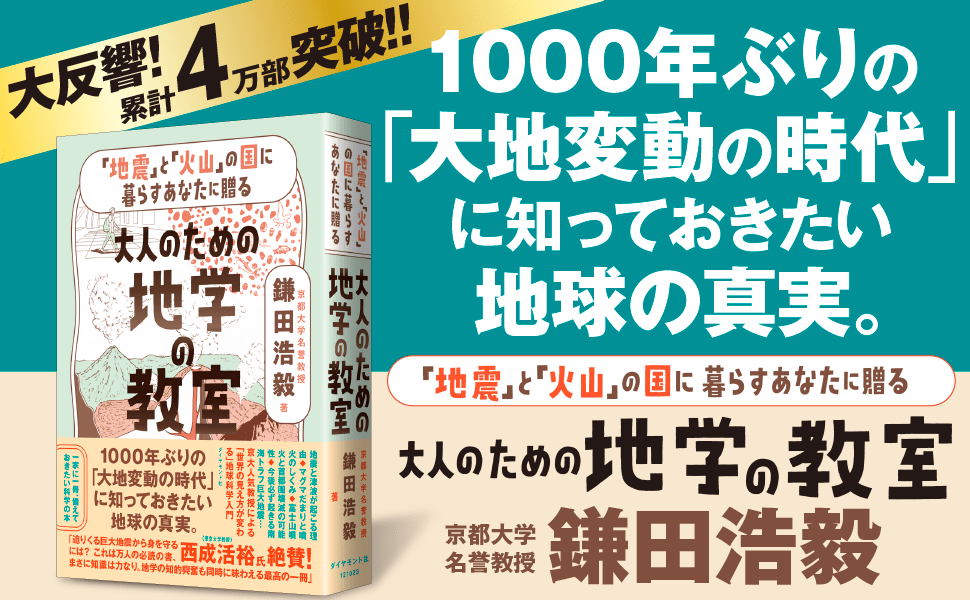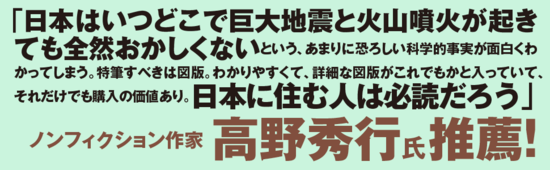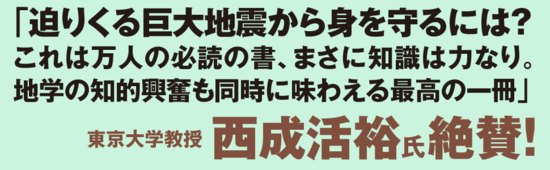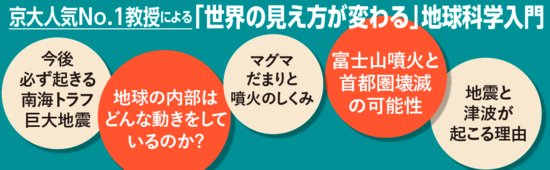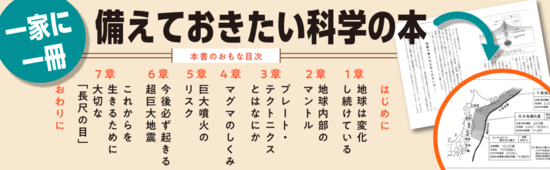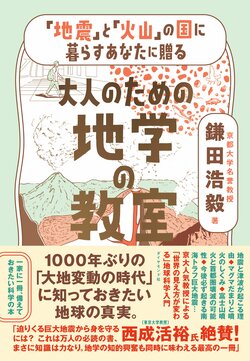東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
溶岩流と火砕流
火山の噴火のニュースで火砕流とか溶岩流といった言葉を聞いたことがあると思います。
ちょっとややこしいので、ここで整理しておきましょうか。
マグマがそのまま液体として火口から横に流れ出ると「溶岩流」で、それが冷えて固まると溶岩になります。それで四方八方にマグマをまき散らす現象を「火砕流」と言います。
さらにマグマが空中に飛び出して冷えて固まり、バラバラになって降ってくるのが「火山灰」です。
つまり火砕流と火山灰は似たもので、火砕流は数百メートルぐらい上がって、熱を保ったまま流れ出したもの。火山灰は火砕流よりも高く、たとえば3万メートルぐらいまで上がって上空で冷やされて風に乗って飛ばされていくもの、ということです。
あとは火山灰に似たものに「火山弾」があるけれど、その二つは構成成分などの基本的な要素は同じで、バラバラの度合いが低い、つまり粒が大きいと火山弾になります。
それと噴火にともなって飛ばされるものとしては「噴石」もあって、これは火口付近にある古い岩石を飛ばす現象、あるいはその吹き飛ばされた岩石です。
火山弾も噴石も時速100キロメートルを軽く超える高速で飛んできます。
火砕流の温度は?
なお、火砕流はとても高温です。マグマはもともと1000度ぐらいでしょう。火砕流はなかで熱を保っていて600~800度なんですね。
さらに巨大な火砕流、たとえば阿蘇山の火砕流は880度もあるんです。1000度から100度ぐらいしか下がらない。
1991年に噴火した雲仙普賢岳の火砕流は600度ぐらいで、これは実測してわかりました。600度だから人間を含めてすべての生物は生きられない高温で、それが一気に流れ下った。
それに火砕流が流れる速度はとても速くて、最大で時速100キロメートル。ただ、これは推定で、実際にそこまで大きな噴火の火砕流の速度を測定した例はありません。
1991年の雲仙普賢岳の噴火でヘリコプターで測定したのは時速60キロメートルぐらいだけど、それは規模が小さかった。
過去の阿蘇山や鹿児島湾の火砕流はもっと大きいから多分、時速100キロメートルぐらいということで、車でも逃げられません。
それと火砕流は周りの空気やもともと含んでいた水分の影響で「粉体流」になります。粉体流は火山にまつわる用語ではなくて、気体と固体の微粒子からなる流れのことで、これは流体力学や工学ではおなじみの現象です。
九州の北半分を焼け野原にした火砕流
まとめると、温度は600度以上で、時速は100キロメートル、物理的な挙動としては乱流からなる粉体流だから、火砕流はとても危険ですよね。
細かいところは抜きにして、これまで日本列島で起きた噴火の様子を紹介すると、たとえば鹿児島湾から出た入戸火砕流は南九州全域を覆いました。
それから阿蘇山から出た阿蘇4火砕流は九州の北半分全域を焼け野原にしただけではなく、なんと海を渡って本州の山口県までいったことがあります。
ちなみに、阿蘇4のように火山の名前のあとに数字が入るのは、阿蘇から出た火砕流の4番目という意味です。
これは火山学の一般的な表記なのですが、阿蘇では阿蘇1火砕流から阿蘇4火砕流まであります。
また、鹿児島湾の噴火で火山灰は東北地方まで飛んでいるし、阿蘇山の噴火で北海道まで飛んでいった実例もあります。
さらに、それらとは別に「火山ガス」も出るんです。火山ガスについては、マグマには水が5パーセントぐらい含まれているから、まず、それが水蒸気になって出る。
それに火山ガスには、水蒸気のほかに硫黄やフッ素や塩素など、人間にとっては有害な物質がどの火山でも0.1から数パーセントは含まれているんですよね。
たとえば安達太良山とか草津白根火山などの温泉にいくと、硫黄の臭いがするでしょう。
それはマグマに硫黄が入っているから。ということで、火山の噴火は周辺に住む人にとってとにかく大変なことなんです。
参考資料:【京大名誉教授が教える、富士山が噴火する日】大量の溶岩で新幹線や東名高速は分断、火山灰で首都圏のライフラインが止まり、被害総額は2兆5000億円、3000万人が被災する…
(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)
京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授
1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。