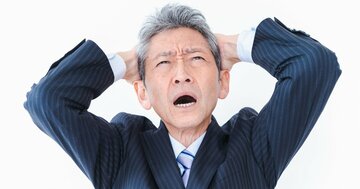要注意!「相続開始前3年以内の贈与」は
相続税の対象に
無知 でも、生前贈与は保険や小規模宅地等の特例よりは優先度が低いんですよね? 注意点を教えてください。
前田 はい。まずは「相続開始前3年以内の生前贈与は、相続税の対象になる」というルールがあります。
「今からじゃ遅い」は本当?
孫への贈与ならセーフの可能性も
前田 ですから、「お父さんが余命1年だから、相続税対策のために生前贈与してもらおう」と思っても時すでに遅し。たとえ年間110万円以内の生前贈与をしていたとしても、それが相続開始前3年以内に行われたのであれば、相続税がかかります。ただし、このルールの対象となるのは、「相続」または遺言で財産を贈る「遺贈」により財産をもらった人です。
適用対象とならない人で、一番わかりやすいのは孫です。孫は相続人でないため、死亡保険を除けば、相続で何かもらうことは基本的にはありません。そのため、孫に遺言書で財産をのこさないのであれば、相続開始直前の生前贈与であっても、相続税の対象となることはないのです。
2024年からは「7年ルール」へ!
生前贈与の難易度がアップ
無知 まあ、普通は相続人に生前贈与をするでしょうけど、そのときは亡くなる3年より前に贈与をしておけばいいということですね。
前田 実は法改正があって、2024年1月以降の生前贈与については、相続開始前7年以内の生前贈与が相続税の対象になります。
新ルールの適用タイミングに注意!
2027年相続発生から本格適用
前田 ということは、家族が亡くなる時期を予測したうえで、その7年より前に生前贈与をしないといけません。ただし、新ルールは2024年1月以降の贈与だけが対象となるため、2023年中の贈与は現行ルールでの適用となります。少しわかりづらいですが、新ルールの適用については、相続発生日が2027年1月以降になると1年ずつ相続税の対象となる生前贈与の期間が延びていくことになります。
どういうことかというと、たとえば2023年12月と2024年1月に110万円ずつ贈与し、相続発生が2027年2月の場合、新ルールは2024年以降の贈与から適用となるため、2024年1月の110万円だけが相続税の対象となるわけです。
特例制度でピンチを回避!
非課税で贈与できる方法とは?
国税 これまでの3年以内のルールが7年以内に延びると、かなりインパクトがありそうですね。
無知 僕の両親は、これから7年もたつと、ともに90代。日本人の平均寿命からすると、もう生前贈与で相続税対策をするのは難しそうです。
前田 そのような問題を回避する方法がいくつかあります。まずは、贈与税の特例を使うという方法です。
贈与税の特例を活用しよう!
「非課税」で贈与するための制度
前田 贈与税には「住宅取得等資金贈与の特例」や「贈与税の配偶者控除」という特例があります。これらの特例を使って生前贈与をすれば、年間110万円以上を贈与しても非課税になりますし、たとえ相続開始の直前に贈与が行われていたとしても、相続税を計算するときに加算されません。
注意!専用口座に残ったお金は相続税の対象に
国税 贈与税には「教育資金一括贈与の特例」や「結婚・子育て資金の特例」もありますが、これらについてはどうでしょう?
前田 教育資金一括贈与の特例は、いったん贈与者である親が、信託銀行などの金融機関で専用口座の契約をして、まとまったお金を預けておいて、受贈者となる子どもや孫が教育費を支払うときに限り、専用口座から非課税でお金を引き出せる仕組みです。
結婚・子育て資金の特例も基本的な仕組みは同じで、決められた目的に沿って資金を専用口座から引き出せば、贈与税が非課税になります。ただ、これらの専用口座にお金が残っている状態で贈与者である親が亡くなると、その残額は相続税の対象になります。教育資金一括贈与の特例については、受贈者である子どもや孫の年齢などの状況によっては専用口座に残額があっても相続税に影響しないのですが、あくまで例外的なケースです。
国税 住宅取得等資金贈与の特例や配偶者控除なら、そういう複雑な問題を考えなくてもいいわけですね。
贈与税の特例一覧:
非課税での生前贈与を実現するために
✓ 配偶者控除…「おしどり贈与」とも呼ばれており、婚姻期間20年以上の夫婦限定で利用できる。夫または妻へ居住用不動産等を贈与する場合、2000万円まで非課税。
✓ 住宅取得等資金贈与…取得する住宅の要件により非課税枠が異なる。500万円(省エネ等住宅の場合は1000万円)まで非課税(2026年12月31日まで)。
✓ 結婚・子育て資金一括贈与…18~50歳未満の子どもや孫に対して適用される。1000万円まで非課税(2025年3月31日まで。ただし、2年間延長予定)。
✓ 教育資金一括贈与…0~30歳未満の子どもや孫に対する贈与に適用される。1500万円まで非課税(2026年3月31日まで)。
生前の相続税対策は何ができる? … 生前贈与~法改正で7年持ち戻しに
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。