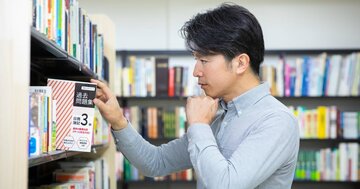完全に排除することはできないが
ゴマすりを少なくする努力で組織は変わる
 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
人間社会には古来、「権力者に取り入る」ことで地位や利益を得る人々が存在してきた。王侯貴族の時代であれ、近代企業社会であれ、ゴマすりの構造は大きく変わらない。これは人間関係が本質的に感情や心理に左右されるものである以上、完全に避けようがない側面ともいえる。
だからこそ、それによる腐敗を防ごうと、組織では、ゴマすりの影響力を最小限に抑え、本当に実力や成果を上げた人間が正当に評価される土壌を育もうと努力しなければならない。
数字や事実に基づいた目標設定と評価を行うことで、上司の主観が評価に与える影響を可能な限り減らそうとしたり、いわゆる「360度評価」のように、一人の上司だけではなく同僚や他部署の責任者など、複数の視点から総合的に評価を行う方法をとったりするなど、ゴマすりだけでは高評価が得にくくなるような仕組みづくりがすでに進められていることだろう。
しかしながら、実際の現場でゴマすりを完全に排除することはできない。
組織にできることは、ゴマすりの出現率を少しでも下げること、ゴマをする人をできるだけ出世させないことくらいだ。心もとないと思われるかもしれない。しかし、その「多少なりとも下げる」べく努力するかどうかという一点が、組織全体の健全性や優秀な人材の流出防止に大きく寄与し、企業価値の向上に直結すると考えられる。
太古から変わらないゴマすりと、自然と生まれる「かわいがってもらう」という関係性。そのいずれもが人間社会の一面を反映しているだろう。企業や組織が生き残りをかけて競争する現代において、本当の意味で価値を生み出すのはどちらのアプローチか。答えは明白である。
(プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社 代表取締役 秋山 進、構成/ライター 奥田由意)