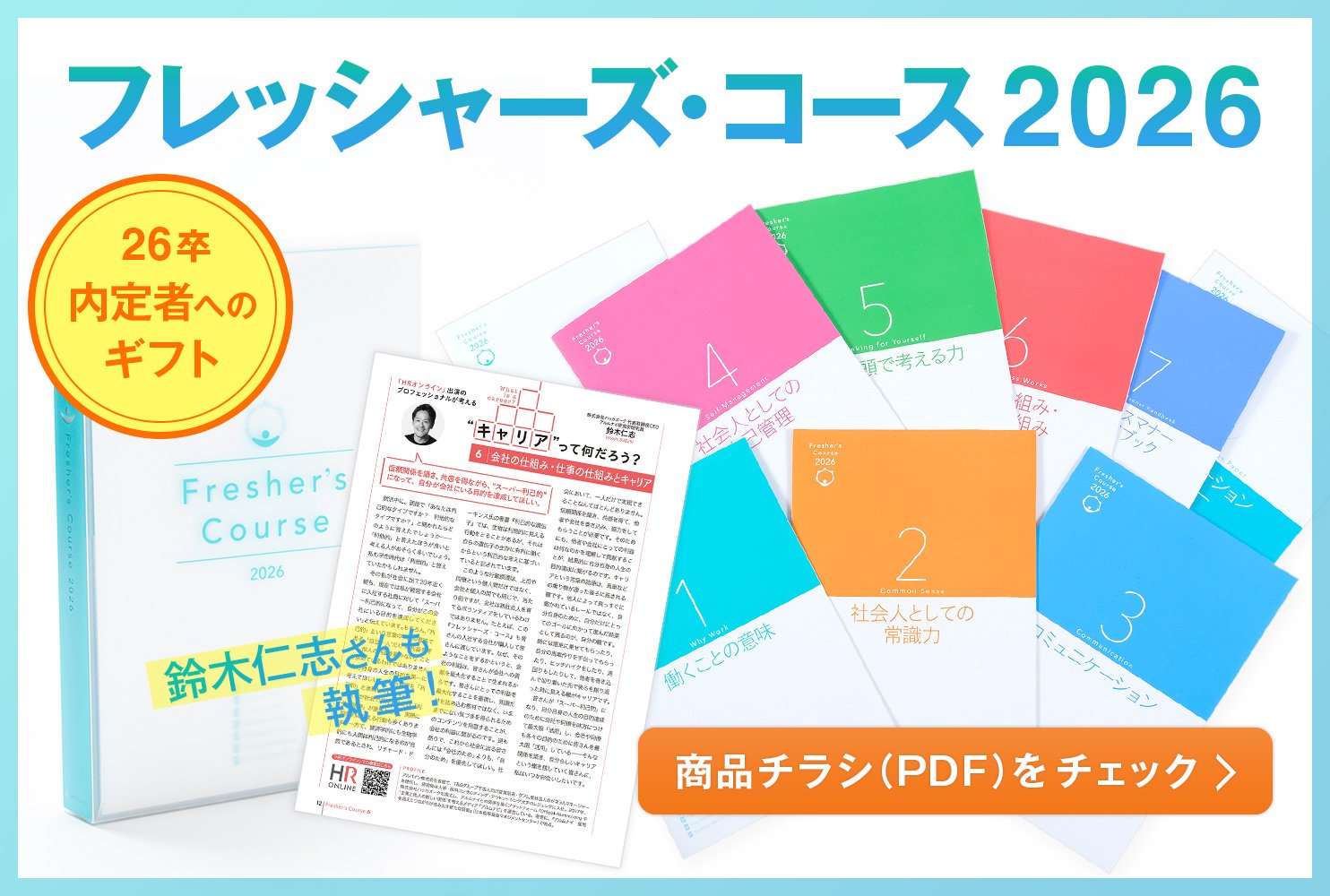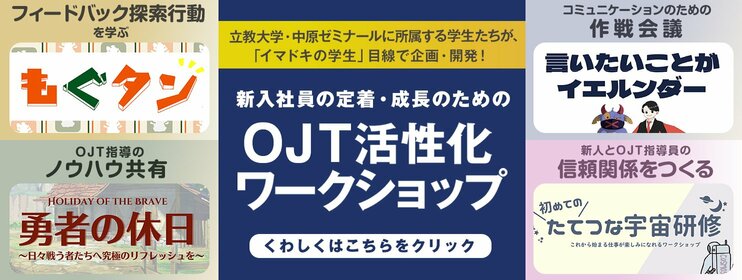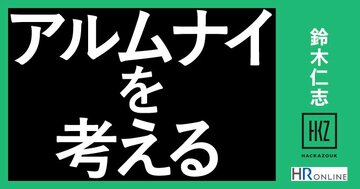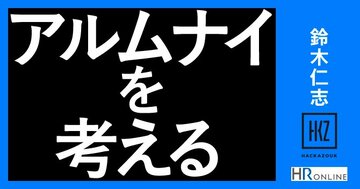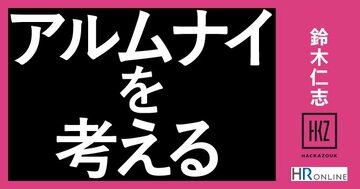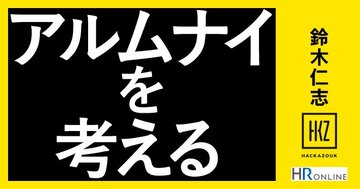「再雇用」だけではない、関係構築の広がりが大切
導入から1年。A社では、次のような取り組みを継続しています。
●年2回の全体イベント
●小規模な対面/オンラインイベントの定期開催
●コンテンツ配信(月数回)
●新規登録時および定期のインタビュー・アンケート調査
●アルムナイ間や現社員とのマッチング支援
そして、実際に、次のような成果が生まれています。
●複数名の再入社
●複数名との業務委託契約
●アルムナイが勤務する企業との販売代理店契約
●アルムナイが勤務する企業のサービス導入
A社のアルムナイの取り組みは社内でも表彰を受け、いまでは他部門から「アルムナイに相談したい」「こういう人材はいないか?」といった問い合わせが来るようになりました。来年度からは、予算や運営リソースの一部を他部署でも分担する方向で検討が進んでいるとのことです。
とはいえ、このようにスムーズに立て直せる企業ばかりではありません。A社のアルムナイの中にも、「どうせ、安く再雇用することが目的なんでしょう? 方針が変わっても、もう関わる気はない」という厳しい声もありました。最初に採用だけを目的に設計してしまったことで、アルムナイからの企業に対する信頼を失ったのです。最初の印象を変えるには時間がかかりますし、やり直しにはコストもかかります。
アルムナイとのつながりを「採用手段のひとつ」としてのみ捉えるのか、それとも「人的資本や社会関係資本」として位置づけるのか。
アルムナイとのつながりが「人的資本や社会関係資本」となるような関係性を選ぶには、他部署を巻き込む覚悟や、経営層の理解が必要になるでしょう。しかし、最初の一歩を誤ることで、築けたはずの関係を失ってしまうリスクもあるのです。
どのような形でアルムナイとの関係を始めるのか。その設計は、今後の企業の人材戦略全体にも大きな影響を与えるはずです。