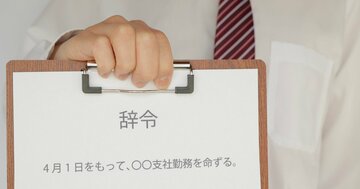ビジネス環境や働き方が大きく変化する中、働く現場では「人と組織」をめぐる課題が複雑化している。近年では、個人の学習・変化を促す「人材開発」とともに、「組織開発」というアプローチが話題になっており、『いちばんやさしい「組織開発」のはじめ方』(中村和彦監修・解説、早瀬信、高橋妙子、瀬山暁夫著)のような入門書も刊行された。今回は、こうした「人と組織のあいだに渦巻くモヤモヤ」に正面から切り込んだ話題作『冒険する組織のつくりかた 「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』の著者であり、気鋭の組織づくりコンサルファームMIMIGURI代表でもある安斎勇樹さんに、「プレイヤーとして優秀だった人が、マネジャーとしてつまずく理由」について話を伺った。(企画:ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
“自分が”活躍したい管理職
――プレイヤーとして成果を出してきたものの、マネジャーに昇進してからどうもしっくりこない。そんな人には、どんな共通点があるのでしょうか?「管理職に向いていない人」の特徴について教えてください。
安斎勇樹(以下、安斎) まず前提として、管理職というのは、部下の育成や自己実現に向き合いながら、チームとして成果を出していく役割です。その意味では、「自己犠牲的」とまではいかないにせよ、「他者のために動ける人」がマネジャーに向いていると思います。
そのうえで「向いていない人」がいるとすれば、まず1つ目は、“承認欲求が強すぎる人”です。
自分の手柄を示したい、自分を褒めてほしいという気持ちが先に立ってしまうタイプ。こういう人は、個人の成果を重視しすぎてチーム全体の成果を見られなくなってしまうんですよね。
ただし、これは「出世欲が強い人」とも言えるので、経営層から評価されるという意味では出世していく可能性は高い。だけど、チームで人を育てたり、チーム全体で成果を上げるという観点では、マネジャーとしては向いていないと思います。
ビジョン過剰・こだわり強すぎ問題
安斎 2つ目は、“ビジョンが強すぎる人”。
自分の「こうしたい、ああしたい」が強くて、コントロール志向が強いタイプですね。これは一見リーダーシップがあるように見えるけれど、最初のフロントラインのマネジメントでは扱いづらい。
ある程度の調整や周囲との協調が必要とされるポジションにおいては、そうした強いエゴが邪魔になることがあります。
「自分でやったほうが早い病」
安斎 3つ目は、“職人気質の人”。
細部にこだわりすぎるタイプです。自分でやったほうが早いと思ってしまったり、人に任せられない。ディテールへのこだわりが強すぎると、マネジメントの仕事においては障害になることがあります。
こうしてみると、マネジメントに向いていない人というのは、ある意味「自己中心的な人」と言えるかもしれません。
逆に、最初のフロントラインマネジメントをうまくやれる人って、自分が褒められたいわけでもなく、ビジョンを押しつけたいわけでもなく、細部にこだわりすぎることもない。
むしろ、調整役として周囲と成果を出していけるような、ある種「自分を引っ込められる人」だと思います。