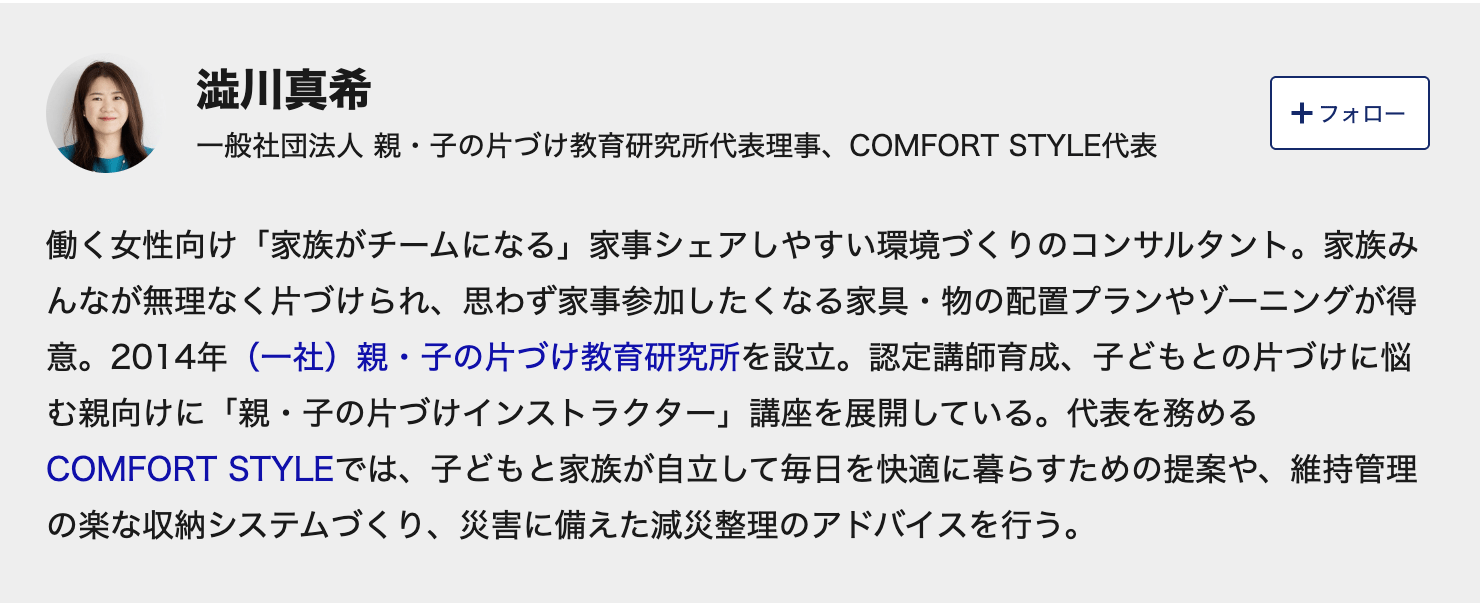お風呂タイムを“お世話”から
“ルーティン”へ変える仕組み
汚れの程度が軽いうちは洗剤を使わなくても、汚れは落とせます。ブラシでこすったり、クロスで水拭きしたりするだけでOK。洗剤を使わないのでお子さんにお手伝いしてもらうのもいいでしょう。
とにかく汚れを溜めないことが、掃除を面倒にしない一番の秘訣です。そのためには掃除のタイミングも決めてルーティンに組み込みましょう。
私が講師を務めるお掃除スペシャリスト講座では、自分のおうちに合わせた掃除のスケジュールをつくることができるので、自分ひとりで考えるのが大変な方はこうした講座を活用するのも一つの手です。
そして、掃除グッズは「隠さず使いやすく」。見せても違和感のないシンプルなデザインのアイテムを選び、使う場所にそのまま置いておくのが習慣化への近道です。
特に未就園児や園児がいるご家庭では、「お風呂=子どものお世話の時間」というイメージが強いかもしれません。でも、子どもが「自分でできること」が増える仕組みを整えると、親の負担はグッと減ります。
おすすめは、パジャマ・下着・タオルをセットにして子どもが自分で取り出せるようにすること。ラベリングしたボックスにセットしておけば、入浴前の「準備して〜」が不要になります。
お風呂場の中で使う、子ども用のボディソープやおもちゃなどを一箇所にまとめ、トレーやバスケットなどを使って定位置を作りましょう。おもちゃは洗面所に置いておいて、必要なものを選んで持って入り、出るときに一緒に持って上がれば、カビたりすることも減り、使ったあとはお片づけ、という習慣も身につきます。
「今日はこのタオルにしようっと!」「このおもちゃとお風呂に入る!」
そんな風に、子どもが自分で選ぶ楽しさを感じられると、お風呂の時間が自然と前向きなものになり、“やらされる”から“楽しみになる”へと変わっていきます。
仕組み化で、毎日がラクに回る
だから時間にも心にも余裕が生まれる
水まわりが整うと、朝の準備から寝る前の支度までが驚くほどスムーズになります。
・子どもが自分で支度できるようになり、親の声かけが減る
・掃除が習慣化され、いつでもキレイをキープできる
・家族で家事をシェアしやすくなる
水まわりは毎日使う場所だからこそ、使いやすく・片づけやすく・掃除しやすい工夫が大切です。小さな仕組みの積み重ねが、共働き家庭の暮らしをぐっとラクにしてくれます。
まずは、洗面所の棚ひとつから見直してみませんか? 明日の朝が、ちょっとスムーズになる第一歩になるかもしれません。
最新記事がメールで届くので、読み逃しがなくなります。