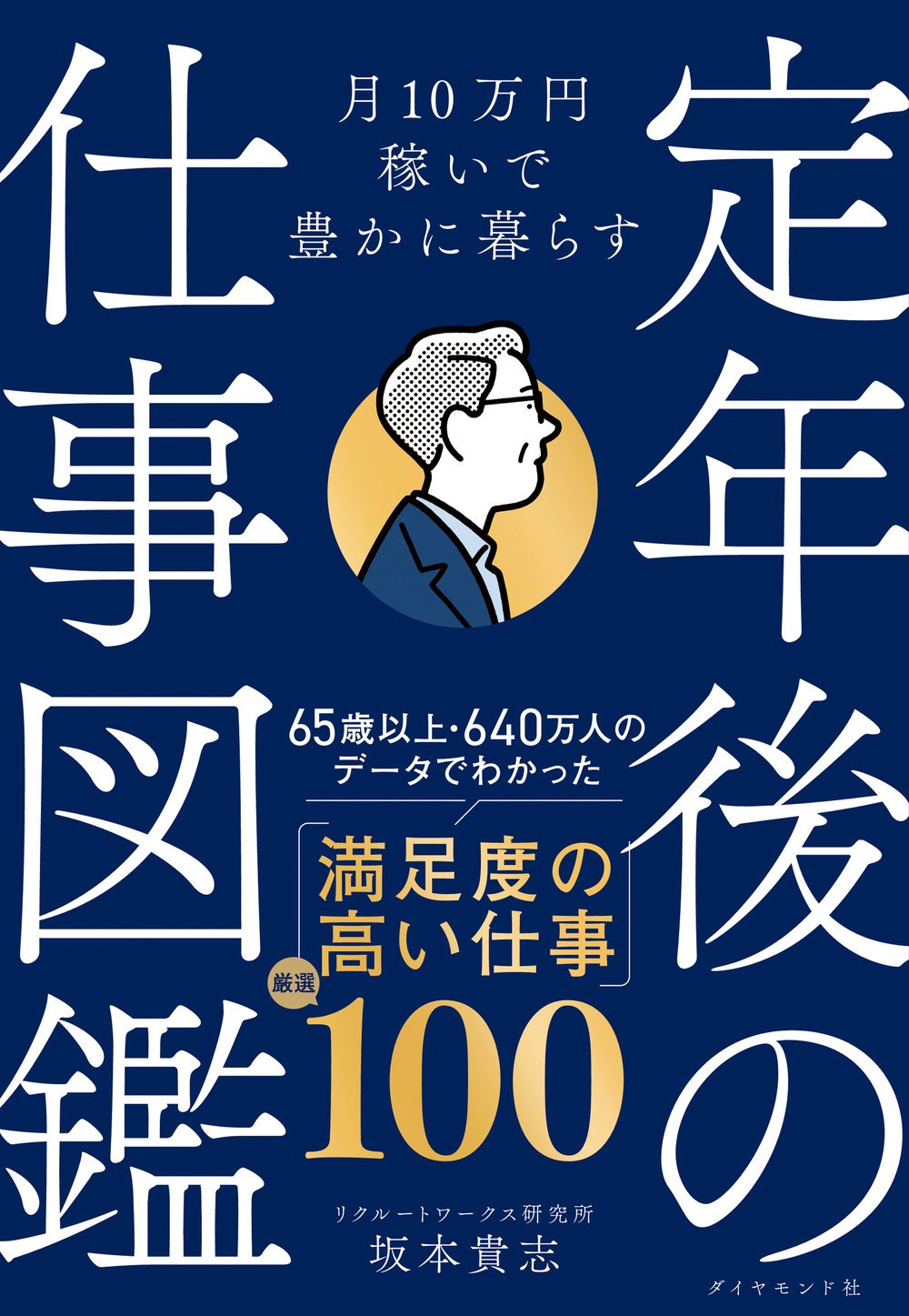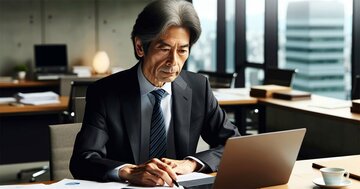「60歳以降の仕事人生にも、ガイドが必要だ」――そう語るのは、リクルートワークス研究所の坂本貴志さん。高齢期の就労・賃金を専門とする坂本さんが、65歳以上・640万人のデータを分析し、まとめた書籍が『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』です。
定年退職=引退だった時代は終わり、いまや「定年後の仕事探し」を自分自身で行う時代がやってきました。本書では、実際に働いている人のデータを参照しながら、19カテゴリ、100種類の仕事を紹介。現役時代とは全く違う仕事選びのコツについても解説しています。この連載では、本書より一部を抜粋・編集して掲載します。今回は、実際に定年後の仕事をしている方のインタビューを掲載します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
定年後のキャリアは「現役時代の延長線上」で考えない
「定年後の仕事」を考えるうえで大事なことは、仕事のキャリアを「新卒~定年後まで」の一本道で考えないことだ。
定年後の仕事は、必ずしも現役時代の延長上にはない。本書で紹介している「小さな仕事」にスムーズに移行するためには、仕事人生を「3つのステージ」に分けて考える必要がある。
❶若年~中堅期
新入社員から50歳くらいまで。スキルアップしながら組織内で昇進・昇格し、それによって高い収入を得ることにモチベーションを求める時期。
❷中高年期
50~60代半ばまで。まだまだ稼ぐ必要があるものの、組織内の立場で限界が見え、気力・体力の面で変化がある。公的年金支給が始まる65歳まである意味もうひと踏ん張りの時期。
❸高齢期
60代半ば以降。この時期に入ると年金の支給が始まり、子どもも独立して家計支出が減少する。
60代半ばまでは「過去の経験を活かした仕事」の満足度が高い
3つの世代のうち、若年期~中堅期と高齢期のつなぎ目である「中高年期」の時期にどのような選択をするかはその後の定年後の人生を大きく左右する。
この時期にどのようなキャリアを選ぶと、人生の満足度につながるのだろうか。本書で紹介しているリクルートワークス研究所の大規模調査では、60代前半・後半の「正社員として継続して働く人」「再雇用されて働く人」「転職した人」で満足度を比べた。分析の結果、60代前半に関しては同じ会社で働き続けている人の満足度が高いことがわかったのだ。
一方、定年前(56~60歳)と定年後(61~65歳)を比較すると、全体平均で2割程度年収が下がっている現実がある。収入水準が下がるのは、定年後の再雇用に伴う報酬水準の引き下げや、ポストオフによる年収ダウンによるもの。
なお、企業規模別にみると、中小企業では定年後の収入の減少幅は11.5%であるが、大企業の減少幅は27.6%となっている。中小企業と比べて、大企業では定年後に収入が大幅減となるケースが多い。年収は大幅に下がるものの、満足度は相対的に高いということは、「多少年収や役職が下がったとしても、60代半ば頃までは基本的にはこれまでの仕事の経験を活かして働き続ける」という選択肢が結果的には満足感につながるということだ。
定年後継続雇用は批判的な論調で扱われることも多いが、データからは決して間違った選択なわけではないとわかる。
そう考えれば、多くの人にとっては、60代半ばまではこれまでの仕事で継続して成果を出しつつ、それ以降に第2部で紹介するような仕事に移行するという戦略が、中高年期から高齢期にかけてのキャリアの最適な戦略になると考えられる。
これは家計の観点でみても同様である。定年後に年収が下がるといっても、多くの人にとって継続雇用期間の収入を上回る条件の求人を探すことは決して簡単なことではない。また、65歳までは現役時代と同じ会社で働き、厚生年金を会社に負担してもらうことで、その後の年金額を増やすというメリットも大きい。