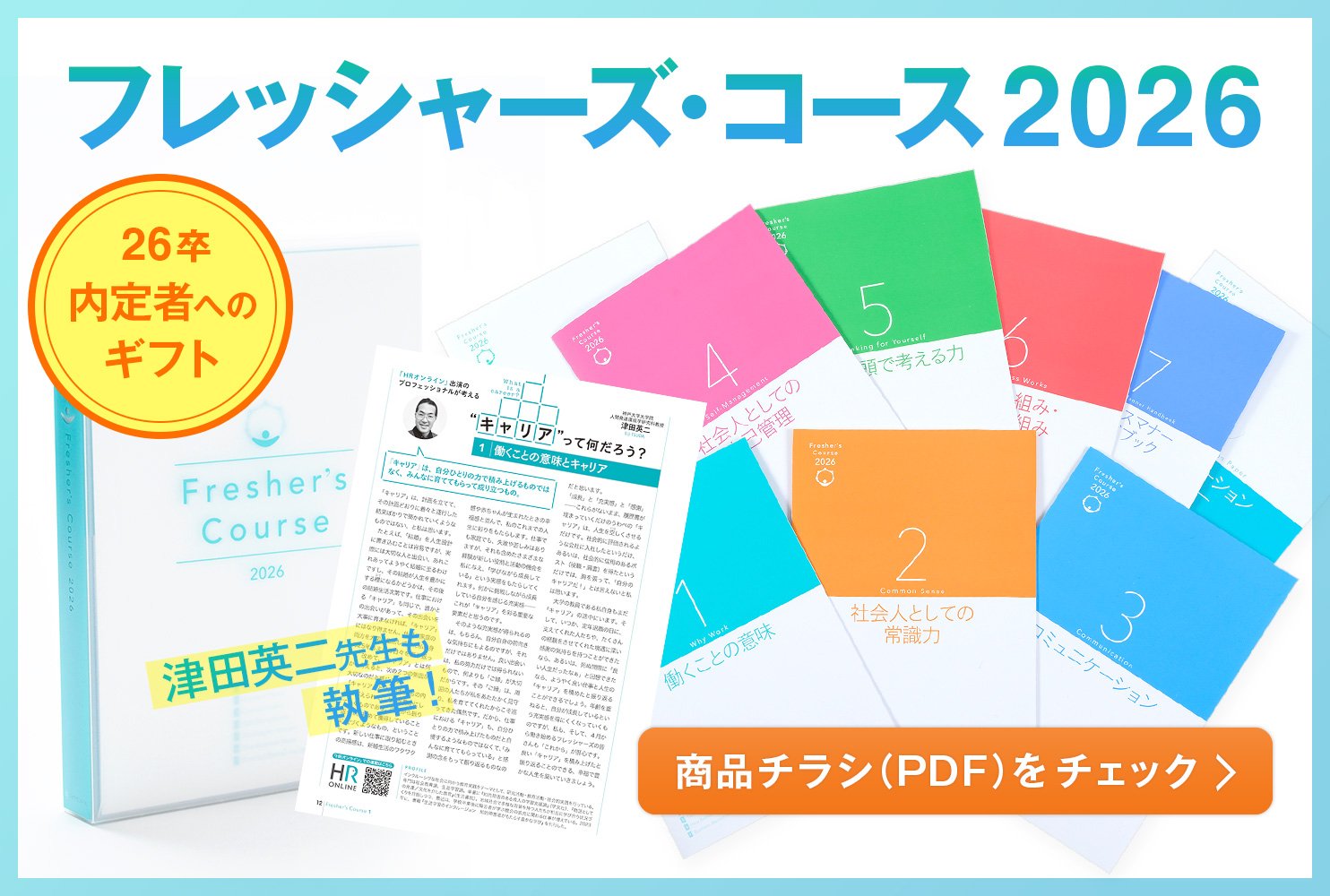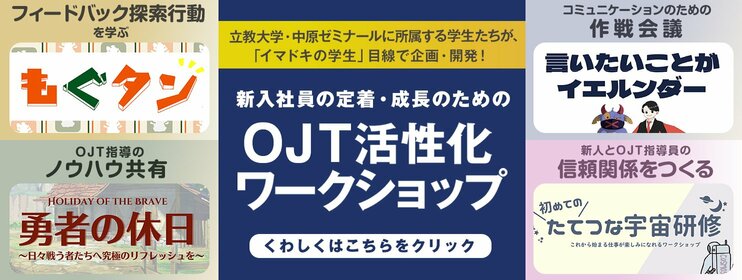元留学生の活躍が日本の社会を切り開いていく
多くの場合、外国人留学生が留学を決意する動機は、日本での学習や生活への憧れといった「惹きつけ要因」と、母国において居心地の悪さを感じていたり、日常に物足りなさを感じていたり……といった「押し出し要因」とが重なっているように思う。
留学の動機は、どこの国の若者でも直面する「アイデンティティの模索」という一面をもっている。「自分が何者であるのか?」ということに迷い悩むのは、日本人の学生でも同じである。それゆえに、朱さんがそうであったように、文化や言葉の壁を越えて、留学先の日本でも同じ若者どうしで意気投合するということが起こり得るのだと思う。そして、留学中に自分が大切にして生きていきたい何かを見つけて、力強く巣立っていく。朱さんは、その過程を鮮明に語ってくれた。
私自身がこれまで深く関わった外国人留学生のほとんどが、修士論文を書くことを目的に入学してきた大学院生だった。大学院の外国人留学生の多くは、母国の大学を卒業後に来日し、研究生として、日本語や専門の勉強を1~2年重ね、大学院入試を受験して大学院生となる。その後、2年間で修士論文を書き上げて修了していく。
例えば、修了後に日本の大手小売業に就職し、母国の支店で店長として活躍している修了生がいる。この修了生は、留学時代の留学生仲間と結婚して子どもを育て、家族全員で神戸に遊びに来て、私と酒を酌み交わしながら近況を語ってくれる。また、結婚や出産を経て、苦労しながら博士論文まで書き上げ、修了後も日本に残って子育てをしながら障がい者福祉の業界で活躍している修了生もいる。この春、修士論文を書き上げて修了していった外国人留学生は、大学院の授業や研究フィールドでの出会いなどを通して、母国の学校で受けたスパルタ教育の傷を癒やし、自由に幸福を追求することの価値を学んだ。この留学生は、日本での学びを続けるかどうかに最後まで悩んでいたが、最終的には、就職活動をするために母国に帰っていった。
どの留学生も、苦労しながら懸命に生き、成長しようとしている礼儀正しい若者たちである。それぞれの道で活躍するこうした若者たちが、国境を超えたグローバルな社会の未来をつくっていく。
そして、大学院を修了した外国人留学生が日本で就職するケースの増加を、私は実感している。「日本に住み続けたい」と考える外国人留学生が増加したということと、日本企業の外国人留学生登用に障壁が少なくなってきたことが、その要因だと思う。いずれの要因も、日本社会が多様性を受け入れるようになってきた証左と言えるだろう。
外国人留学生にも多様性があることは言うまでもない。文化や言葉の壁に苦しんで、日本社会への適応に苦労する留学生も多いだろう。私の目から見ると、外国人留学生も日本人の学生と同じように、「自分がどう生きていくか?」ということに悩み、模索を続けた学生生活を経て、人のため、社会のためになることのできる自分を探す若者である。
悩みながら、自分を高めようと努力している若者は、国籍・文化・ジェンダー・性別・障がいの有無にかかわらず、輝いている。
企業の人事担当者のみなさんは、外国人留学生の動向を百も承知に違いないが、採用活動においては、外国人留学生が「日本で悩みながら成長してきたこと」に光を当てて、彼ら彼女たちの入社後のやる気に火をつけていただけたらと思う。
挿画/ソノダナオミ