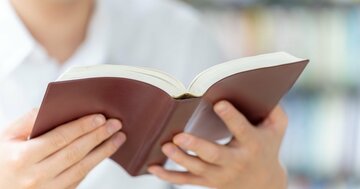「株主優待」と聞くと、多くの方がビールやお菓子、レストランの割引券など、ちょっと得をする特典を思い浮かべるのではないでしょうか。日本では当たり前のように存在するこの制度ですが、改めて考えてみると不思議です。なぜ企業は、わざわざコストと手間をかけてまで、株主に“モノ”を配るのでしょうか。
この素朴な疑問から本格的な研究を始めたのが、『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』の著者で投資銀行と米系コンサルを経て大学教授へと転身した異色の経歴を持つ宮川壽夫氏(大阪公立大学大学院経営学研究科・商学部教授、昭和女子大学グローバルビジネス学部客員教授)と、宮川氏の筑波大学大学院時代の師であり、日本のコーポレートファイナンス研究をけん引してきた南山大学教授の伊藤彰敏氏です。本対談では、株主優待の本質や、データから見えてきた驚きの事実、そして今後の優待の進化について語っていただきました。普段何気なく受け取っている「優待」の裏側にある企業戦略を、ぜひ知っていただければと思います。
(第4回/全4回)(構成/森遥香)
南山大学 経営学部 教授
東京大学経済学部卒、慶應義塾大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)でMBA取得、ウェスターン・オンタリオ大学Ph.D.(経営学博士)。国際大学国際経営学研究科助教授、レジャイナ大学(カナダ)助教授、筑波大学准教授、一橋大学大学院経営管理研究科 教授を経て現職。2014年FMA Asian Conference共同実行委員長を務める。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
株主優待の謎:ファイナンス理論の「辺境」
――株主優待について、単刀直入にお聞きします。優待を出している企業の株は、結局のところ「買い」なのでしょうか?
宮川壽夫氏(以下、宮川):その問いに直接答えるのは難しいのですが(笑)、我々の研究アプローチは「株を買うと儲かるか」というより、もっと基本的な、「なぜ株主優待制度なんてものがあるのか」という問いからスタートしています。研究が本格化したきっかけは、10年以上前になりますか、伊藤先生との雑談の中で、ふと優待の話題になったことです。
伊藤彰敏氏(以下、伊藤):そうでしたね。私が「そもそも、なんで企業って優待なんてやるんですかね?」と問いかけた。それが全ての始まりであり、我々の株主優待に関する研究アプローチの根幹です。
宮川:ちょうど昨年から、日本証券業協会で「株主優待の意義に関する研究会」が発足し、私も伊藤先生も専門家として委員を務めることになりました。ただ、それ以前から、先生との対話の中で「なぜ企業はわざわざ優待なんてものをやるのか?」という疑問は深まっていました。配当なら現金を口座に振り込めば済む。だが株主優待は違います。品物を用意し、宛名を整理し、梱包して、配送するので、手間もコストもかかります。それでも多くの企業が優待を続けている。“わざわざそんな面倒なことをなぜ?”となることを深掘りしてみると面白いのではないかと考えたのです。
――言われてみれば不思議ですね。コストも手間もかかる上に、トラブルのリスクもある。それに見合うメリットがあるということでしょうか?
宮川:まさにそこがポイントです。そして、我々の研究の出発点として重要だったのは、この株主優待という現象が、既存の「配当理論では説明がつかない」という点でした。
伊藤:わからないことがあれば、当事者に聞けばいい。そこで、「どういうつもりでやっているのか」「目的は何なのか」を直接企業に聞きに行こう、ということになった。
宮川:ええ。夏の暑い日に、伊藤先生と二人で優待を導入している代表的な企業、何社も訪問してインタビューを重ねました。答えは本当に各社各様でしたが、そこから研究は具体的に動き出しました。その後、私の筑波大学時代の同級生である同志社大学の野瀬(義明)先生も加わり、3人で研究を進めています。