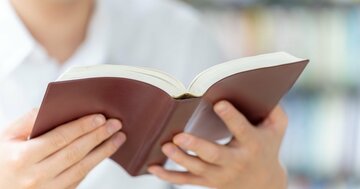企業経営において、ROE(自己資本利益率)や資本コストといった指標が重視される時代になりました。東証の改革以降、多くの日本企業が数値目標を掲げ、市場の期待に応えようとしています。しかし、その「数字」は本当に企業価値を正しく示しているのでしょうか。
今回対談したのは、『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』の著者で投資銀行と米系コンサルを経て大学教授へと転身した異色の経歴を持つ宮川壽夫氏(大阪公立大学大学院経営学研究科・商学部教授、昭和女子大学グローバルビジネス学部客員教授)と、宮川氏の筑波大学大学院時代の師であり、日本のコーポレートファイナンス研究をけん引してきた南山大学教授の伊藤彰敏氏。日本企業が大切にしてきた雇用の維持や企業文化、“見えない価値”をどう捉え、未来にどう活かすべきか。数値に隠れた本質を見抜くための視点を、ファイナンスの専門家が語ります。
(第3回/全4回)(構成/森遥香)
南山大学 経営学部 教授
東京大学経済学部卒、慶應義塾大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)でMBA取得、ウェスターン・オンタリオ大学Ph.D.(経営学博士)。国際大学国際経営学研究科助教授、レジャイナ大学(カナダ)助教授、筑波大学准教授、一橋大学大学院経営管理研究科 教授を経て現職。2014年FMA Asian Conference共同実行委員長を務める。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
投資家の視点と経営者の視点:ズレから生まれる課題
――配当政策を考える上で、投資家と経営者の視点の違いはどのように影響するのでしょうか?
伊藤彰敏氏(以下、伊藤):投資家は基本的に“いくらで買って、いくらで売るか”に関心があります。上場企業の株なら、短い場合には3ヵ月間で投資利益を生み出せればいいと考えてリターンを求めるのが彼らの立場です。一方で、経営者は20年、30年先を見据えて企業を経営しなければならない。この時間軸のズレは重要です。
宮川壽夫氏(以下、宮川):まさにその通りですね。実際、日本企業の経営者は市場のプレッシャーにさらされながらも、長期的な視点での経営を模索しています。短期的な株価やROEの数値にとらわれることなく、“可能性の束”をどう手に入れるかにもっと心を砕くのが優れた経営者です。20年後、30年後に企業がどう社会に貢献するか、そのビジョンを持つこと。具体的なルートは今決めなくていい。選択肢を広げ続けることが経営者にとって重要な役割の一つだと思います。
――企業経営は、どうしてもKPIや数値目標に縛られてしまう印象があります。お二人は今のそういう経営のあり方について、どう感じていますか?
宮川:最近、企業は東証の開示要請を受けて、ROEなどの数値目標を掲げています。「3年後にROE8%を目指す」といった数値目標にこだわった経営計画を発表する企業が増えていますが、僕はむしろそのことで投資家と企業の認識ギャップが広がっている気がしています。
多くの日本企業が「過剰に数値目標だけに縛られていないか?」という問題意識を持っています。確かに将来の計画を具体化することは必要ですが、ROEを何パーセントにする、という話ばかりしていると、「この会社がなぜ今の姿になったのか」という文脈が抜け落ちてしまうんです。
たとえば、企業が『自社の資本コストは6%なので、ROEは8%を目指します』と説明すると、投資家は『それでは低すぎる』『そもそも資本コストが過小評価では?』と言ってくる。すると、そこでもう議論の接点が見えなくなってしまいます。
単純化された財務指標を一律にクローズアップさせて経営を評価するのは非常に危険です。過去の成功には、環境や人材、文化といった“見えない要素”が複雑に絡み合っている。そこを無視すれば、将来の正しい意思決定もできなくなってしまう。
伊藤:そうですね。ROE8%という数字自体に意味があるわけじゃない。それをきっかけに、“どんな会社を目指すのか”を考えるべきなんです。数字はナビゲーション。目的地ではないんです。
投資家の多くは、高成長・高収益・高回転といったアメリカ型のモデルを前提にしています。一方で、日本の経営者は“持続可能性”や“社会との共生”といった価値を大切にしている。その前提が違えば、当然評価の軸もずれるのです。
つまり、アメリカでは成長の止まった企業は市場から早々に退出し、次のビジネスに置き換わる。しかし日本企業は、雇用の維持や地域社会との連携といった社会的役割を担っており、単純に効率や利益率だけで企業価値を測ることはできないのです。