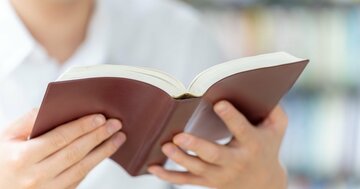なぜ、人は働くのか?――そう聞かれて、すぐに答えられる人は少ないかもしれません。生活のため、お金のため――そうした答えも間違いではありませんが、もし「企業の存在意義」から考え直してみたらどんな答えが導き出せるでしょうか。
今回は、発売当初から大きな話題を呼んでいる『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』の著者で、投資銀行と米系コンサルを経て大学教授へと転身した異色の経歴を持つ宮川壽夫氏(大阪公立大学大学院経営学研究科・商学部教授、昭和女子大学グローバルビジネス学部客員教授)と、宮川氏の筑波大学大学院時代の師であり、日本のコーポレートファイナンス研究をけん引してきた南山大学教授の伊藤彰敏氏に、「コーポレートファイナンスとはなにか?」を元に「働く意味」や「企業の役割」をゼロから解きほぐしていただきました。会社とは何か、なぜ組織が必要なのか、そして企業が生み出す“価値”とは何か。働くすべての人に関わる“根本的な問い”を、大学教授ならではの視点で語っていただきます。
(第2回/全4回)(構成/森遥香)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
コーポレートファイナンスから考える「企業」について
――今日はコーポレートファイナンスについて全くの初心者である私に、基本から教えていただきたいと思います。
宮川壽夫氏(以下、宮川):はい。大学生に最初に話す内容ですが、まず世の中にはビジネスのアイデアを持つ人がいます。そのアイデアを実現するためにお金が必要になり、そのお金を出す人、つまり投資家がいて、株式会社という仕組みが出来上がります。
株式会社は、まず資金を調達し、その資金を工場や設備などの資産に投資します。そして、その資産を使ってビジネスを行い、キャッシュ(現金)を生み出します。当然ながら、投資してもらったお金以上のキャッシュを生み出さなければ、企業が存在する意味はありません。
では、企業は「どのように資金を調達し」「どのようにそのお金を資産に投資するのか」、つまり「どこにどうお金を使うか」をどうやって意思決定するのでしょうか。さらに、投資した資産でビジネスを展開し、「競合とどう戦い、どうやってお金を増やしていくのか」。そして、「増やしたお金を次にどう配分するのか」。株主に還元するのか、あるいは更なる成長のために再投資するのか。経営者はその際、何を考えるのか――。
こうした株式会社の一連の活動フロー全体を見て、それを「企業価値」や「株主価値」という一つの物差しで評価していく。大まかに言えばこれがコーポレートファイナンスです。ビジネスや経営、株式会社の根幹に関わる全てを包含する、非常に発展性の高い学問分野と言えます。アイデア次第で、様々な方向に研究が広がる余地がありますね。
伊藤彰敏氏(以下、伊藤):では私からは、少し違う角度から、対話を通じて考えを深める形で進めてみましょうか。そもそも「企業価値」とは、企業があって初めて値段がつけられるものですよね。では、そもそも企業とは何のことなのでしょうか?
企業はなぜ「組織」として存在するのか
――企業とはある一つのゴール、例えば利益を追求するための集団のことでしょうか?
伊藤:「人の集まり」ですね。追求するものが利益かどうかはさておき、「組織」とは何か。人の集まり以外に特徴はありますか? メンバーは固定されていますか? それとも流動的ですか?
――メンバーは変わると思いますが、流動性はありつつも、そんなに頻繁には変わらないイメージです。
伊藤:そう、「組織」であるからには、ある程度メンバーは固定的ですよね。参加者、広げればステークホルダーが、ある程度「長い期間コミットする」。それが組織の特徴ではないでしょうか。では、組織と対比されるものは何か。組織の反対は?
――個人…でしょうか?
伊藤:個人でもいいですが、組織と同じような活動を、組織ではない形で行うとしたら? 企業は物を買い、人を集め、お金を集めて、物を作り、市場で販売する、という一連の活動を継続的に行っています。このためには、多くの人やお金が「長期間」その組織にコミットすることが不可欠です。
もし同じ活動を組織ではない方法でやるとしたら、プロジェクトベースで、その都度、人やお金を市場から調達することになるでしょう。メンバーは日々変わるかもしれない。でも企業が“組織”という形をとるのは、長期的に人や資源が関わることでしか生まれない価値があるからです。