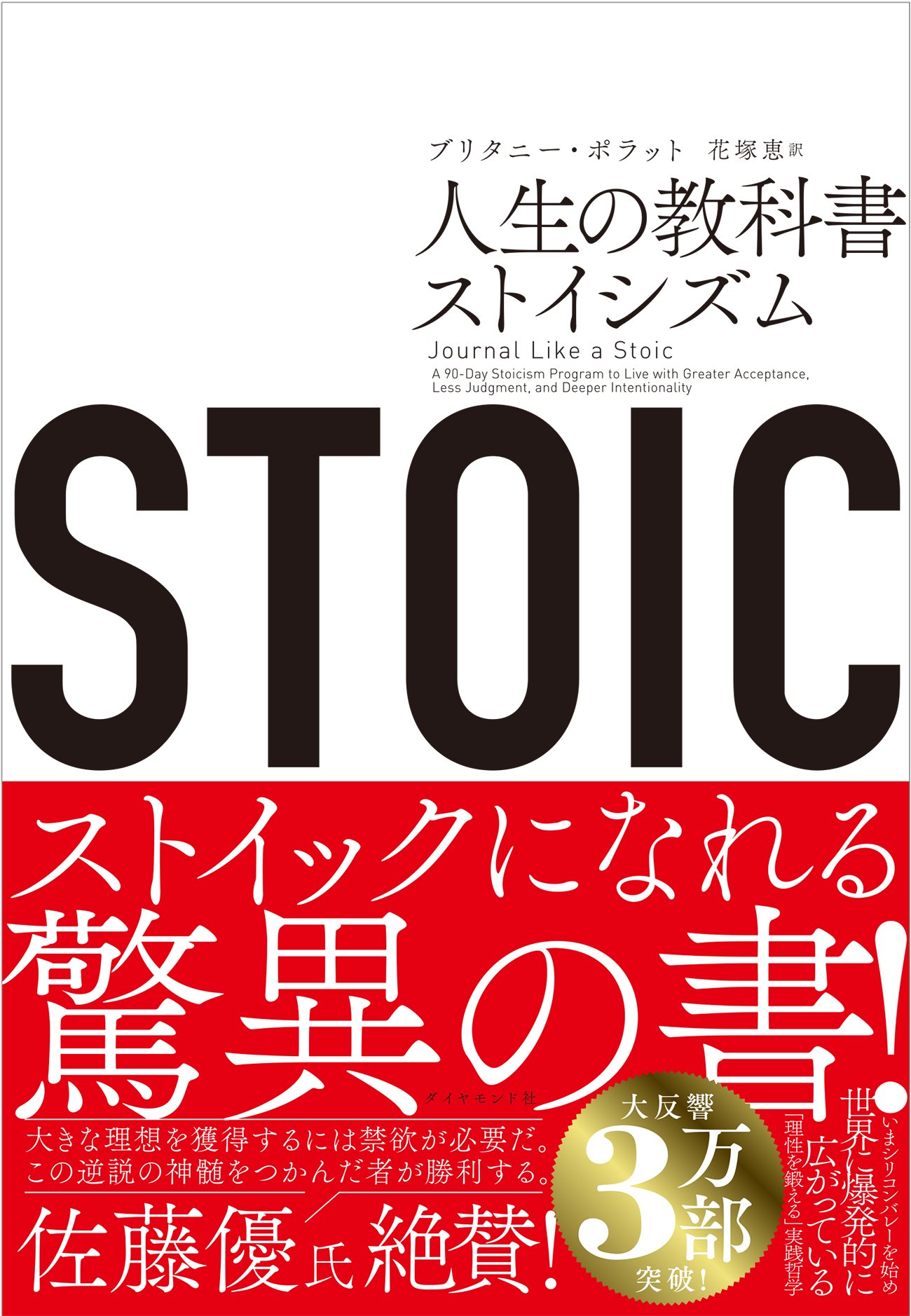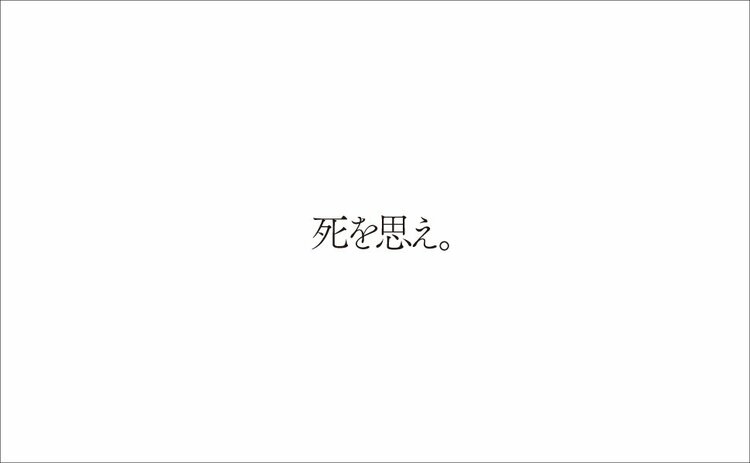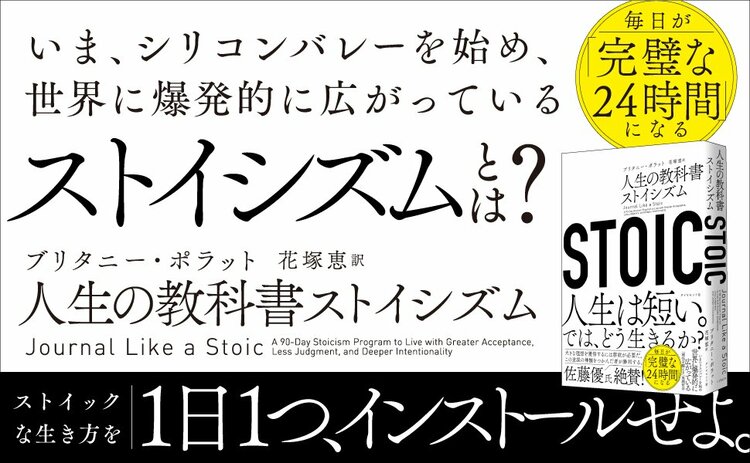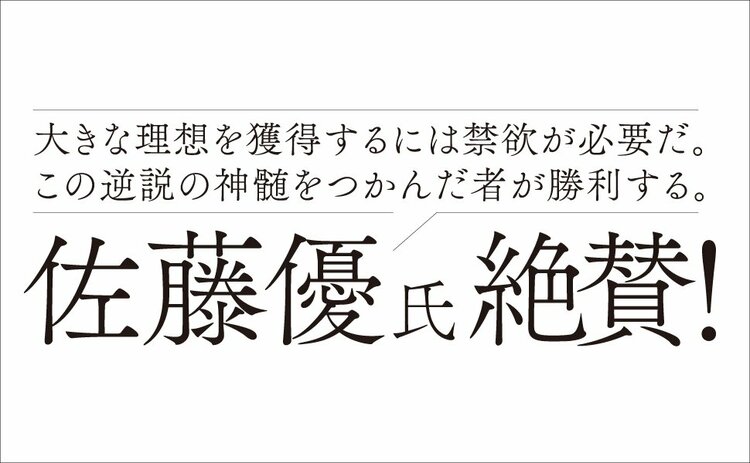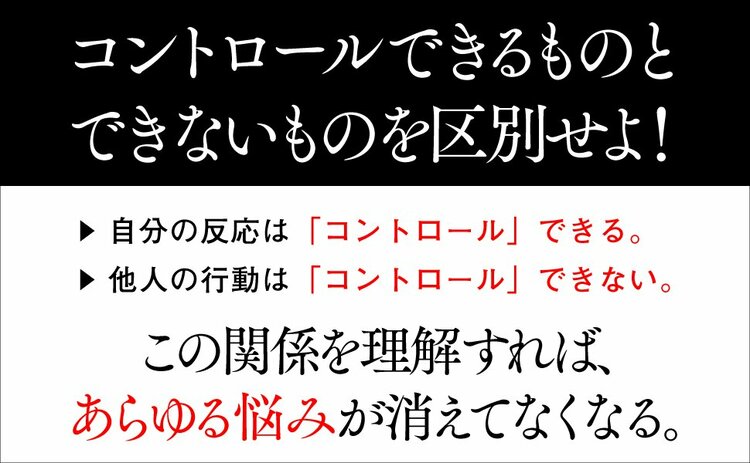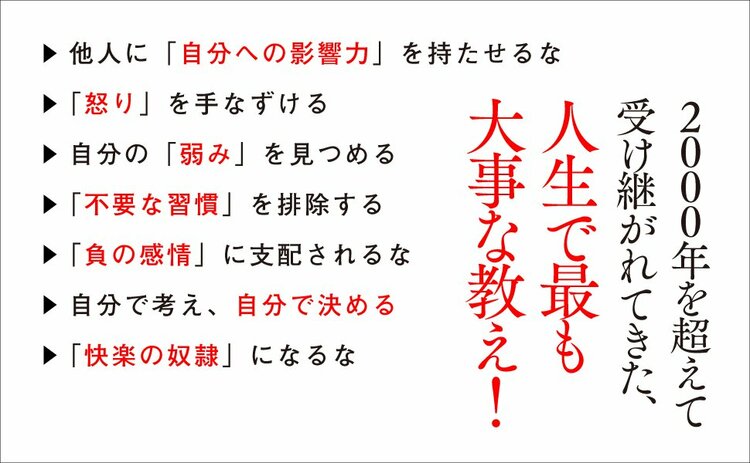いまシリコンバレーをはじめ、世界で「ストイシズム」の教えが爆発的に広がっている。日本でも、ストイックな生き方が身につく『STOIC 人生の教科書ストイシズム』(ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳)がついに刊行。佐藤優氏が「大きな理想を獲得するには禁欲が必要だ。この逆説の神髄をつかんだ者が勝利する」と評する一冊だ。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。(ダイヤモンド社書籍編集局)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
一触即発、ケンカの理由
ある児童施設の支援員から聞いた話だ。
小学4年生の男の子数人がケンカを始めたので、支援員は「どうしたの?」と声をかけた。
「こいつがウザイって言うから」
数人がAくんを指さす。Aくんは来たときから落ち着きがなく、イライラしたような様子があった。
「何がウザイの?」
Aくんはなかなか言葉が出てこなかったが、丁寧に聞いていくと、なんと「明日の遠足が楽しみで気持ちが落ち着かなかった」ということがわかった。ソワソワした気持ちをなんと表現していいかわからず、「ウザイ」という言葉になってしまっていたのだ。
支援員が話を聞くとAくんは落ち着き、ケンカもおさまったという。
私はこの話に驚き、感心もした。
Aくんの言葉や表現の未熟さに原因があったわけだが、私がそこにいたとしても、まさか「ウザイ」がまわりの子のことではなく、遠足に向けた気持ちだったなんて思いもよらなかっただろう。
支援員が丁寧に聞きとりをしなければわからなかったことだ。
とりあえず謝らせる?
私なら反射的に、「ウザイなんて言ったら傷つくよ。謝りなさい」などと言っておさめようとしたかもしれない。よくても、「どっちも悪いところがあるね」と言ってお互いに謝らせたかもしれない。
しかし、本当の気持ちを表現できないまま、とりあえず謝ることを繰り返していたら、子どもとしては不本意で、もやもやとした思いがつのるだろう。子ども同士でも遺恨が残ってしまうかもしれない。
Aくんのこのケースは、いい支援員がいてよかった。気持ちを解きほぐしてくれたことで、Aくんにとっても学びになったのではないだろうか。
ストア哲学者のエピクテトスは、「行動の背景を知るまでは褒めても責めてもいけない」と言っている。
行動の「背景」を見る
人がとる一つひとつの行動の背景にどのような判断があったかを知るまでは、褒めても責めてもいけない。(エピクテトス『語録』)
――『STOIC 人生の教科書ストイシズム』より
ストイシズムの知恵では、「疑わしきは罰せず」が推奨されているという。
一見、他人が悪い行動をしたように見えても、自分が知らないだけで、正当な理由があることはいくらでもある。
逆に、いい行動に見えるものでも、実は利己的な考えやよこしまな思いから行っている場合もある。
自分から見えているものは一部でしかないのだから、性急に「いい」とか「悪い」とか判断はできないのだ。
『STOIC 人生の教科書ストイシズム』によると、エピクテトスは大勢から尊敬を集めた教師だった。教え子たちのことも、すぐに褒めたり責めたりはしなかっただろう。行動の背景を見る目を持つことで、正しく人を見抜いていたに違いない。
私も、子育てにおいても人間関係においても、すぐに判断を下すのではなく、行動の背景に目を向けることを意識したいと思う。
(本原稿は、ブリタニー・ポラット著『STOIC 人生の教科書ストイシズム』〈花塚恵訳〉に関連した書き下ろし記事です)