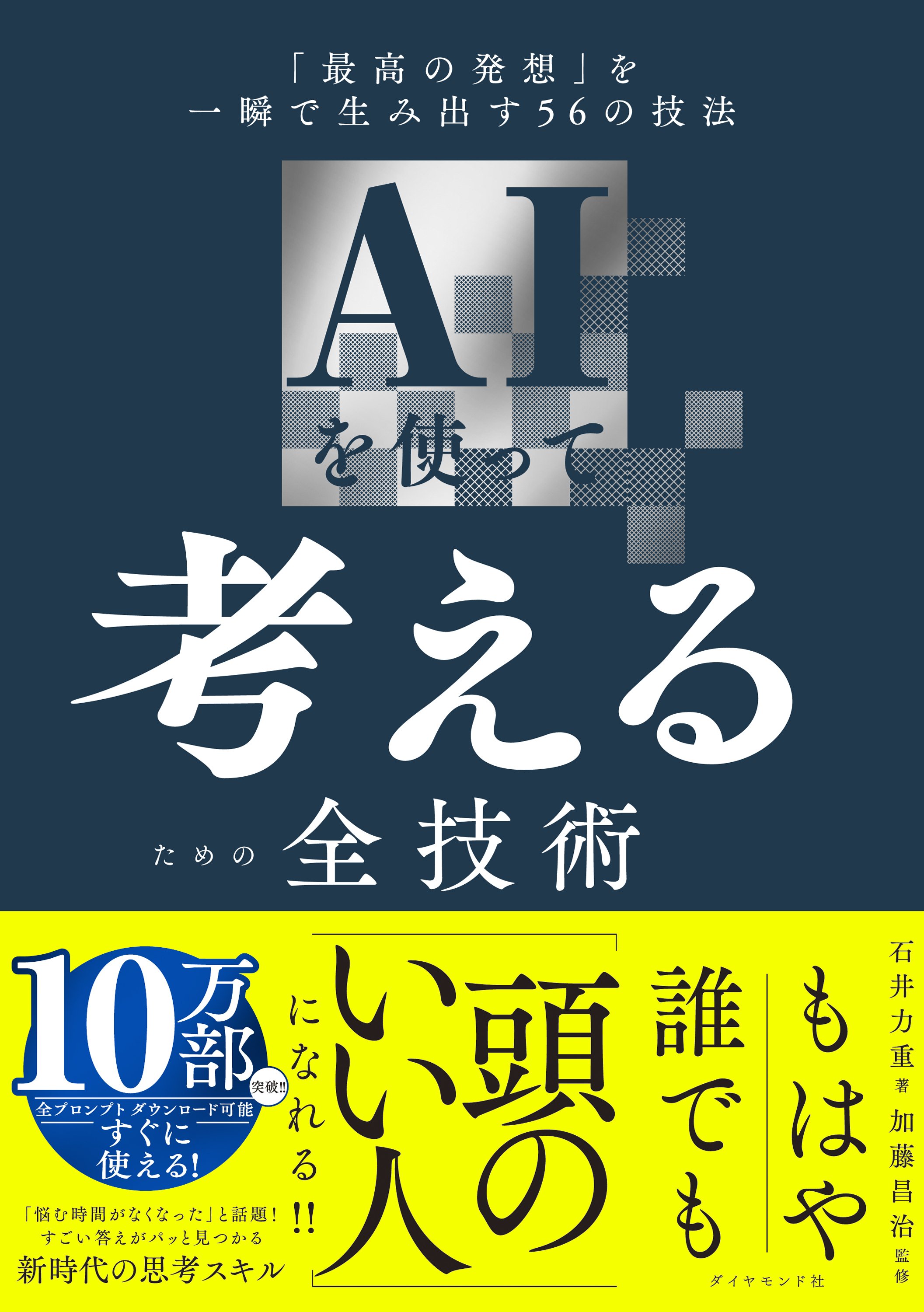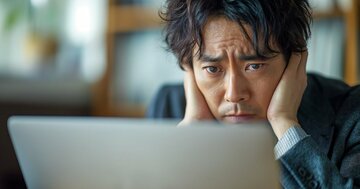「手に職をつけて、自分の力で食っていく」。そんなキャリア観が、AIの登場によって根底から揺らいでいる。あらゆる業務が一瞬で完了でき、誰もがコンテンツを無尽蔵に生み出せるようになった時代に、私たち人間はキャリアにおいてどのような生存戦略をとるべきなのだろうか。
AIを「思考や発想」に活用するための書籍『AIを使って考えるための全技術』の発売を記念して、起業家であり、「やりたいことが見つからない人」に向けてキャリア設計を説いた書籍『物語思考』の著者でもあるけんすう(古川健介)さんに「AI時代のキャリア戦略」について話を聞いた(ダイヤモンド社書籍編集局)。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
これから先、人類は「馬」になる
――これから先、AIによって人類はどうなっていくと思いますか?
5年後とか10年後、量子コンピューターが実用化されると、今まで何十年もかかっていたようなノーベル賞級の発見が「5分に1回」ぐらいのペースで出てくるようになるらしいんです。そうなると、たぶん人間の認知が追いつかなくなる。
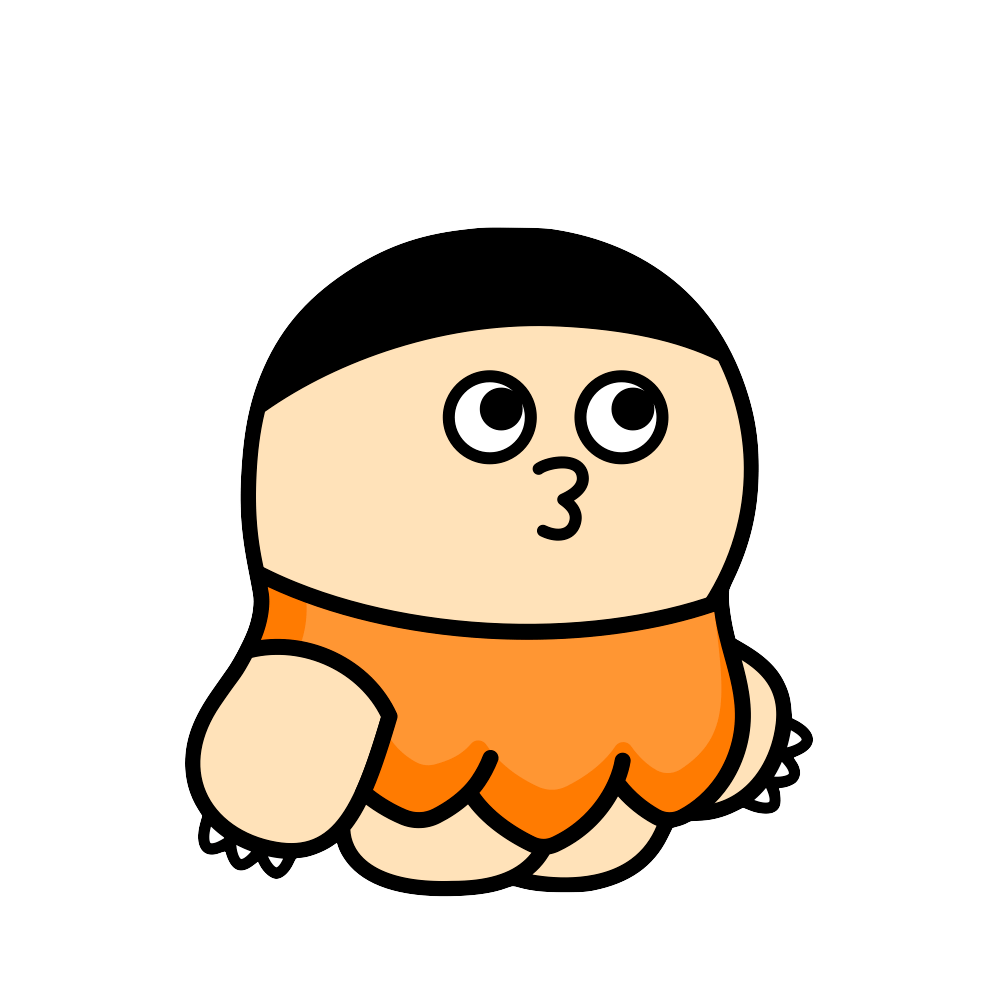
けんすう(古川健介)
アル株式会社代表取締役
学生時代からインターネットサービスに携わり、2006年株式会社リクルートに入社。新規事業担当を経て、2009年に株式会社ロケットスタート(のちの株式会社nanapi)を創業。2014年にKDDIグループにジョインし、Supership株式会社取締役に就任。2018年から現職。会員制ビジネスメディア「アル開発室」において、ほぼ毎日記事を投稿中。
X:https://x.com/kensuu
note:https://kensuu.com
アメリカの誰か有名な人が言ってたんですけど、「人間は馬のようになるだろう」と。馬って、自分に値段がついていることも、その理由もわからない。なんで輸送されてるのか、なんで走らされてるのか、“わからない”まま動いてる。
これと同じように人間も、「わからない」ままにAIからの指示で動くようになると思います。
たとえば「この会議が終わったら、トイレに行く前にいったん手を洗ってください」とか。「なぜそうするのか」はよくわからないけど、AIに言われたから「なんとなくそうなのかな」と思って従う。そんな自由意志のない世界になっていくんじゃないでしょうか。
すでに我々の自由意志はあやふやだ
でも、じつは今もあまり変わらないのかもしれません。
たとえば、「なんで今、自分は電車に乗って会社に向かっているんだろう?」って、ちゃんと説明できる人ってあまりいないと思うんです。「行かないと給料がもらえないから」だと思いますけど、じゃあ「なんで自宅勤務じゃダメなのか?」って聞かれると、あいまいな答えしか出てこない。
「よくわからないけど、会社や上司に言われてるから従っている」だけとも言える。仕組みがわからなくても、人間は動けてしまいますからね。
これからは、その“上司”や“会社”のさらに上位存在としてAIが来るようになる。そんな未来になると思うんです。
「判断」はAIに、「決断」は人間が
なのでそもそも、「判断」という行為はなくなっていくと思います。
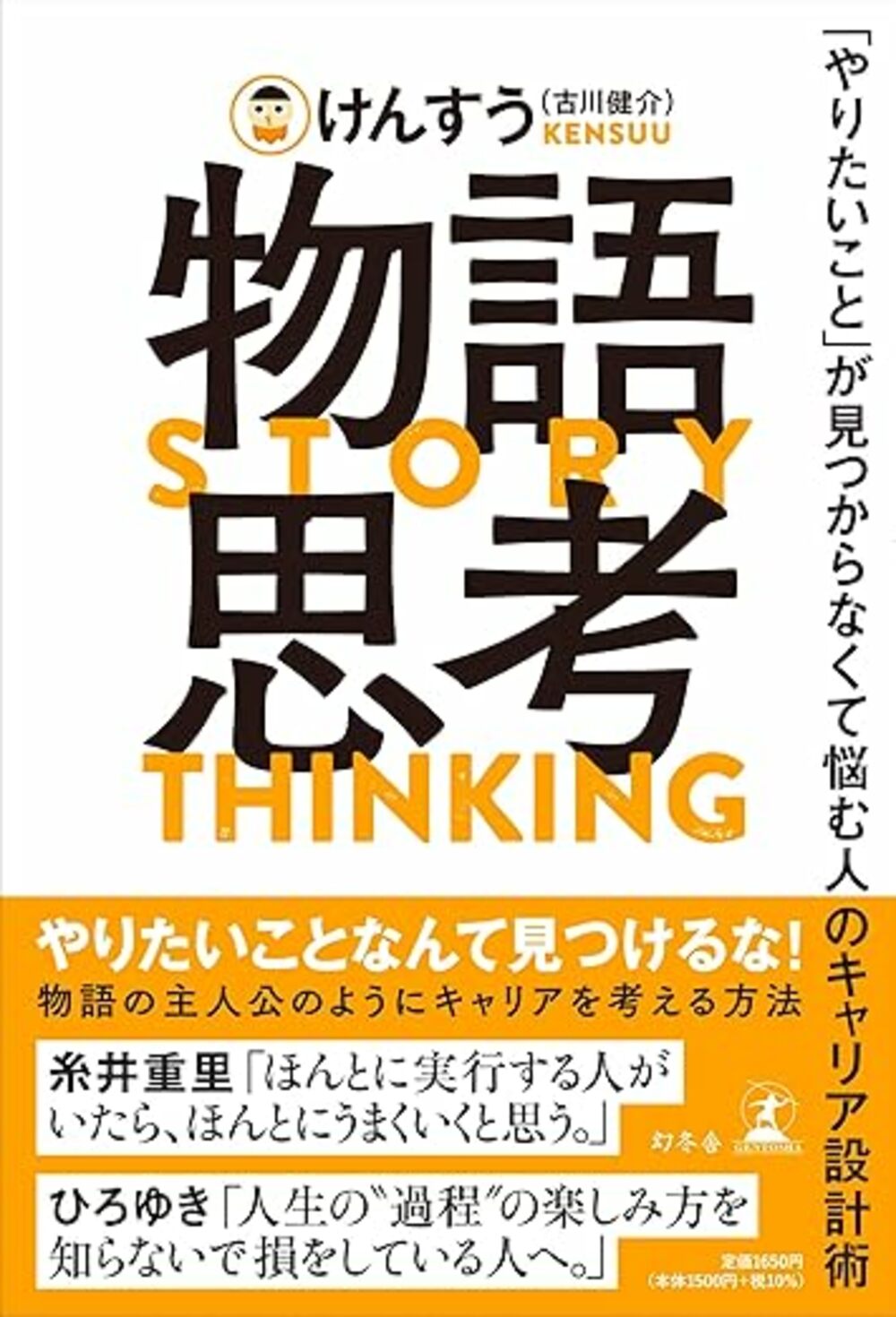 『物語思考 ー「やりたいこと」が見つからなくて悩む人のキャリア設計術』
『物語思考 ー「やりたいこと」が見つからなくて悩む人のキャリア設計術』けんすう(古川健介)著、260ページ、幻冬舎
判断とは、情報を集めてメリット・デメリットを整理し、最適な選択肢を選ぶことですよね。でも、それってAIの方が圧倒的に得意なんです。
じゃあ、人間がやるべきことは何かって言うと、「決断」だと思っています。
たとえば、「会社を辞めるべきか、続けるべきか」って、いくら情報を集めても明確な答えが出ないですよね。どっちもメリット・デメリットがあるし、未来は予測できない。だから、最後は「えいやっ」と決めるしかない。
なのでこれからは「それは判断すべきことなのか? 決断すべきことなのか?」を見極めることが大事です。
論理的に判断すべき場面で直感的に決めてしまったり、逆に、決断すべきところで延々と悩み続けて判断しようとすると、結果的に意思決定を誤ります。
「合理的判断が必要なこと」はAIに聞いてさっさと正解を選ぶ。一方で、「答えのない問い」はAIを使ってリスクや条件を整理したうえで自信と責任を持って自分で決断する。この使い分けが、これからのAI時代における賢い人間のあり方だと思っています。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』に関連したインタビュー記事です。書籍では、AIを賢く使って問題解決するための56の方法を紹介しています)