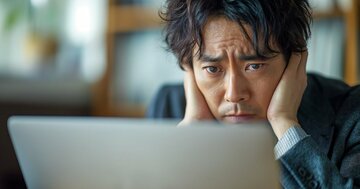「手に職をつけて、自分の力で食っていく」。そんなキャリア観が、AIの登場によって根底から揺らいでいる。あらゆる業務が一瞬で完了でき、誰もがコンテンツを無尽蔵に生み出せるようになった時代に、私たち人間はキャリアにおいてどのような生存戦略をとるべきなのだろうか。
AIを「思考や発想」に活用するための書籍『AIを使って考えるための全技術』の発売を記念して、起業家であり、「やりたいことが見つからない人」に向けてキャリア設計を説いた書籍『物語思考』の著者でもあるけんすう(古川健介)さんに「AI時代のキャリア戦略」について話を聞いた(ダイヤモンド社書籍編集局)。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
AIを使って他人の人生を「小説」にする
――けんすうさんご自身の、ちょっと変わったAIの使い方ってありますか?
そうですね、『物語思考』でも書いたんですけど、「自分の人生を物語にする」って大事なんですよね。
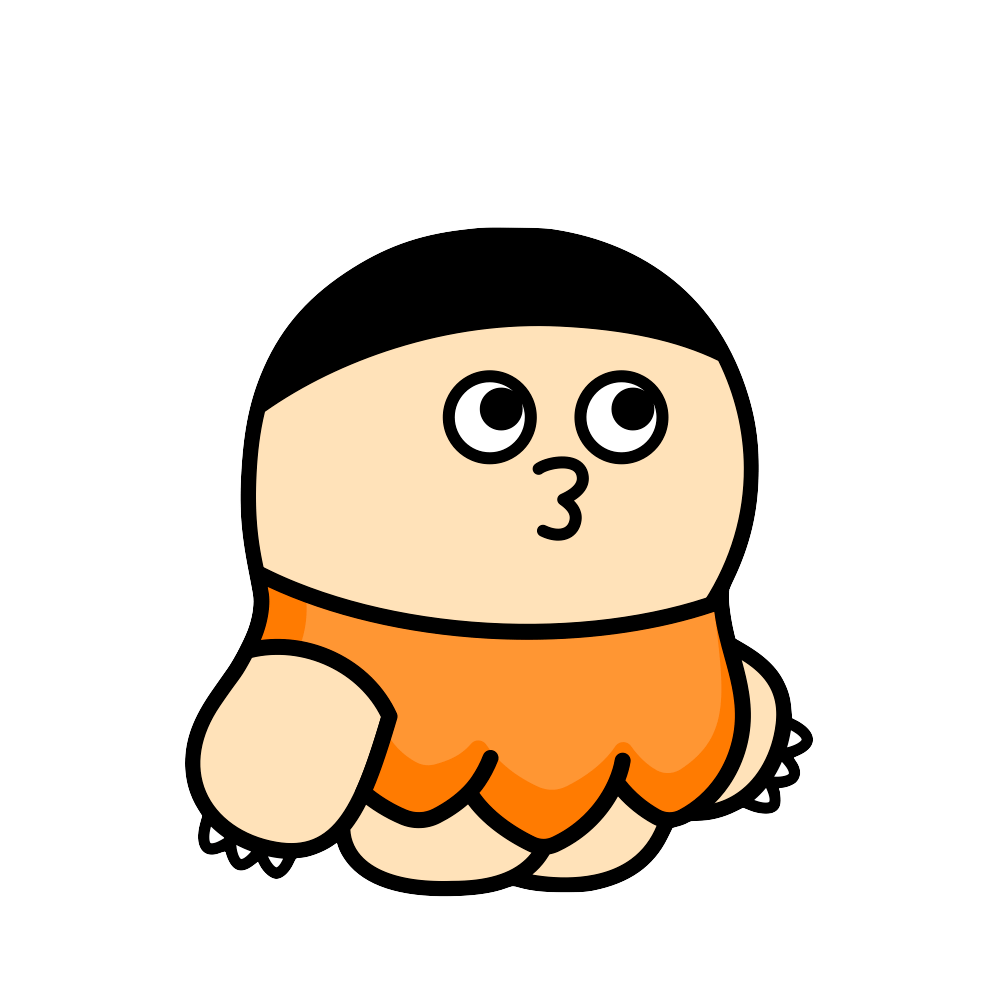
けんすう(古川健介)
アル株式会社代表取締役
学生時代からインターネットサービスに携わり、2006年株式会社リクルートに入社。新規事業担当を経て、2009年に株式会社ロケットスタート(のちの株式会社nanapi)を創業。2014年にKDDIグループにジョインし、Supership株式会社取締役に就任。2018年から現職。会員制ビジネスメディア「アル開発室」において、ほぼ毎日記事を投稿中。
X:https://x.com/kensuu
note:https://kensuu.com
で、その応用として、「他人の人生を物語にする」っていうことをAIにやらせたりしてます。
たとえば今日これから会う人がいるとき、その人についてディープリサーチしてもらって、その人の歩みを小説風にまとめてもらう。
正直、AIが書く小説って全然つまらない。でも企業の広告漫画みたいな感じで、読めはするんですよ。だから、箇条書きで並んだ経歴を眺めるよりも断然頭に入ってくるんです。
市場の「構造」を分解して、最適な戦略を選ぶ
もう一つ、AIの強みだなと感じてるのが「構造理解」の力ですね。
たとえば自分がYouTubeを始めるなら、AIに「アメリカのYouTuberたちは、どういうビジネスモデルで稼いでいるのか?」って聞いて調べてもらって、その結果を10個とかに分類してもらうんです。すると、広告費で稼いでる人もいれば、物販が主軸の人、イベントを展開してる人もいてと、AIがしっかり整理してくれる。
さらに、それぞれの市場規模はどのくらいか、自分の立場に置き換えたらどの道が合っているかまで提案してくれる。これが本当に使いやすい。
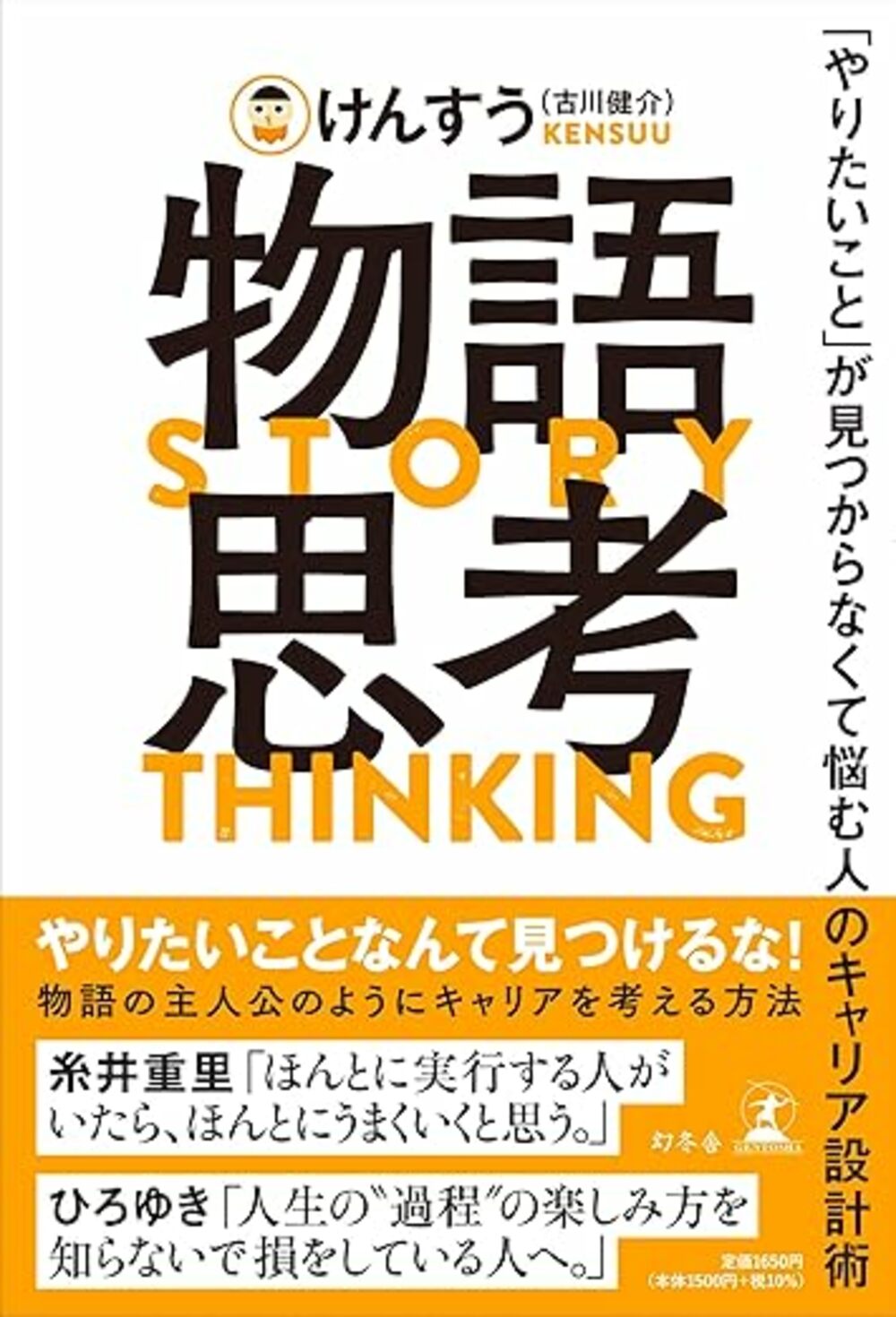 『物語思考 ー「やりたいこと」が見つからなくて悩む人のキャリア設計術』
『物語思考 ー「やりたいこと」が見つからなくて悩む人のキャリア設計術』けんすう(古川健介)著、260ページ、幻冬舎
これの何がいいかっていうと、自分の無意識の“思い込み”を外せることなんですよ。
たとえばYouTuberになるって言ったときに、普通は「広告費で稼ぐ」って考えがち。そうなると、再生回数を増やすことしか考えなくなって、それがうまくいかないと詰む。
でも、「再生回数は少ないけど、グッズ販売でしっかり稼いでいる人もいる」と知っていれば、別の戦略もとれます。
自分の知識だけで考えてると見落としがちなことも、AIに構造化してもらうと気づけるんです。
「無知の知」のためにAIを使う
自分で言うのもあれですけど、AIをうまく使えてる人って、「知らないことに気づく」ためにAIを使ってる人が多い印象です。
「YouTubeの再生回数を増やしたいけど、どうすればいい?」じゃなくて、その前の、そもそも「再生回数を増やす以外に方法はないのか?」ってことを探る。
つまり「自分の考えは完全ではない」と、つねに自己否定の気持ちを持って、自分が知らず知らずにかけてた制限とか思い込みといった“ブレーキを外す”ための道具としてAIを捉えてるんですよね。
「知りたいこと」を教えてくれる単なる検索ツールの上位互換じゃなくて、自分が「知ろうともしていなかったこと」に気づかせてくれるツールとしてAIと付き合うことが大事なんじゃないかと思っています。
(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』に関連したインタビュー記事です。書籍では、AIを賢く使って問題解決するための56の方法を紹介しています)