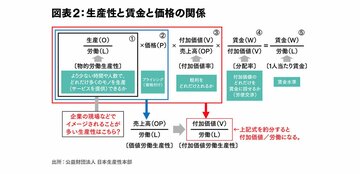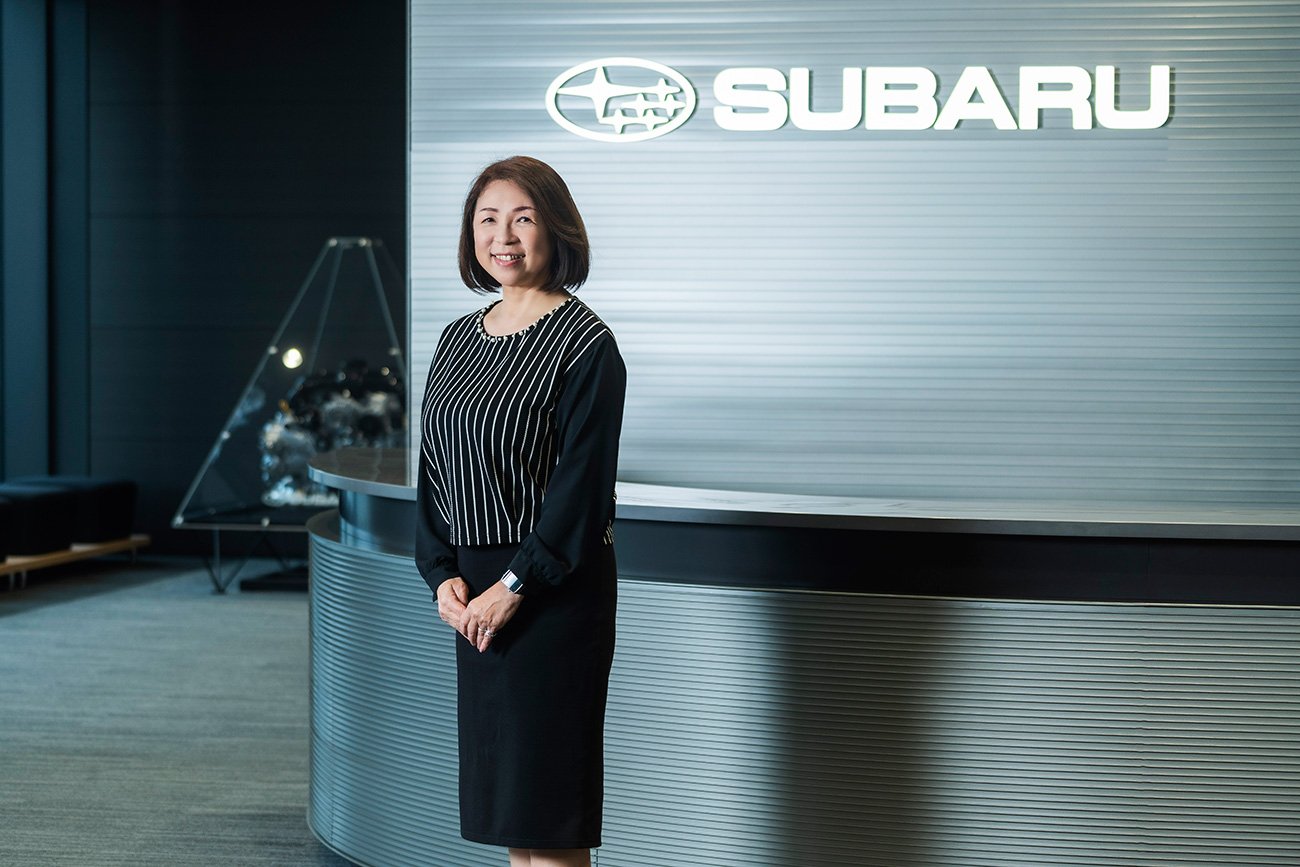
SUBARUでは全社的に遅れていたDX(デジタルトランスフォーメーション)の第1フェーズをコロナ禍を挟みながらも完遂し、2024年からは、DXの定着・深化を進めている。同社執行役員CIO・IT戦略本部長の辻裕里氏へのインタビュー後編では、製造業のDXを成功させる秘訣、女性ならではの視点を生かした生産性向上の施策、ITガバナンスの強化、社内のデジタル人財育成など、多角的な取り組みの実際とCIOの役割について聞いた。
大風呂敷を広げず小さく始めて成功体験を横展開する
大坪 製造業においては特にDX(デジタルトランスフォーメーション)の導入が難しいといわれています。成功の秘訣は何でしょう。
辻 二つあると思います。まず、あまり大きな絵を描き過ぎず、小さなところで成果を目に見える形で出すことです。そうすると仲間が増えて、自分事として捉えられるようになり、横展開されるようになる。製造業は人数が多く、組織構造がしっかりしているため、ひとたび良いと思ってもらえれば、自然に横へと広がっていく。小さくても成功の喜びというのは非常に大事だと考えています。
一方で、IT部門としては、その横展開の際にあたふたせず対応できるよう、裏側ではしっかりとした全体的な青写真を描き、グループ全体やサプライヤーまで含めた広い範囲の設計をして拡張した際の基盤を整えておく必要があります。
大坪 SUBARU Resumeがそれに相当するのでしょうか。
辻 はい。従来、工場の品質問題の報告や改善は紙ベースで行っていましたが、それでは、迅速な対応ができません。そこで、改善記録などをその場でタブレットに入力し、SaaSツールで可視化・分析・共有できるようにしました。こうした量産における品質向上の仕組みが「SUBARU Resume」です。最初は名前もなく、「工場品質活動」などと呼んでいましたが、小さく始めたところ、結果が出たので、名前を付けて広げていきました。
大坪 それは偶然生まれてうまくいったのでしょうか。
辻 SUBARU Resumeは、工場の現場をよく理解しているベテラン社員の「こんなノウハウがあるからデータ化したい」「こんなことができたらいいのに」という強い思いと、ITツールの可能性を知っているIT部門の「こういう技術がある」という知識がうまくマッチし、形になった好例です。
最初は周囲から「価値が見えない」という声もありましたが、無理を承知で話を聞いてもらい、予算を付けて支援し続けました。予算がゼロだと活動自体が萎んでしまうので、1〜2年は見えないところで支えることが必要です。そのおかげで、IT部門が一方的に導入したのではなく、現場起点で小さく始めて、「ITでここまでできる」という手応えとともに、現場でも効果を実感し、横展開が進みました。
現在では、SUBARU Resumeで使っているSaaSツールを、営業系や間接部門でも情報可視化のツールとして活用しています。こうした小さな成功体験の積み重ねが、全社的なDX推進の原動力になっていると思います。