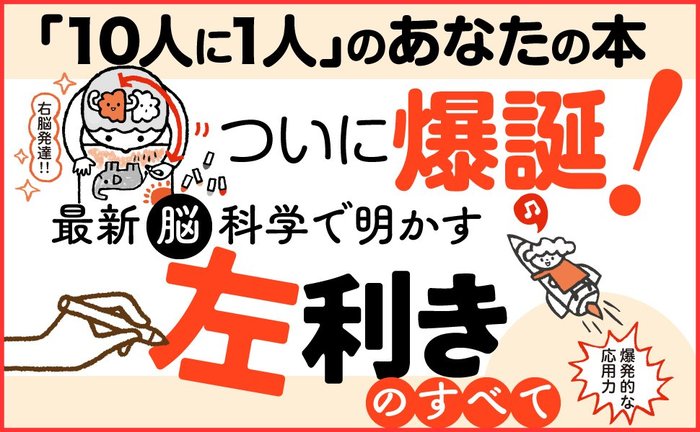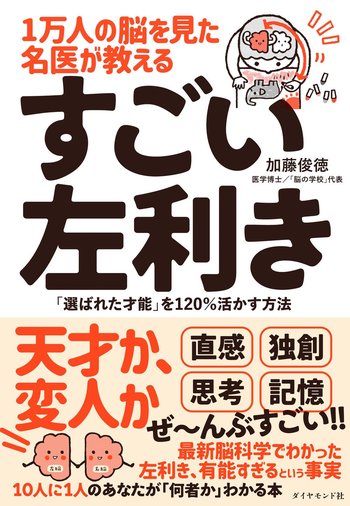「10人に1人」の確率で生まれる左利き。なぜ、左利きの人がいるのか。どのような利点があるのか。自身も左利きの脳内科医・加藤俊徳氏が、筆を執りロングセラーになっているのが『1万人の脳を見た名医が教える すごい左利き』だ。左利きのメリットや特徴を知ることができるだけでなく、「右利きはどうすればいいのか」についても示唆をを得られる1冊。利き手から考える、加藤氏が唱える脳を活性化させる方法とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
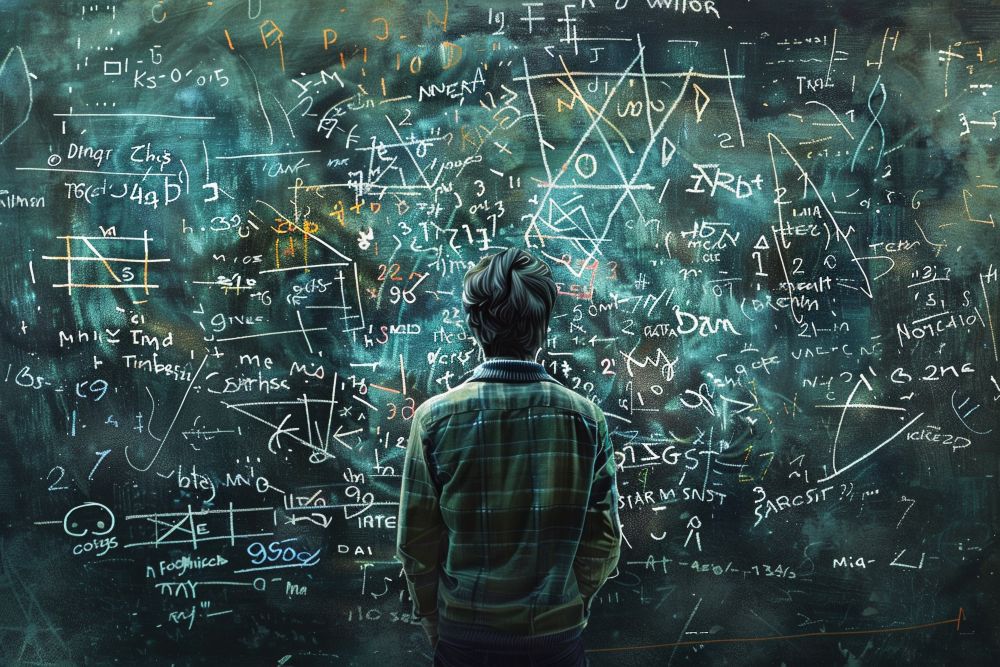 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
直感は、論理的に考えるよりよい結果が出る
アインシュタイン、エジソン、ダーウィンは左利きだったと言われている。
モーツァルト、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ピカソなど世界的な芸術家にも左利きは多い。
近代では、ビル・ゲイツやバラク・オバマなどが左利きであることが知られている。
そんな左利きの人について、その特徴やすごさなどを解説しているのが本書だ。
著者の加藤俊徳氏は、医学博士にして脳内科医。今では世界7000カ所以上の脳研究施設で使われ、脳の活動を近赤外光を用いて計測する「fNIRS法」を1991年に発見した研究者として知られる。
その後、アメリカのミネソタ大学放射線科に招かれ、さらに脳研究を深めて帰国。独自開発した加藤式MRI脳画像診断法を用いて、子どもから超高齢者まで1万人以上を診断、治療を行ってきた。
数多くの執筆歴があり、片づけ、感情、ADHDといった多様なテーマで脳の働きを解き明かしてきた加藤氏が、本書では「左利き」に焦点を当てる。
自身も左利きである加藤氏が、その強みとして「直感力」「独創性」「ワンクッション思考」などを挙げつつ、右利きの人にも役立つ脳の鍛え方を紹介している。
例えば、直感。
誰しも直感で何かを感じることがあるに違いない。なんとなくこっちがいいな。こっちはどういうわけか気乗りしないな……。
「言葉にならない脳の知らせ」と著者は記すが、人はそれを単なる衝動や思いつきと考え、存分に活かせていないという。
オランダの心理学者は、サッカーの専門家とそうでない人を集めて、サッカーリーグの試合の結果を予測させる実験を行った。
すると、時間を与えて熟考するよりも瞬時に判断させたほうが、より正確な結果を予測したのだという。
必要以上に時間をかけすぎると、余計な情報が加わり、かえって予測の精度が悪くなるというのだ。
右脳のデータベースが、鋭い直感を生む
この文章を書いている私は、社会的な成功を手にした多くの経営者や起業家、スポーツ選手や科学者などに取材をしてきたが、意外に感じたことがあった。
著書『彼らが成功する前に大切にしていたこと』に記しているが、例えば、とんでもない確率を乗り越えてポストに就いた大企業のトップの多くが、「実は元々この会社に来るつもりはなかった」などと語っていたのである。
「偶然にも先輩がいた」「友達が説明会に行くので一緒についていった」「時間があったので受けてみた」といった入社理由が多かったのだ。
これもある意味、直感だろう。そして彼らの直感は正しかったことになる。結果的に社長にまで上り詰めたのだから。その会社が自分に合っていたのだ。
だが、「直感は当たったり外れたりするものではない」と著者は記す。
このデータベースが蓄えられるのが、右脳だ。右脳は、モノの形や色、音などの違いを認識し、五感にも密接に関わっている。
一方で左脳は、言語情報を扱い、計算をし、論理的、分析的な思考をする機能を持っている。
つまり、右脳は、視覚や五感をフルに活用した、言語以外のあらゆる情報を無意識のうちに蓄積している巨大なデータベースなのだ。
直感力が優れているとは、このデータベースに大量の情報を送っていたがゆえということになる。
そして、常に左手から右脳に刺激を送り続けている左利きは、膨大なデータからベストな答えを導き出す直感に優れているというわけである。
ただ、これは右利きもこれを意識すればいいということだ。
つまり、直感の精度をあげるには、そもそものデータ量を増やすことが最も大切です。(P.63)
しかし、脳は直接、外界と接することはできない。だから、目や耳、手足などの器官を通じて、情報を運び込まなければいけないのだ。
それは、たくさんの本を読むといった知識の蓄積だけではない。「言葉以外の情報」も重要になるのだ。それを意識して増やすのである。
直感を活かすための3つのステップ
「言葉以外の情報」とは、どんなものなのか。加藤氏は、こんな提案をする。
・コーヒーを淹れたら、お気に入りのカップに入れて香りを楽しむ
・「きれいなもの」「かわいいもの」を見たり集めてみる
・アニメキャラを思い出す
・歩きながら、色のついたものを見つけてみる
・ペットや動物をじっと見つめてみる(P.64)
普段やっているようでやっていないこと。言ってみれば、ちゃんと日常の一つひとつをしっかり意識してみること。それだけでも、直感に磨きをかけることができるというのだ。
そして、直感を活かすための3つのステップを提案する。「直感があることを信じること」「浮かんだことをメモすること」「実際にノートを使って検証すること」だ。
直感は「言葉に残して→検証する」というステップを踏むことで、どんどん磨かれていくからです。(P.76-77)
実際に未来の啓示のようなものを得られたり、患者を一目見ただけですぐに入院を決定したこともあったという。そして検証を続けると、当たる確率がアップすると記す。
さらに直感を伸ばす脳トレを提案する。「散歩をする」もそのひとつだ。
まず、散歩に行く前に、昨日やり残したことを思い出したり、今日の課題を確認したりして頭に入れておきます。
そして散歩をしている間は、課題についてはいったん忘れて、咲き始めた花を見たり、花にとまる蝶の模様に注目したりして、散歩を楽しみます。(P.84-85)
脳には、運動系、記憶系、視覚系、聴覚系、思考系など多くの「脳番地」があるというのが著者の考え方だが、散歩はそれらを活性化させることができるのだ。
他にも「ルーティンになっている行動を変える」「夢分析をしてみる」「浮かんだことに優先順位をつける」「憧れの人だったらどうするか仮定してみる」などの脳トレを提案する。
普段なら思い付かないような直感が湧いてくれば、自分の限界を超え、大きく人生を変えていくことができるかもしれない。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『メモ活』(三笠書房)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。