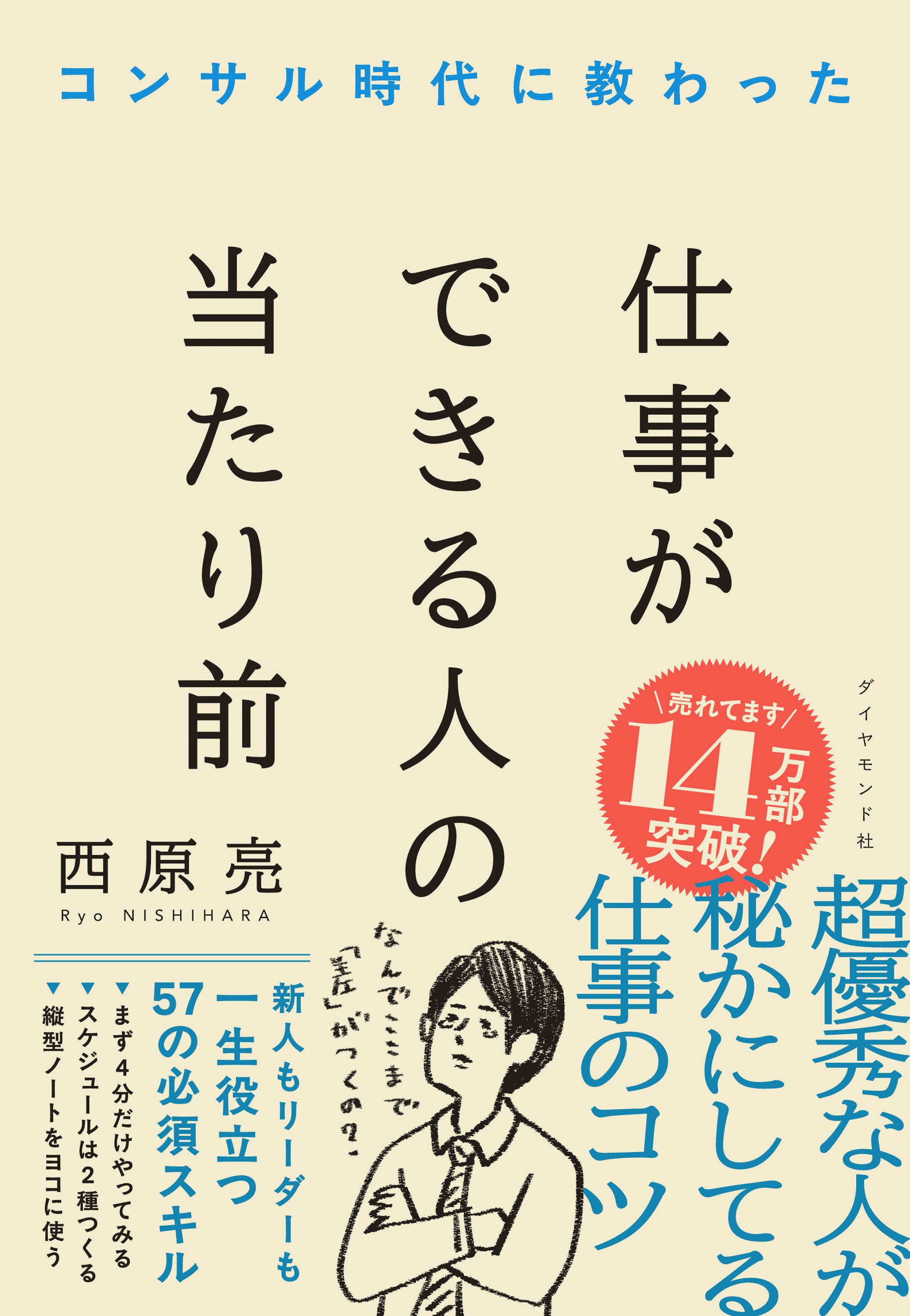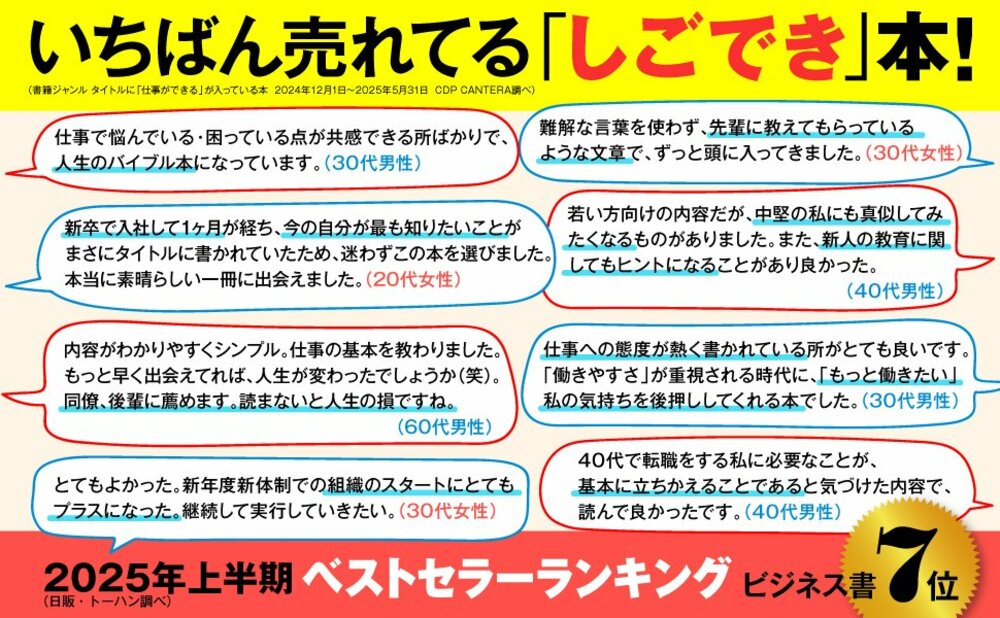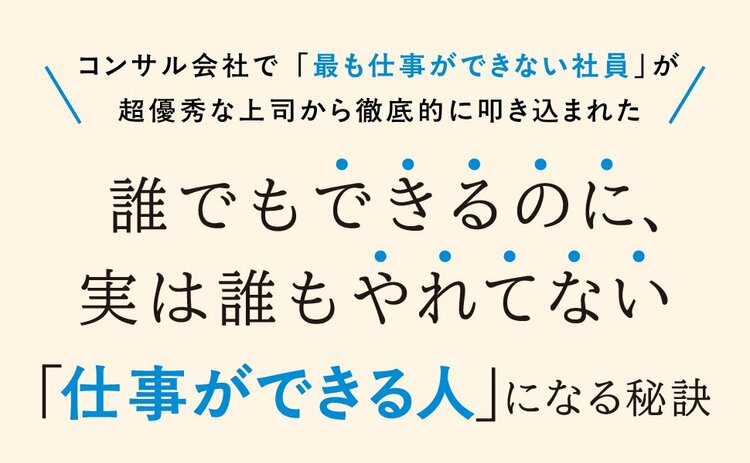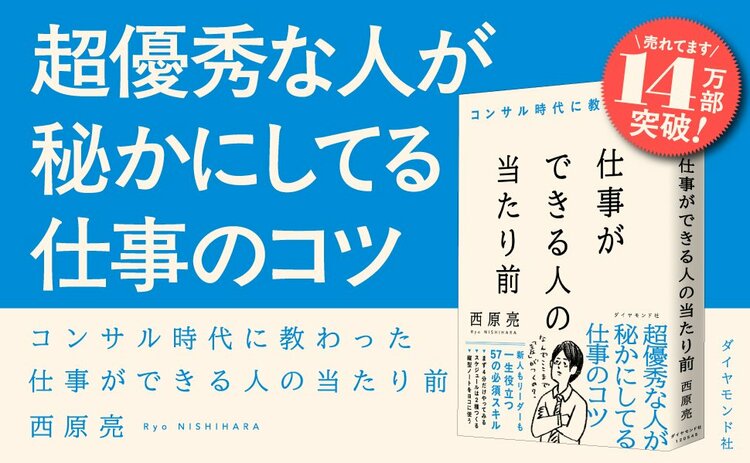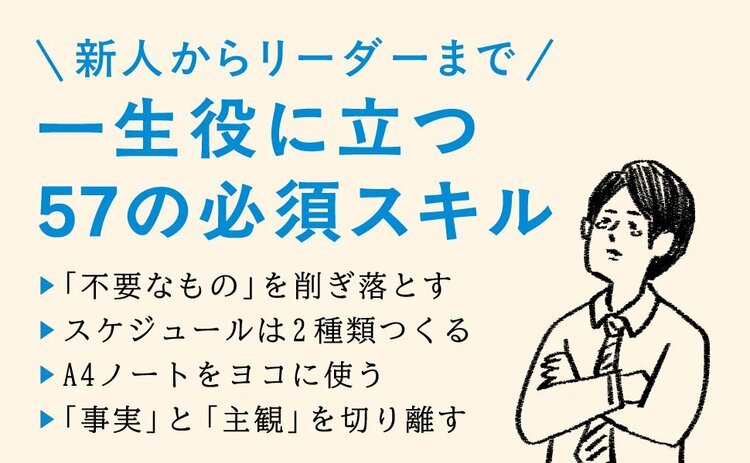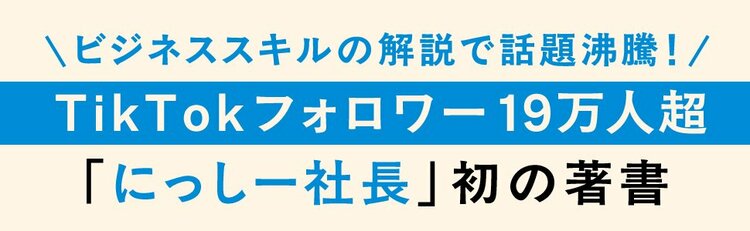「頑張っているのに、結果がついてこない」「必死に仕事をしても締め切りに間に合わない」同僚は次々と仕事を片付け、成果を出し、上司にも信頼されているのに、「なんでこんなに差がつくんだ……」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?
ビジネススキルを発信するTikTokのフォロワーが20万人を超え『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった「超優秀な人が秘かにしている仕事のコツ」を本記事で紹介します。(構成/ダイヤモンド社・林拓馬)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
仕事ができる人は、どのように計画を立てるのか?
計画を作成しなさいと言われている人は、実際非常に多いものです。
そもそも「計画」とは何かというと、それは目標達成のための筋道を立てることを指します。
たとえば「来年、売上を120%アップさせます」という目標を掲げたとします。
その場合、当然その目標を達成するためにどのような道筋を立てるのか、ということを考えなければなりません。
しかし、ほとんどの人がやってしまうことがあります。
それは、単に数字の羅列だけで計画を作ったつもりになってしまうことです。
たとえば極端な例として、「来店人数」「売上」「客単価」「利益」などの数値を、4月、5月、6月、7月といった各月ごとに並べて、「はい、これで計画ができました」と言ってしまうケースです。
ですが、これはただの数字の並びであって、目標達成のための筋道にはまったくなっていないのです。
確かにこの数字の計画は必要ではありますが、それだけでは不十分です。
次に必要になるのは、「これをどうやって実現させるのか」という実行計画です。
例えば、売上の数値が右肩上がりになっていくことを目指すわけですが、それなら「今から来月、どのようにして売上を上げるのか」「来月から再来月に向けて何をするのか」といった具体策を、計画の中に書き込む必要があります。
このためには、具体的な施策をきちんと考えなければなりません。
たとえば「来店客の増加のために何をするのか」「対応品質をどのように上げるのか」「販促施策をどう進めるのか」などを、月ごとに明確にし、それを実行計画として立てるのです。
そして「この施策をやることで、この数値が上がる」というロジックをしっかり示すことが大切です。
しかし、これだけでもまだ十分とは言えません。
実際にこれを実行するのは社員やスタッフなどのメンバーです。
このメンバーそれぞれがより高いパフォーマンスを発揮できるようにするために、「行動計画」が必要になります。
行動計画とは、目標が設定され、目標達成のためのアクションプランが決まった後に、それを確実に実行できるようにするためのものです。
現場では、さまざまな問題やトラブルが発生します。
それを乗り越えるために、「この人は1週間単位で何をするのか」「それによって何を達成し、何を得るのか」ということを、メンバーごとに週単位で具体的にセットしていきます。
こうして、各メンバーがこの行動計画を達成することで、実行計画の目標が実現し、最終的に数値計画で示した目標の達成へとつながるロジックをしっかり作る必要があるのです。
これが、基本的な計画の立て方です。
多くの人は、数字を並べただけで「計画ができました。あとはみんなで頑張りましょう」と言ってしまいがちです。
ですが、それでは現場が迷ってしまいます。
必ず、「数字の計画」「実行計画」、そして「メンバーレベルの行動計画」まで落とし込むこと。
それが、良い計画につながります。
ぜひ皆さん、明日から実践してみてください。
(本記事は『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者、西原亮氏が特別に書き下ろしたものです)