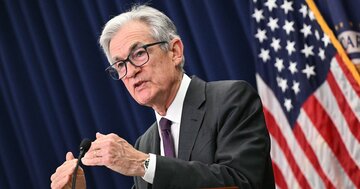Photo:Win McNamee/gettyimages
Photo:Win McNamee/gettyimages
相互関税「一律15%上乗せ」“騒動”
「適時に修正」は本当か、新たに半導体課税も
日米関税交渉で“合意”した相互関税が8月7日に発動されたが、今後、合意通りの実施となるのかはなお不透明だ。
発動を前に6日付で出された相互関税に関する連邦官報で、各国・地域にかける新たな相互関税率が公示されたが、日本に対しては15%の税率が既存の各品目の税率に上乗せされるというものだった。日本政府は、米国がもともと「15%未満」の関税を課している品目の新税率は一律15%になり、「15%以上」の品目には相互関税は適用しない特例で合意したと説明しているが、このことに官報は触れておらず、特例の適用はEU(欧州連合)だけだ。
訪米中の赤澤経済再生相が急きょ、米側に確認する事態となり、赤澤氏によると、米国側内部の「事務処理のミス」で、米国政府が「適時に大統領令を修正する」ことを確認したという。事業者が払い過ぎた関税はさかのぼって米政府が還付するという。また、自動車関税の15%への引き下げも大統領令の修正と同時期に行うとの言質を得たという。
だが「適時」というのはいつになるのかは「できるだけ早く」というだけでなお曖昧だ。
トランプ大統領は6日には、米国に輸入される半導体についても、生産拠点を米国に造る場合は例外としながら、100%の関税を課す方針を示した。相互関税の合意後も、銅への50%関税発動や医薬品への高率関税賦課を表明しており、今後もトランプ関税の拡大はとどまらない懸念がある。
トランプ政権の関税政策は、当初から方針が二転三転する不確実性があった。
「タリフマン」を自称するトランプ大統領だが、関税を貿易不均衡是正だけでなく、外交や経済安全保障政策などを有利にすすめる「ディール(取引)」手段として過剰に活用することが目立っており、側近に通商・貿易政策の立案、交渉、実施などを取り仕切る“プロ”がいないことが政策の振幅を大きくすることになっている。
こうした政権構造は変わりそうになく、日本企業は、トランプ関税の不確実性や米国の「自国第一」保護主義は続くことを前提に対応を考える必要がある。